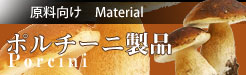7. 美食について
この世に生を受けて生きる喜びと感じられるものは、夢に向かってこれを実現すること、森羅万象に至る感動のひと時を心の通う友と杯を交わすこと、快眠をむさぼること、素敵な異性とデートすること、うまいものを食べうまい酒を飲むこと、など無数にある。
しかし、生きていくために最も必要とされるのは、生を受けて死するまでの間に摂り続けなければならない毎日の食事である。カロリーを摂取しなければ、人は生きていけない。この「食事をする」ことについて言うなら、その人の生い立ち、生まれた土地、生活環境によって、最小限度から最大限度にまで内容に違いが現れてくる。生活に厳しい環境では、生きるために最小限度の摂取カロリーとビタミンを摂ることが要求される。食料に不自由なしに暮らせる地域では、カロリー摂取に加え、どのようにすればおいしいものが食べられるかという問題がテーマになる。
最近のわが国のテレビ番組を見れば、これでもかこれでもかというほど、料理や美食に関する番組が多く見受けられる。こんな現象が見られるようになったわが国は、ある意味では、国民の生活が満ち足りていると言えるのだろう。王侯、貴族ではなく、ごく普通の全ての国民が、このように美食を楽しむことができるようになってきている。銀座や青山、六本木、代官山などの町を歩けば、ありとあらゆる国の料理店が通りのあちこちに見られ、選択に迷うほどである。しかもそれぞれの店は日本の金満振りを象徴していて、インテリアも立派である。もちろん料理に関しても日本人シェフの繊細な美的感覚によって本場を凌ぐ感じさえする。そういう点では日本は世界に冠たる美食天国とも言えよう。
それでも、日本食に関しては素晴らしい料亭が全国津々浦々に至るまで見られるものの、ことフランス料理、イタリア料理などの西洋料理店に関しては、大企業や諸官庁が集中する一部の都会に見られる程度であり、まだ発展途上にあると言えよう。しかし、近年、イタメシブームといわれる現象によってイタリア料理店が全国的な広がりを見せているので、そのうち、日本全国のどの地方都市でも、洋食を代表するものとして、いくつかの立派なイタリアンレストランが必ず人気を得るようになるだろう。
日本料理はさすがに長い歴史と伝統に裏打ちされ、店も職人も客も一体となって、「食」の場を盛り上げている。この点に関しては、わが国の食に関する文化の優越性を世界に強調できると言えよう。
日本のフランス料理店での店側のサービスや客の様子などからは、次のようなことが言えるだろう。いままでのフランス料理店では店や客が作り出す雰囲気にぎこちなさが感じられたものであるが、近年の10年において店側のサービスも急速に改善されて心地良いものになってきていることは事実で、喜ばしいことである。ワインブームもあってソムリエたちの活躍も著しく、メトル・ドテル(給仕長)もさりげないサービスで食事の場を楽しくさせてくれるようになった。まず何よりも、若手シェフによる工夫と研鑽が本場をさえ凌ぐ腕前になってきて、メニューが豊かになってきたことを見逃すわけにいかない。
20年ほど前だろうか。パリの老舗で昭和天皇も訪仏の際にお立ち寄りになったことがある鴨料理専門のレストランが、日本で初めて某有名ホテルにオープンされたので開店1ヶ月ぐらいのときに食事に出かけた。まだ開店間もないこともあって、メトル・ドテルやギャルソンが張り切りすぎていて、こちらはゆっくり食事をしたいと思っているのに、メニューの内容はどうだとかこうだとか、必要以上に解説してくるのには辟易したことがある。しかも、それぞれの係りの存在が必要以上に強調されていて、最も必要なときに、さりげなく振舞うべき動作に欠けていて失望したのである。食事の時間は、ゆっくりくつろいで美味を愉しむものであるのに、これでは料理の講習会とかテーブルマナーの勉強会に行ったようで落ち着かないことこの上ない。そんなわかりきったことを、いちいち説明されなくても、自分の方がはるかに食材などには精通しているのにと思う人もいるであろう。そのような場合は丁寧というよりむしろ失礼なギャルソンと思われるに決まっている。聞かれたことに答えれば良いのである。
今はさすがに有名ホテルに入っている店だけに、サービスも洗練されてきていると聞いているが。このようなことは、まだ地方の店や東京などでも新しく開店したばかりの店などで見かけられる。
真のサービスとは、客が何かを知りたがっている、何かを欲しているという挙動を確認したときのみ、さりげなく対応すべきある。たとえば、ホテルリッツやクリヨンなどのサービスと比較してみると違いは明らかである。パリのホテルリッツは200に満たない客室の、日本でいえば、ごく小さなホテルであるが、その中で働いている人間は600人前後だという。1室あたり3人が配置されているわけだが、何度訪れてみても、そのような大量の人が働いているとはとても思えないほどさりげないサービスが行われている。
ダイニングにしても、人影まばらということはないが、とりたててギャルソンの動きが目立つということはない。しかしながら、客の方で水が飲みたい、メニューの選択に迷っている、ワインはどれにしようなど、少しでも用事がありそうな様子がうかがわれるときには、どこからともなくスーッとそばに来て、こちらの事情を的確に把握し、さりげなく対応し、すぐさま処理してくれるのである。最初のうちは、あまりにもスムーズで、かつ、さりげないので、気にも留めなかったが、何度か出入りすると、その繊細極まりないサービスに驚くべき配慮を感じるようになって、少しばかり勘定書きが高くついても十分に納得することになるのである。
フランスやイタリアのレストランでは、このような一部の超高級店に限らず、町の人口が1万人に満たないような片田舎のレストランにおいても配慮に満ちた温かいサービスを受けることが多い。
その点、日本ではまだ歴史が浅いので責めることはできないが、そろそろ習熟していただいて、もっと食事を楽しめるようになっても良い頃ではないかと思っている。
最近はテレビでも料理に関する番組は驚くほど多く、うれしい限りである。中でも、某テレビ番組で視聴率を上げることに貢献した服部氏や石鍋氏、坂井信行氏などは、日本全国に広くフランス料理というものに対する知識を広め、素材などを紹介したことで特筆すべきものがあろう。もちろん中国料理の陳健一氏や周富徳氏、日本料理の道場六三郎氏もそうである。愛嬌ある笑顔の山田宏巳氏にいたっては、イタリア料理をお茶の間に浸透させたことで大きく貢献したと言えよう。日本全体が料理に関して、貪欲なくらい、関心を高めたのは、これらの料理番組が茶の間に多く放送されるようになってからである。いまやテレビをつければ、必ずどこかで料理に関する番組が放送されており、食べる側の人たちの関心をいやが上にも高めている。
西洋料理にワインは欠かせない。ワインの世界でも田崎真也氏のような世界大会でグランプリを獲得したソムリエが出現し、雑誌やテレビに登場しては、さまざまな料理との相性によるワインの紹介、また、それぞれのワインの特性について紹介して、日本人の食と酒に対する興味をいっそう高めた。これはまた、家庭における西洋料理の材料やワインの消費に結びついて、我々の食生活に潤いと豊かさをつくり出してきたと言える。
今やフランスにおいて、イタリアにおいて、それぞれの有名レストランに日本人従業員のいないことは無い。こんな場所にもいるのかと思われるほど、修業を目的とする若者が働いている。もちろんその結果として、シェフなどの重要な仕事を現地で任せられる人達も多くなっている。また、充分に修業を積んだ後で日本に帰り、レストランの厨房を任せられている人たちも多い。今では何も本場に行かなくても、溢れるような料理情報、食材調達などの助けもあり、居ながらにして充分に料理技術の習得が可能なまで、日本の料理界の内容は高いものになっている。
有名シェフについては、雑誌、テレビなどに登場する機会も多く、全国的にもよく知られている。現在、日本で活躍するベスト30のシェフのそれぞれは、本場イタリアに行っても、ベスト30位に入るだけの技量を備えているのではないかと思われる。日本人客のニーズや店の経営方針などにより、また、利潤も考えなければならず、本場ほどにメニューに多様性は持たせられないかも知れないが、料理そのものの腕前はむしろ本場以上のものを持っているのではないかと思う。
ホテル西洋銀座のイタリアンレストラン「アトーレ」の室井氏には親しくさせてもらっている。小生の会社はピエモンテ州クネオという町にあるイタリア高級食材メーカーであるイナウディ・クレメンテ社の日本総代理店をしているが、室井氏は若い頃にこの近郊のレストランで修業したことがあり、イナウディ氏は彼を知っていたのである。そのイナウディ氏からはよく室井氏のことを聞かされた。いわく、彼が日本に帰ることは止められなかったが、彼ほどの腕があれば、イタリア中のどこの店に行っても有名シェフになれるだろう。日本ではどうしているのかと。小生は、日本でもやはり大活躍をしていると答えるのだが、イナウディ氏は、彼ほどの腕なら、イタリア最高のイタリアンレストランで腕をふるって欲しいのにと言って悔しがっていたほどだ。
ちなみに室井氏はポルチーニやトリフの仕入れのために、アレキサンドリアのレストランにいるとき、しばしばイナウディ社の客になっていたのである。イナウディ社のクレメンテ社長は、アルバのトリフやピエモンテのポルチーニを仕切る立場にいて、イタリア中の有名レストランのシェフのみならず、ヨーロッパの王族や、高級食料店に通暁しているグルメ中のグルメである。
アルポルトの片岡氏、アルポンテの原氏、アクアパッツァの日高氏、エノテカピンキオーリの辻氏、カステッロの山田氏、ジャルディーノの石崎氏、ダ・ノイの小野氏、ヒロの山田氏、ベットラの落合氏、ペペ・ロッソの遠藤氏、ラ・ゴーラの澤口氏、リストランテ山崎の濱崎氏、その他の多くのシェフの方々にも仕事を通じて多大なお世話になっている。しかしこのような極めて優秀なシェフの方々に限らず、今の日本では若年の実力のあるシェフが次から次へと輩出しているので、ベテランのシェフといえども、のんびりとはしていられないであろう。
このような食の環境の中で、多彩な料理を通じて味を判別する顧客のグルメ度もますます高まっている。いくら料理人が良いものを作っても、食べる方にその反応がなければ、次第に料理の方も質が落ちていくし、しまいには、つまらないものになってしまう。
イタリアという国は食以外にもファッションとか歴史の遺跡、そして美術や風景にも見るべきものが無尽にあり、またサッカー熱も高い。その結果として、若い学生から老人にいたるまで、日本からイタリアへ出掛けていく旅行者が増えてきた。それによって、本場のイタリア料理を口にする人々が多くなり、現地の高級レストランで食事をして帰ってくる日本人も増えた。食材に関する情報もあふれている。客側の人間は、少しばかり味の良い料理では満足できなくて、次から次へとオープンする人気店での食べ歩きをするようになってきている。今では客から、ああすべき、こうすべき、といった注文が正確に出てきているように思われて、シェフの方々のご苦労が思いやられる。
美食をするということは、衣装の贅沢と並んで庶民にとって、最も贅沢な愉しみに思えるが、衣装は一度買えば何度も利用できるのに対し、一晩のワインを楽しみながらの高価な食事というものは、5~6時間もすれば完全に体内から消え去ってしまう。その意味では、なによりも贅沢な行為と言え無くはない。しかし、舌先に残る味覚の余韻や、食事をとりながらの親しい者との語らいは、心の中に深く残ってこれこそが至福の時と思わせられる。日本人の生活が、ものには何不自由なくなってきた最近になって、本当の暮らしの贅沢が味わえるようになったのである。その点では、これ以上に結構なことはないと思われる。
小生(1944年生)が社会に出た頃は、先輩から、カツ丼をごちそうしてやると言われれば心から喜んだものだし、それ以前には、デコラのテーブルに安っぽいビニールパイプの椅子の安食堂(当時全国的にどこにでもあった)で支那ソバをごちそうすると言われても嬉しかったものである。
農産物の品種改良により凶作の心配が無くなったこと、経済力の向上、そして流通網の発達などによって、人間はカロリー摂取のためにだけ食べるということから、次第に美味なるものへの関心を高め、美食にいたるようになった。
アメリカやドイツやイギリスの食卓では、ビタミンとカロリーの摂取さえ満たされれば味はどうでもよいといったような傾向が共通するが、近年では都会を中心に次第に美食の方向に向かっていると思われる。小生の推測では、20~30年もすれば、アングロサクソン系の国でもゲルマン系の国でも、それぞれの特徴を打ち出しながら、飽食の後に真のグルメ文化が育つに違いないと思っている。西洋には、グルメ(美食家)になるためにはグルマン(大食漢、食道楽)の時を経なければ到達しないといわれる通説があるが、これらの国の人もこれからグルメの方向に向かうのではないかと考える。
さて、筆者自身が食材を求めて世界を飛び回るという仕事をするようになったきっかけについて述べてみたい。
筆者は1944年、つまり日本が敗戦を前にした戦時下に東北の片田舎に生まれた。カロリーとビタミンの補給をすれば食生活はこと足りる。食事が美味い、不味いなどと申し立てることのできるような環境では育たなかった。しかし、生家の家業は穀物や油糧等を扱う、今で言う農家相手の農協のような仕事をしていた関係で、倉庫の中には小豆や馬鈴薯を始めとする農産物が100トン単位で山積みされていたのである。したがって神田の青果市場や名古屋や大阪の各市場から商品にクレームがきたとか、あそこの商品の質が良いとか悪いとかという話題を子守歌のようにして育ったのである。
殊に羊羹で有名な虎屋黒川に納入する大納言小豆については、おばちゃん達がずらりと並んで、一粒一粒最良質のものを調達すべく作業をしていたその姿を見て育ったのであるが、そのことから世間には食のレベルというものがあるということについて自然に知らされたように思える。
青森での高校時代、同じ高校の一級下の後輩の勉強を見てくれと頼まれて、通学に難のある冬の時期に限って、3食付の下宿を無料で提供してもらったことがある。そこは青森を代表する珍味で有名な家で、小生は下宿をさせてもらいながらその家の長男の勉強を見たのである。その後、大阪で住友信託銀行に入社したが、途中で大学受験に転じ、その後気分転換のため、京都や奈良の古寺、遺跡を巡りたくて、ある方の紹介によって京都で3食付の居候のアルバイトを許されることになるのだが、これもまた珍味屋であった。
居候を許される代わりに、毎朝京都駅に荷物を取りに行くことと、一日3~4時間オートバイで品物を配達することが仕事であった。嵐山の「吉兆」、三条京阪の「辻留」、木屋町の「たん熊」、そして大阪の「なだ万」や「花外楼」、有馬温泉の「古泉閣」、甲陽園の「はり半」など、今にして考えると、日本の名店と言える料亭に毎日のように出かけて勝手口から入り込んで、調理場に珍味を届けたのである。貴船の「ふじや」や「ひろ屋」には2日おきに行った記憶がある。そのようなことを、京都の古都見物をしながら3ヶ月ほど続けたのである。
その頃の小生の将来に対する思いは、外交官や政治家を志すことにあった。現在の地中海フーズ株式会社を創業する、あるいは食に関係する商売に関わるなど全く予想すらしなかった。天下国家のありようにしか興味は無かったのである。しかしながら、そのようなアルバイトを続けながら、将来社会に出たら、いずれの日かこのような場所に来て食事ができたらと思い、憧れを抱いていたのである。
しかし、人生は、考える方向とは別の方向へ動きだし、やがて土地開発業務に携わるようになるのである。ある程度社業も順調にいって、接待や飲食の機会が頻繁に増えるにつれ、それまで勝手口から出入りしていた店にも、20代後半には客として出入りするようになり、そのほとんどの店で食べ歩きをすることが楽しみになったのである。好きな京都へは頻繁に出かけ、特に貴船にはよく出かけたものである。
その当時は社業も順調過ぎるほどに順調にいき、仙台の国税から一週間近く3人の査察官が来て調べられたこともあり、また面白いことに3億円事件の犯人ではないかと警察に密告するものがあって、電話などで、時の捜査官平塚八兵衛氏とやりあったこともある。当時の?末は、青森県警や野辺地警察署に残っているに違いない。むろん、小生の無罪は仙台の国税による査察によって理路整然として解決されているのであり、今は笑い話であるが当時あまりにも頻繁に欧州旅行などするので、スイスの銀行に金を預けているのではと勘ぐられたらしい。
小生が食べることに興味を持つようになったきっかけのひとつには、現在、青森県、特に南部地方で知られている「スーパー・ヤマヨ」の創業者、島谷勘吉氏との出会いも関係している。彼は30年ほど前には、老舗の魚屋の二代目であった。兄の同級ということもあって、隣の町で事業所を開設した小生の良き理解者でもあった。朝、市場に行って仕事を終えると、その後、昼寝から就寝まで、一年365日のうち350日ぐらいの時間を小生の事務所と自宅で過ごすようになったのである。もちろん、始終新鮮な魚や珍味を携えてのことである。
スーパーという小売りの形態が国内に普及し始めた頃、島谷氏もスーパー業界に乗り出すべき時期を迎えていたのである。ちょうどその頃、小生もアメリカに用事があって、アメリカに行くと言い出したら、オレも一緒に行くと言い出し、結局5週間にわたって、全米、カナダの要所を視察したのである。そのときの、彼の食に関する知識欲には貪欲なものがあった。旅行中、美味なるものを求めて、毎日あちこちへとくり出したのである。その時にニューヨークやメキシコなど各地で一流のレストランを食べ歩いたことも若き日の思い出だ。
しかしながら小生の旅行歴の始まりは決して美食を求めてのものでは無かった。そのことは今でも変わらないが、結果的には口に合う食事を求めて意識するしないにかかわらず旅程が組まれていることについては否定できない。おいしい食べ物を出すレストランがあれば急遽旅程を変えたりすることが頻繁だからである。
その結果、これ以上カロリーを摂りすぎてはいけないとドクターストップがかかっている状態で、自業自得というべきなのであろう。
<イギリスの食事>
イギリスの食事は、その味覚等のレベルでドイツに共通している部分もあり、同時にアメリカにも共通するのでイギリスを中心にこれらの国のことも書くことにする。北欧、いわゆるスカンジナビアについては少し異なると思われる部分があるが、概ねアングロサクソン、ゲルマンと同じものとしてここに加える。
さて、何から書けばよいのかとふと考えさせられるのは何故だろうか。初めてロンドンに出かけたとき、ヒースロー空港に着陸する機上から、あれがテームズ川だ、ロンドンブリッジだと感激を味わったが、この国の料理についてはあまり満足した想い出はない。最初の頃は当然ローストビーフを頻繁に注文し、時にはフィッシュ・アンド・チップスを頼んだりしたのだが、毎日このようなものでは物足りなくなり、ソーホーやピカデリー近辺にある中華料理店に入って空腹を満たしたものである。
ロンドンの中華は日本のあっさりしたものと違いラーメンなどは具材が豊富に入って贅沢な気はしたが、やはり日本で慣れ親しんだ麺の、のどごしや舌ざわりとはどこか違っていて、美味しいけれど満足しきれない感じがする。結局、何倍か高くつくのを覚悟しながら日本食を食べさせてくれる所を探して、やっとほっとして、その後パブで一杯ひっかけてホテルに帰るというパターンが繰り返されることになったのである。
小生は元々甘くておいしいデザートは好きなのだが、近頃はカロリー制限の必要から、これらを敬遠しているので、お菓子などについて論ずる資格はないが、この国におけるアフタヌーンティーという喫茶の習慣は心地良く気に入っている。素晴らしい形式美もあり洗練されている。ナイトブリッジのハロッズなどに立ち寄ったなら、近くにあるホテルのティールームでゆっくりと時を過ごすことなどは、優雅この上ない。その後メイフェアをそぞろ歩きをすれば、ロンドンの良さが伝わってくる。
あえてこの国の食事の楽しみを挙げるなら、ホテルで早朝に受けるモーニングサービスだろう。この給仕のスタイルは最近では徐々にすたれつつあると推測するのだが、早朝にドアのノックでまず目覚めさせられ、まだ眠気が残りベッドから起き出せない状態の時に、メイドがカートに紅茶やベーコンエッグ、パンなどを乗せ、ベッドサイドに朝食のセットをしてくれ、ベッドにいるままで食事につくのであるが、これ以上贅沢なことはない。まるで貴族にでもなったのではないかと思わせるに充分である。この朝食のスタイルはイギリス独特のものであるようである。
クラリッジスやサボイのホテルのダイニングも荘重にして厳粛な感じがしてこれはこれで良い。ボーイがタキシードではなく燕尾服を着て恭しく給仕してくれるので、こっちは良い気持ちになる。30そこそこの若造に、背が高く、姿勢も良く、気品に満ちたりゅうとしたボーイが給仕してくれたので、良い気分になったのである。その雰囲気のみで満足させられた思いが強く、どんなものを食べたかについての印象がない。モーニングサービスといい、ディナーといい、テーブルマナーを大切にして、食事の時間中は少し気取った雰囲気の時が流れるが、味については大いに問題があるようである。食事の形式美については威厳があって申し分ない。
ロンドンでは料理界の変化が著しいらしい。最近のことはあまり詳しくないが、妻の親しい友人にロンドン郊外の大学で教えている人がおり、帰国時に我が家にも泊まったりするので、新しい情報も入ってくる。
ロンドンでは最近になってようやく、各国の特徴ある専門料理店が多くなっているということを聞いた。中でもチェルシーあたりでは寿司屋がずいぶん流行っていて、日本で食べるよりは安くて美味しいらしい。他の地域にも寿司のブームは広がり(ベジタリアンが多いこと、ヨーロッパを騒がせている狂牛病も影響しているらしい)、各地で回転寿司が大繁盛しているということである。フランス料理店やイタリア料理店のメニューも豊かなものになって、ロンドンの飲食事情は面目を一新しているという。
ロンドンなど(ロンドンに限らずヨーロッパ全体を周って感じることであるが)、その国の首都や都会などで会食する場合は、通り一遍で誰にでも入れるような場所に本当に良いレストランはないということである。ましてイギリスはクラブ制度の本家本元であることから、観光客など部外者がガイドブック片手に歩いたとしても真に美味しいレストランを探すのは難しいのかも知れない。しかし味について言うなら、サボイやクラリッジスなどのダイニングルームにおいてさえも、やはりイギリス料理はイギリスの料理であると感じさせられる。つまり、食べる人、そして作る人の舌感覚はフランスやイタリアとは大きく異なっている事実は否めない。
前述のようにベッドサイドでとる朝の食事は非常に優雅なものであった。最近ではかなり上質なホテルでも、ビュッフェスタイルが主流になってきており、自分のその日の体調に合わせて食を選べ、また、自分の口にあったものを必要な分量取ることができるので、これはこれとして便利である。ブリティッシュスタイルの朝食の場合は、量が多く、食べきれないほどのものが出てくる。イギリス、そしてドイツやスイスでは特にそうであるが、朝食時にシリアル(ミューズリー)が何種類も豊富にボウルに盛り込まれて並んでいるのは素晴らしい。宿泊するホテルによって、朝食にもばらつきはあるかも知れないが。
イギリスなどではむしろロンドンといった大都市より、地方都市のヨークやチェスター、エジンバラなどに出かけてみると、地方特産の魚類などに美味なるものがある。ドーバーやブライトン辺りで、ドーバーソール(ひらめ)をムニエルやグリルにしてもらい、食すのはなかなか良かった。小生の経験では、エジンバラ近くの北海の海岸の、名も知らない漁村で食べたメルルーサのフライなどは絶品とも言える味であった。身が分厚く、色の白い揚げたてのメルルーサは、鮮度の良いこともあって本当に美味しかった。これらの国々では魚を生で食べる習慣が無く、どんな魚も加工するか即冷凍をする。日本人はどうしても活き魚にこだわるが、海から揚げて生け簀で生かされている魚ほど味のつまらないものはないという人も多い。プランクトンの豊富な海の中にいてこそ美味しさが感じられるのに生け簀の魚にはそれが無いというのだ。小生もそのように思うがどうであろうか。活の良さと味の良さ、この二つの問題は重要だ。
イギリスの食でその他に特筆するものとしてはインドカレーがある。イギリス中どこに旅してみても、カレーに関しては特に美味しかったように記憶している。これは東インド会社などを通じてイギリスがインドを植民地支配した結果、イギリス本国にインド人の調理人などを多数受け入れたことによるのではないかと察せられる。イギリスでインド料理と言えば多少意外に思うのかも知れないが、パリでベトナム料理やクスクスなどのアラブ料理がおいしいのと共通した理由によるものと考える。
さて、その他のアングロサクソン系、ゲルマン系の人々の食卓である
ドイツは、ソーセージのおいしさを上げることができる。材料のミックスの具合や、各地方の特色による各種のソーセージがあり、料理というより食材として秀逸の部類に入るだろう。ジャガイモをたくさん食べることについては辟易するが・・・。
オランダ、デンマーク、スカンジナビアなどに美味しいものがあるかと思い出しても、ニシンの酢漬け、うなぎの燻製、ビーツ、スモークドサーモンなど、決まりきったものしか浮かんでこない。がその中では、トナカイの肉は調理法にもよるが、苔桃のジャムと合わせると意外に美味しかった。
北欧で忘れてはいけないものがひとつある。タラ料理である。日本のタラは形が小さく、生食で食べるので水っぽいが、その代わり淡泊な良さがあり、鍋料理には適しているようだ。しかし、小生が言うのはこの生タラのことではない。塩干ししたタラのことである。京都の棒ダラとは違うが、乾燥させることによって一層旨みが増し、生ダラとは比較にならない美味な食材になるのだ。クリームソースやパプリカのソース、そしてトマトソースで煮込むのである。戻した塩ダラをオリーブオイルやベーコン油を、ニンニクで炒め、じゃがいもを加えてトマトソースで煮込む料理は各地で見られるが、じつに美味しいもので小生の大好物である。
スペインではバカラオ、ポルトガルではバカリャオ、イタリアでバッカラ、フランスでモリューと呼ぶ。漁獲地ノルウェーでもこれを食すのであるが、どのレストランで食べてもバターとクリームをたっぷり使ったほとんど同じような調理法だけしかなく、味付けについても塩気が強すぎる嫌いがある。供給先のラテン諸国の方が実にさまざまな工夫をして、美味しくタラを料理する。味覚の違いもあるのであろうが、全く別物を食べている気になるのである。北欧の人たちによる魚の調理方法は、単純すぎて日本人の口には、満足できるものではない。
<スウェーデンのあの臭い缶詰の話>
小生が今まで関心を持っている食べ物に、スウェーデンの発酵したニシンの缶詰がある。缶ブタに切れ込みを入れるとシューっと吹き出す例のアレのことである。例のアレといってもわかりにくいが、何という名称なのか不確かなので表現のしようがない。ニシンの塩水漬け発酵食品とでも言えるのだろうか。「くさや」のようにとてつもなく臭い匂いがすることでマスコミでも何度か取り上げられた有名なものだ。雑誌やテレビでこれを見て是非トライしたいものだと思っていたが、2001年の年5月に北欧へ出張し、この缶詰を買い求め、試す機会を得た。
たしかに匂いは強烈であるが、発酵内容は日本の馴鮨にははるかに及ばず、塩辛いだけの他愛の無いもので、京都の鮒ずしとは比較にならないものであった。小さいニシンの頭を取り除き臓物を除かないで、単に塩漬けして缶詰にしたもので、それ以外の工夫はされていない。これを買ったとき、売り場の人も、外国人がよくこんなものを食べるなという顔をしていた。こちらは関心を満たす気持ちと、土産にしてシューっと缶から出てくる強烈な臭いで人を驚かせようという魂胆だったのであるが。
アングロサクソンの延長という意味でアメリカの食べ物について触れると、これはあくまで一般的に言うのだが、美味しいものはない。ハンバーガー、フライドチキン、T-ボ-ンステーキ、コーラetc.。歴史が浅く、文化的にも未成熟なため、仕方のないことかも知れない。
アメリカ料理ではないが、現在はアメリカ料理として米国民の間に浸透している本来はメキシコ料理のタコスやチリビーンズがある。これらはまだ味覚的に日本人にも合うのかも知れない。中にはアメリカのアイスクリームはとても美味しいという人もいるが。
アメリカではビーフステーキをおなか一杯食べたいと思っても、皮をむいていないポテトと350g以上の牛肉のかたまりがドカンと皿にのっているだけで、何の繊細さもない。350g以上と書いたが、それはスタンダードのステーキサイズであって、ニューヨークカットになると500g位の大きさになり、ヒューストンやダラスなどのテキサスで出てくるテキサスカットは650gはありそうで、盛られた皿を見ただけで食欲が減退しそうだ。カロリーとビタミンだけ、と小生が思うゆえんだ。
アメリカで印象に残った一番おいしかった料理はエスキモー(最近ではイヌイットと呼ぶらしい)のコツビューで食べたサラダである。その時はポークソティーの450g位のものを食べていて途中で食べきれなくてイヤになり、口直しにメニューを開いてフレッシュサラダを注文したのであるけれど、まさか北極圏内の氷点下40度という土地でサラダなど食べるとは思ってもいなかった。あまりにも新鮮で美味しかったので聞いてみたら、昨晩我々と一緒の飛行機でカリフォルニアから乗り継いで到着したばかりの新鮮な野菜だったのである。後で判ったが、北極圏のアラスカといえどもアメリカを構成する州である。その中に北辺の国境警備についている米軍の基地があることと、エスキモーの人達のため、150人乗りの航空機の後部を改修し、全体の3分の2くらいのスペースを空けて物資の輸送を主目的にした貨客飛行機を週2便往来させている。それに昨晩乗せられてきて冷蔵庫内で保存され、取り出されたものであるとのことだった(エスキモーでは外気に放りだしておけばすぐに凍結するので、凍結させないために冷蔵庫で保管しなければならない)。
このようなことを考えてみれば、その時のサラダはカリフォルニアの産地で食べればもっと新鮮で美味しかったことは当然であろうが、予期しない出会いに感激することによって胃袋の働きが活発になり、意識による有り難みもこれに加わって、ことさらに美味しく感じたに違いない。美食というものの何たるかについて考えなければならない要素を持っているように思われる。
<フランスの食事>
フランス料理と聞けばなんだか改まった気持ちで、最高に美味しい料理という印象と優雅な雰囲気を想像して、招待されればうきうきした気持ちになる。逆に人にごちそうしなければならないときは、財布の中身が気になる。女性の場合は、何を着ていけばよいのかなど、ソワソワウキウキという気分にさせられるだろう。そもそもこのフランス料理というスタイルは、元来は、フィレンツェのメディチ家の姫がフランスの王族に嫁ぐ際に、嫁ぐ娘に寂しい思いをさせないよう、調理人を帯同させてフランスに送り込んだことがその始まりであるとされている。
フランス料理の始まりは、まずは王族貴族により一般的に普及したものであり、他の国のように農民や漁師の地場料理などから発展した家庭的料理方法とはその始まりが全く異なっており、しかもそれが今日にも続いている。もちろん、今では貴族などは法制的には存在しないことになっているが、ヨーロッパ、特にイギリスなどでは特権階級は潜在的かつ慣習的に厳然として残っている。このような特権階級の人達に支えられ、フランス料理は小市民的食事形態と趣を異にしているのである。庶民の料理形態はフランス家庭料理と呼ばれるものであり、フランス料理店で給仕されるものとは違うのである。
以前はフランス料理店への出入りは、服装などでもそれなりの水準が暗黙のうちに必要とされたようだが、昨今ではアメリカ人に限らず、ヨーロッパの人達でも、ジーンズにラフないでたちで堂々とレストランに出入りしている。このことは、現代の王侯貴族というものに対する解釈が時代とともに穏やかに変化して、スポーツ貴族やマスメディアの作った貴族、ロックミュージシャンなどの成り金貴族など、あらゆる分野における身分や出自に関係ない生活貴族を生み出している現代の世相にマッチしているのである。
改まったフランス料理店での会食に出かければ、1日だけでも王侯貴族になったような雰囲気にさせてくれる。フランス料理にはそんな魅力がある。荘重華麗なインテリア、メトル・ドテルやギャルソンの物腰、ささやき合うように直情を抑えた会話など、多少の緊張感を意識しながら、自らを抑え気味にして、その場の雰囲気に浸る気分は、何とも形容しがたいスノビズムを感じさせてくれる。
このように王族貴族のために発展したこの食事形式は、近世に至るまでは一般庶民の食することのできないものだった。王族貴族は自らの勢力を誇示するために、居館というか居城とも言える豪華な建物を広大な敷地の中に建てて、定期的に彼ら王族の仲間を招待したりして、その居館を取り囲む猟場において、シギやヤマドリ、野兎、イノシシなどの狩りをして、夜な夜な饗宴を催すことが多かったのである。今のように1泊とかいうものでなく、1週間、2週間と長逗留する場合も多く、時には芸術家や人気の高い詩人や文化人を招いて、月単位に及ぶ食客として、もてなしをすることを自慢し合ったらしい。
そのようなことから、中国の満漢全席に似たフルメニューが食卓に並べ立てられ、考えられないほどの大食によってその場を楽しんだらしい。もっとも人一人の胃袋には自ずと限界があるので、彼らは一旦飲み込んだ食物をもどすことによって、再び胃を空っぽにして延々と饗宴を続けたらしいのである。これならば、いくらでも食べ続けることができるし、肥満防止にもなる、糖尿病や通風対策にもなるのかも知れない。そのような当時の一般常識を今に当てはめて考えたら、とんでもない非常識と思われるかも知れないので、その点は理解しなければならない。
ベルサイユ宮殿のような壮麗かつ豪華極まりない宮殿でのパーティーは、その最たるものであったに違いない。そして料理の残り物はそこで働く人達に分け与えたり、時には城主の誕生日などには、一般庶民にもそのおすそ分けをしたりして恵みを施していたことが当時の風俗などを紹介した書物などから伺われる。
なにはともあれ、その時分の雰囲気などは今のフレンチレストランとは違い、酩酊するほどに鯨飲し、ベルトを緩めて、お腹を抱えるほどに大食したらしいのだ。挙げ句の果てベルサイユ宮殿においてすら、トイレの必要が有れば、移動式トイレで用便、小用を足し、時には窓から外に向かって汚物を投げ捨てるなど、今の尺度で考えればとても粗野でお話にならない類の常識が支配していたのである。
その後フランス革命などの歴史を経て王政や貴族制度が法律的に消滅した後、たとえばブルボン王家であるとかカロリング王家であるとかの王族や領主に抱えられていた料理人も失職する事態になり、結果としてそれらの人々によるレストラン経営によって、フランス料理なるものが普及したとされている。必然的に宮廷料理に近いものが庶民階級まで広がったのである。
当然ながら、ソムリエを伴い、菓子職人、いわゆるパティシェなども含むことになる。そのような饗宴料理としての性格というものは、単に空腹だから食事をするといったものとは当然違っており、美味の追求のためにはあらゆる工夫が重ねられ、食材についても珍味珍肴を要求されたであろう。その中から、フランス料理特有の調理方法が開発されたものと理解される。永い調理研究の歴史あってのフランス料理なのである
何時間も、いや時には何日間もかけて美味を追求したであろうし、他のパーティーには出されていないようなオリジナル料理を用意するために努力したに違いない。これは当然、各家庭で毎日つくられる料理ではマネのできないことである。このようにして発展したフランス料理であればこそ美味にして食べることの幸福感を感じさせてくれるものであろう。
一方家庭料理の内容は、今述べたような理由によってレストランのフランス料理とは全く異なっていて、シンプルでより質素なものである。むしろ、パスタこそあまり食べないものの、イタリア料理法的プロセスやメニュー構成で供される感じがする。もちろんソースを重要視することに変わりがないとしても、素材を手短に利用している。そして作りおきのソースやパテなど家伝の味を大切にしていることが伺われる。フランス料理もイタリア料理と同様に、地域に根ざした個性的な面が当然あり、サヴォア風、リヨン風、プロヴァンス風、マルセイユ風、ブルターニュ風、ノルマンディー風、アルザス風など変化に富んでいる。
フランスはどんな田舎に出かけてもこぎれいで立派なレストランがあり、料理人、給仕人ともに洗練されていて気持ちが良い。レストランの建物が質素なものであったとしても、ダイニングルームはテーブルがきれいにセットされていて驚くほどである。人々が食事、特にレストランで食べる時間を非常に楽しみにしていることが感じられる。ファストフード店もないわけではないが、それよりもむしろ、ゆっくりと心地良い雰囲気の中で美食ができるようになっている。これは、スペインやイタリアなどにも共通しているが、名も知らぬ小さな田舎町にも必ずこぎれいな、食事の美味しいレストランがある。ラテン系の人達は、一家揃っての夕食の時間を神聖視するような習慣があって、生活が豊かでないにしても、食卓はいつもきれいだ。
話が変わるが、冬の寒いパリの街角などでアツアツの焼き栗をほおばる楽しみ、手をかじかませながらうす暗い電灯の下でレモンをきゅっと搾って食べる生牡蠣などは、立ち食いながら美味で、冬の風物詩としてパリになくてはならないものである。パリジェンヌはクレープなども好きなようだ。
そんなひとときのパリを小生は好んでいる。フランスのチーズの美味なることはいわずもがなである。テリーヌ、パテ、チーズはやはりフランスに限る。オンフルールやノルマンディー地方で食べる新鮮なムール貝やひらめなど、またブルターニュのロシェルなどで陸揚げされるオマール海老や牡蠣は絶品である。そういえば「料理の鉄人」番組で誰でも知っている渋谷のロシェルのオーナーである坂井氏はここの土地で修業をしたはずである。小生も仕事を通じてここの総料理長をしている工藤氏にはひとかたならずお世話になっている。
ペリゴールの黒トリュフやフォアグラも外すわけにはいかない。カルカッソンヌやニームなどにはシックで洗練された料理店が多く、何度行っても食べ飽きない。マルセイユのブイヤベースは日本人の大好物だ。このブイヤベースはフランス料理として考えるとやや本流を外れたものであるが魚介の食べ方としては最良のもののひとつであろう。
リヨンは言うまでもなく、ポールボキューズの名店がある場所であるが、今ではそれにも負けないほどに人気のある新進の料理人が育っている。いずれにしても美食の町としてはフランス屈指の地なのである。
マルセイユからリヨンまでの途中にヴァランスというローマ時代からの落ち着いた町があるが、ここにも良い店がある。シャンベリーからジュネーブ寄りに入ったアヌシーの町も良い。リヨンから西のボルドーに向かってクレルモンや温泉地でもあるヴィシーの方面もまた、とても豊かな土地柄である。
エスカルゴやマスタードなどで有名なディジョンに触れる。ここはイタリアで言えばボローニャのように豊かな大地に囲まれて物資が集散する交通の要衝でもある。近くのボーヌの町は素晴らしく魅力のある町でニュイ、ポマール、ジュヴレ・シャンベルタンそしてロマネコンティなどブルゴーニュ地方の良質のワインが取引される町である。ボーヌとディジョンを結ぶ街道の両側には世界でも最も良質のブドウ畑(Cote-d’Or)が広がっている。「美味しいワインがあるところに美味しい料理あり」で、このブルゴーニュには自家製のパテなどを自慢できる小さなオーベルジュやレストランが数多く存在し、人々の気持ちも穏やかでもてなしの心が温かい。
ディジョンからTGVの超特急新幹線に乗ると1時間半もあればパリのリヨン駅に到着する。ここまでの移動はレンタカーよりフランスご自慢の新幹線が良いようだ。パリ・リヨン駅舎の2階にあるフランスレストラン「トランブルー」は程良い大きさで、天井一面にフレスコ画が描かれていて宮廷風の雰囲気を持っている。もちろん料理にしても、ミシュランの星つきの店であり、シャンゼリゼにあるフーケの店と似たようなメニューで統一されている。正統派と呼ぶべきか、およそ、いろいろな国を歩いてみても、駅舎の中にこれほどの立派なレストランを持つのは、ここパリ・リヨン駅をのぞいて見当たらない。これにはそれなりの理由があるのである。あまり飛行機を利用しなかった時代、そして新幹線がない時代のパリでは、ニースやカンヌそしてモナコ、モンテカルロなどのコートダジュールに出かける際には、ここリヨン駅から夜行列車に乗って出かけるのが一般的だった。別れを惜しんだり、また出迎えて食事をしたりといろいろな事情により、会話を愉しめる場所として優雅な人達の離合集散の待合いに利用されたものであろう。無論、現在にしても、世に知れた名店で客を惹きつけている。
パリは、セーヌ川をはさんでサントノーレの真中辺にあるエリゼ宮のあたりを一区として時計回りに二区、三区と渦巻き状に区割りされており、パリの何区に住んでいるかによって、経済状態がどうかとか、どのような職に就いているかなどが推測できるという人もいるが、ここは美食の町で、仮に何区であっても食事は充実している。そのうちでも極め付きは、ヴァンドームからマドレーヌ広場、オペラ座にかけての三角形の中、シャンゼリゼからモンテーニュ通り、トロカデロ広場、凱旋門にかけての内側に集中している。これらの地域のホテルやレストランのレベルは非常に高い。
もし、このあたりの地域の最高級ホテルに滞在し続けたら、あっという間に財布が空っぽになるだろう。しかしレストランについては特別なワインなどを所望しない限り、フルコースをとってもそんなに高くないのである。日本の半分以下の料金で立派なディナーが楽しめる。しかも、メトル・ドテルやギャルソンのサービス、店の雰囲気は日本とは比べ物にならないほど洗練されている。シェフの腕前についてはどうだろう。日本人シェフの腕前は決してフランス人一流シェフに比べても劣ることはないように思える。レストランの経営上の問題を別にして、食材さえ準備されればどのようなメニューでも充分にこなせる力量を今の日本人有名シェフが持っていることは間違いない。ただ店のサービスに関しては、優美さの点ではるかにかなわない。
パリではホテル付属のレストランなどにも素晴らしいものがある。殊にリッツやプラザアテネのメインダイニングは大きさも手頃で華麗さを絵に描いたようである。リッツの気楽なテラス風のダイニングも良い。経営がアラブ系の例のドディ・アルファイド氏(息子は英国のダイアナ王妃と事故死した)に変わってから、正面入口すぐ左側にあったラウンジもなくなってしまった。今のコンシェルジュのカウンターのある右側の奥にパティオ風の小さな(天井は明かり取りのガラス張りがしてある)レストランがあり、最もお気に入りの場所だったのだが、2~3年前に立ち寄ったときには改装されて、無くなってしまったようで少し寂しい気持ちがした。一番奥にあるヘミングウェイバーは当時と変わらず、こじんまりとして落ち着いた雰囲気をかもし出している。ここのカルバドスのX。O。はうまい。小生はここではカルバドスにこだわっている。プラザアテネのメインダイニングは入って正面奥にあるが、ここもやはりパリを代表するホテルの一つとして華麗さに満ちている。華麗さではリッツを超えているのではないだろうか。
ホテルクリヨンのレストランで7~8年前に会食したときのことである。スープがあまりにも塩辛いので、ギャルソンにクレームをつけたら、5分も経たないうちに新しいものと取り替えてくれたが、とにかく塩分がきつくて驚いた。だいたい、西洋人は日本人と比較して25%前後多めの塩分をとるように思うが、それ以上だったのである。そのような場合、決して遠慮しないでクレームを出すべきである。きちんとしたレストランであれば、すぐに対応してくれるはずである。
3~4年前に亡くなった親友の一人で当時全国歯科技工師連盟会長横山勇氏と、インターコンチネンタルホテルを定宿にして奥さん公認でよく遊び歩いたものである。ここまで書いてきて、当時を思い出したら、すこし目頭が熱くなったようだ。また、旅行仲間であり、小生とは一番親しかった日産自動車販売の営業部長だった円谷泰光氏も肝硬変で5年前に亡くなった。当時まだ60歳だったが悔やみきれない気持ちだ。大泉学園に奥さんの節子さんが健在だが、仕事にかまけて、めったに霊前にも行けず申し訳なく思っている。横山氏はガンだったがやはり享年60歳であった。年齢も近く、若い頃からの遊び仲間で、最も親しくしていたので、この本に代えて冥福を祈りたい。
そして小生も今60歳である。親しい両氏を失って、今のうちに自分の来し方を振り返り、費やした時間や内容を考えれば、我ながら良くもこんなに歩いたものだと思えなくもない。60歳というこれまでの積み重なった経験が、たまたまそのような結果になったと思われなくもないが、暇さえあれば旅に出かけていたのであろう。
早くに友を亡くした身にとって、小生もその年齢に近づいているので、それなりに整理整頓して、その地域に関心を持つ旅行者のため、歴史に興味ある人のため、食に関心のある人のために、すこしでも役に立つことが出来ればと思うことが、執筆の大きな動機にもなっている。もう一度断っておきたいことは、旅に関する費用は全て自身の事業からの収益で賄っており、若いときから親の遺産など一円たりとも援助は受けていない。そのことは今紹介した友人2人にしても同じであるが、やはり自分で稼いだ金だから誰に遠慮することもなく遊べたのかもしれない。今にして思えばこの3人はずいぶんと遊びっぷりも良かったが仕事もそれに劣らずしたように思える。
話題がだいぶそれてしまったが、さすがにパリは世界中の人が憧れる「華の都パリ」である。この町には有名で上質なホテルやレストランが無数にあり、ため息が出てくるようである。しかし、本当に美味しい食事がしたかったら、やはりレストランだけを経営している専門店に行くのがよいだろう。バンドーム界隈には、マキシム・ド・パリがあり、また親しく接してもらっているハナエ・モリビル内のパピヨン・ド・パリの上原雄三総料理長の修業したルカ・キャルトンなども近くにある。また、凱旋門近くには、いまパリで注目されている「ステラ・マリス」(日本人シェフ吉野建氏が小田原の繁盛店を引き払って単身パリに乗り込んで今日の評判を確立した)がある。アラン・デュカスやロブションからいずれ近いうちにミシュランの星が獲得できると太鼓判を押されているとのことである。そうなれば文化勲章に匹敵する素晴らしい快挙であり、万歳と快哉を叫びたい。小生は未だこの店を訪れていないので、機会に恵まれたら一度客として訪れてみたいものだ。
その他、イル・ド・フランスと呼ばれるシャンティイやフォンテンブロー、ランブイエの郊外にも多数の名店が揃っている。一昨年宿泊したバルビゾンのオーベルジュの「バ・ブレオ」も宿泊施設は豪華と言うほどではなくむしろ簡素なものであったが真夏の朝日や夕暮れどきに、大樹の下で朝食、夕食と3日間連続してとった食事は、サービス、料理の内容とも素晴らしかった。特に近郊でとれる野菜や果物、チーズなどのメニューが豊富で、中でも殊にパプリカのムースの美味しさが忘れがたいものとなった。
世界の料理の中からどこの国の料理が一番美味しいかと問われれば、小生はフランス料理をあげる。次ぎに中国料理である。欧米人に言わせれば3番目はトルコ料理という人もいるし、ベトナム料理という人もいて、それぞれ違うが、小生の場合、日本人なので、三大料理の中に日本料理を加えている。しかしイタリア料理が一番口に馴染んで好きだし、最も親しみやすいのでこれを三大料理の中に加えたいのだが、ある意味ではフランス料理がこれを代表しているのであえて加えない。フランス料理を誉めてばかり書いたが、この国の人々はベトナム料理やアラブのクスクスなどを好んで食べるし、これらのレストランはフランスの地方都市にも数多くある。もちろんパリなどの大都会ではイタリア食、日本食など、各国の料理店が店を構えていることは当然だ。美食天国であることに間違いない。
しかしながら、フランスのあちこちを旅して1週間も滞在すれば、もちろん日本料理が恋しくなる。日本料理店は値段が結構高いので、そうなると中華料理店やイタリア料理店に入りたくなる。そしてフランスからイタリアに入国することになると、パスタが食べられる。イタリア料理が食べられると思うと、ほっとする。問題はここにある。フランス料理というものは、美食を追求するあまり、コレステロール値が高く連日食べ続ければ胃に負担がかかって、もう結構だと思われる要素を持っている。生クリームやバターを多用することも大きな問題である。家庭料理から出発したわけではないので、美食に偏りすぎ、毎日食するには無理がある。
このような結果からであろうか。約15年ほど前ぐらいから、ヌーベルキュイジーヌなる新語がもてはやされるようになり、それなりに、その道の新進料理人が名をあげることになった。カロリーなども考慮した新作のフランス料理のことで、よりシンプルに盛りつけされている。多分に、日本における京料理のように、皿も盛りつけもより繊細なものになった。これにはフランスに在住する日本人シェフの活躍が大きく貢献したことが広く知られている。ヌーベルキュイジーヌという流れが料理界に与えた影響は大きく、今の料理にかなり反映されているが、最近になってまた以前のようなこってりした伝統的フランス料理に回帰しているようにも思われる。根本的にフランス料理はレストランなど外食で食べることが、そもそもの成り立ちから当然ならば、少しばかりこってりしようが毎日食べるわけでないので、問題はないかも知れない。ディナーは夜8時頃から始まる。そして夜11時過ぎ頃まで、ゆっくりするときには0時を回って午前1時頃に及ぶことも珍しいことではない。週に1度くらいのレストランのフランス料理なら問題はないのだが、連続3日間も続けば、胃が疲れてうんざりすることが多い。いずれにしても小生は日本人である。これを読んでいる日本人の方には小生のフランス料理に関しての意見に同感される方が多いだろうと思っている。
そしてフランス料理店でのマナーについて言えば、小生はほとんどこれを意識したことはない。メニューやワインに関しても知らないと言ってよい。そしてフランス語の知識もほとんどないのであるが、最小限度のフランス語を使って英語で不足を補いながら、その時々の自分の欲求によって、ギャルソンを呼んで、あの人の食べているアレが食べたい、これが飲みたい、と注文するようにしている。その方が結局、自分の求める食事にありつくために一番マトを得ているようだ。初歩的なことを尋ねることは恥ずかしいことかも知れないが、小生はフランス人ではないし、素直に自分が料理について無知であることを告白したところでなんの恥にもならないと、半ば開き直ってそのように思い行動している。
フランス人に日本の料亭などで、ふすまの開け閉め、畳の踏み方、着座の仕方から始まって、先付、向付、八寸がどうのこうの、食材や調理法がどうのこうのと言っても、知っている人がほとんどいないのと同じだと考えればよい。もちろん、マナーやメニューの選び方が良くできていれば、しかもフランス語が話せればスマートに振る舞ってみたいものだ。しかし、小生にとってこれは憧れにしかならない。良い恰好をして流暢でもないフランス語で、アントレがどうだ、デグスタションがどうのと粋がって注文して、こんな筈ではなかったと後で悔いを残すことにもなりかねない。無理をして頑張ってみてもサービスをする人にはミエミエでおかしくもあろう。若いときは気取ったりして、かなり無理をしながら内容を理解できないメニューを見て、判ったつもりで注文していた。したがっていつも発音のできる同じ物を注文することが多くなり、今考えてみれば全くばかげていたと思うのである。
しかし、フランス料理店に出かける場合は、慣れ親しんでいますよと、いう態度をしたりして、気取った態度をしたとしても責めるべきではないと思っている。多少の気取りと心地良い緊張感の中で自己満足ができるならこれはこれでよいのだろう。よそ行きの食事こそがフランス料理である限り、これも楽しみのひとつなのかも知れない。高い出費をするわけだから。またフランス料理をおしゃれして食べに行くことは、楽しみを満たす、うれしい出来ごとなのだから。ただし、大声を出すとか、動作をけばけばしくすることを避け、穏やかに振る舞うことはきわめて大事なことである。それさえ心得ていれば何も気にすることはない、あとは堂々として穏やかな態度に終始すること、それで十分なのである。
<イタリアの食事>
イタリア料理をひとことでといわれても答えるのは難しい。それぞれの地方によって内容が大きく違うからだ。またフランス料理や北京料理のように、饗宴のために美食のみを追求する成り立ちと違うのだ。それは家庭料理をベースにしたいわゆるマンマ(おかあさん)の料理だということである。そして今ひとつは、イタリアはご存じのように南北に分かれていて北と南の気候風土にも大いなる隔たりがある。付け加えるならばそのような国土の成り立ちが生んだカンパリニズモ(愛郷主義ともいうべきか)によって都市国家に分断されていた当時の史実によって各地の習慣が非常に違ってくるからである。
イタリアには無数に方言がある。例えばイタリアでは州と州、県と県という以上に町や村の単位で方言が顕著に違っている。同じようにそれぞれの地方にそれぞれ異なった料理があると言われている。しかしそのことは風土の大きな違いをもつ国においては当然のことだ。どこの国に於いても、山岳地帯なのか海に面しているのかといった風土による違いは、それぞれのいわゆる郷土料理としての成り立ちに変化をもたらすことになる。また、それ故に、その国の料理を食べ歩くことの楽しさや喜びにつながるものと断定してよい。フランスにしてもスペインにしてもそれぞれの地方における料理の違いは際立っている。
現在、取引のあるイタリアの会社のうち一社はピエモンテ州にあり、ここでは地理的条件もあり、フランス料理に似た生クリームやバターを多く使った料理が多い。白トリフの料理には最高のワインとの取り合わせもあり、フランス料理に似て豪華である。もう一社の取引先、これはサルデーニャ島にあるが、この地では、魚料理が中心となる。味付けも塩とオリーブオイル、にんにくなどのシンプルなものである。この島の郷土料理として馬肉料理や子豚料理などもあるが、これらにしても味付けはシンプルである。このようにイタリアの北と南ではこれが同じ国かと思われるほどに調理法についてもバラエティに富んでいる。パスタ料理にしても、北の手打ちパスタに対し、南では乾麺を使うことが多い。
さて、イタリア料理については、最近では有名シェフたちによるとても良いイタリア料理に関する出版物が出回っているし、週刊誌、月刊誌でも頻繁に取り上げられているので、それらの本を読めば十分な知識が得られるため、料理についての詳しい説明はここでは省略することにしよう。「専門料理」、「料理王国」、「四季の味」を初め、「オレンジページ」「クロワッサン」「家庭画報」等々、ありとあらゆる月刊誌は料理記事で埋められている。
小生はイタリア料理が好きである。日本の料理と比べてもイタリア料理がおいしいとさえ思うことがある。この料理の特質は、フランス料理と対比させることによって、より一層、違いが現れてくる。元来、イタリア料理が長男だとすれば、フランス料理は次男、いや妹とした方がよいか。その起源をたどればこの二つの国の料理に関する関係は兄妹のようなものに思える。当然妹の方がおしゃれで、華やかに装っている、という風に考えればよいのである。
王族たちが美食を楽しむことによって発展したフランス料理は華やかで見るからにおいしそうで、その場の雰囲気もまた素晴らしいものである。フランスの項で述べたように、世界で一番手の込んだ、世界一おいしい料理であると認めることには異論がない。しかし、宴席料理というか接待料理というものは、少しく凝りすぎていて、毎日の食事として考えたときにはかなり問題を抱えていることは間違いない。人間の身体というものは、自然に美食を求めるものではあるが、それは舌などによる味覚のことであって、胃袋の方は、時には休養を欲している。また、血液は天然の食材から得られる素朴さを欲していることもあろう。そういうことを無意識下に判断して、今日は何を食べたい、食べるということになってくる。
小生はフランス料理が一番好きだと書いた。そして同時に、毎日は食べられない。精々1週間に1回ならばよいだろうと述べたそのことである。イタリア料理が西洋料理としては、最終的にフランス料理を超えて世界の料理の主流になるだろうと確信する理由がそこにある。
人間は毎日2度3度と、生き続ける限り食事をとり続ける。そのうちで、それぞれの国民としての国の料理が先ず食されることは当然だが、中華はこの際省略するとして、それ以外に食したい西洋料理というものがどんなものであるだろうか。仮に月に1回しか外食しないと考えれば、フランス料理かも知れない(西洋料理のみに限定)。週に1回としても考えられる。しかしながら、週に2回以上、あるいは毎日ということになれば、必ずやイタリア料理ということになろう。
天然の素材の持ち味をできるだけ残すオリーブオイルの軽さ、脂質の摂り方といった健康上の問題、バラエティに富んだ食材、そして気さくな雰囲気と値段の手頃さなど、まだ他にも理由は有ろうが、このようなことによって、イタリア料理はフランス料理に勝っている。食事が、自分自身にとり永遠に摂取しなければならない長期間にわたる営為であることを考えれば、イタリア料理は断然フランス料理以上に支持されるであろう。小生の経営する会社がイタリア料理をメインにした地中海の食材にこだわる理由がそこにある。
もちろん、フランス料理のような美食の極致を演出してくれる料理形式は絶対になくてはならないし、無くなるものではない。誰でも、晴れがましい服装をしたりして、気分転換をしたいときがあるに違いない。もちろん、お洒落に無頓着な人は別の形で気分転換するに違いない。接待やデートなどで、うんと奮発して贅沢を演出しなければならないときもあるだろう。こんな時にはフランス料理が向いている。最近ではビストロやブラッスリーなど、手軽に満足させられる場所も増えており、食べ歩きの楽しみにはこと欠かない。しかし健康上の問題もあり、美食を連日追求するわけにはいかない。毎日の馳走攻めは(竜宮攻めともいうらしい)、何の感激ももたらさないだろう。楽しみは時折あってこそよいのである。
牛肉を食する場合、欧米や豪州産の肉は脂肪分が少なく美味しくないといわれる。一方、日本の但馬牛や神戸牛、そして松阪牛などの美味しいといわれる牛肉は脂肪を大量に含んでいて、誰が食べても美味しいことは変わりなく、芸術的とも言えるほどである。しかし、毎日食べたらどうなるであろうか。間違いなく糖尿病や通風を誘発するに違いない。連日続いたら胃もたれがして、うんざりしてくるに違いない。美食には一定の期間をおいて、一定の量を深く味わうことによって、尚一層、その良さが伝わってくるように思われる。
小生は、最上の牛肉を食べさせてくれる松阪市の「和田金」に、およそ数年に1回のペースで行っている。ここでは、すき焼きやステーキ、しゃぶしゃぶなど、何を食べても美味しい。食べた後の肉の美味の余韻が3年でも4年でも舌先に残っている感じで、5年経ったとしても、その食事の始まりから最後までの光景が克明に意識下に残っている。そのくらい美味しい。こういうのを絶品というのだろう。10年ほど前に、伊勢参りの帰路に立ち寄った際には、店の建物が、ものすごく立派な鉄筋コンクリート5~6階建てになっていて驚いた。相変わらず、年季の入った仲居さんが七輪を持ってきてくれてつきっきりですき焼きを作ってくれた。「和田金」は名古屋の松坂屋本店の新館のみに限って支店を出していたようであるが、妻の誕生日にちょうど名古屋に滞在していたので、夜は高くつくので安くすませようと昼にでかけたが、良い肉が入手できず、無期限で休業とのことでがっかりしたことがある。いや内心では出費が抑えられたのでほっとしたのかも知れない。2001年に名古屋に出かけた際に聞いた話によると、不定期の休業が頻繁に続いたので(良い肉が提供できないとの理由で)「和田金」松坂屋名古屋本店は撤退したらしい。
この店に最初に訪れたのは約35年前である。二階建ての木造で、長い廊下を渡り、座敷の大広間にしつらえられた席に着いたが、驚いたことに、給仕するご婦人たちは、皆50歳以上という感じで、中には70歳以上に見える人も多くいてびっくりした。そして、わざわざ七輪と炭箱や炭火を持って長い廊下を行き来している光景には風情があった。何故このようなことを書くかといえば、例えば東京などのレストランに、しばしば若々しい女性を多数置いてサービスするやり方によって繁盛している店が多く見られるが、ヨーロッパなどで、良いといわれる店ほど、年季の入ったギャルソンによってサービスされることが多く、小生などは、単に若くてきれいな娘さんの給仕よりは、応対に熟練した人の給仕こそが良いと固く信じているので、そのことを言いたかったのである。
話がますます遠回りになって本題のイタリア料理から外れたが、美食過ぎず、胸がつかえるほどでないイタリア料理は日本人にとってはフランス料理よりも受け入れやすい。小生の予測によれば、今後とも、イタリア料理店は増え続けていくにちがいない。あと10年もすれば、現在の分布状況が更に全国に広がって、人口2万人前後の町にもきちんとテーブルクロスをセットしたリストランテが展開されるだろうと思っている。
イタリア料理は日本人にとって非常にわかりやすい。値段も手頃で雰囲気も気楽である。そして素朴な持ち味を活かした調理法と北イタリア料理を除いてバターや生クリームを多用しないオリーブオイル主体の調理法は自然の理にかなっているし、第一健康にとって良いのである。今後の国内市場における外食レストランは古くからあるラーメン屋、カレー屋、とんかつ屋、焼鳥屋、うどん屋、そば屋などの日本食を別にすれば最も大きい外食産業になると思っている。
理由はまだある。仮にフランス料理店で、独立して店を持とうとする場合は、まず、料理を覚えるまでの年限が5~10年では済まないこと、グラスやテーブル、そして店のデコレーションが安っぽいとフランス料理店としての風格が出てこないこと、したがって多額の初期投資が必要で、なかなか店を持つのが難しい。特に地方の場合は、今述べた理由により、地方のそれなりに一流のホテルクラスでなければフランス料理店を開店できないことになり、そこで働くシェフたちは、大手ホテルの待遇の中で、現場を飛び出してまで店を持とうとする意欲、独立心をそがれかねないという面がある。
これに対して、イタリア料理は、先ず調理法が素朴で、ソースなどにフランス料理ほど手をかけないために修業時代の年限が少なくて済むこと、テーブルクロス等はタータンチェックのビニール生地でもそれなりに通用すること、デコレーションはロココやロマネスク、アールデコでもなく、自由な発想で、安上がりであっても店の雰囲気を出せること。すなわち、出店のための初期投資が少なくて済むので独立がし易いのである。
もうひとつ追加すれば、美味しく食べたフランス料理を、一般家庭の主婦がまねしようとしてみても、自分で料理の再現ができない(ソースなどのプロセスが難しいため)が、イタリア料理の方は一般主婦にとっても調理の再現をし易いこと。これらのことが非常にイタリア料理発展に役立っていると考える。たとえば、主婦がどこかのイタリア料理店で食べた味が忘れられないとしよう。雑誌などのレシピを真似て家庭で作ってみる。作ったものが家人に美味しいと誉められる。今度は親しい友人を呼んで家でごちそうする。そしてまた誉められたりする。このようなプロセスを経て、今度は新しいメニューに挑戦する。そのためにまた、新しいイタリア料理店に行って、食を味わった後にそれを再現する。そのようにして次から次へと繰り返しが行われるようになって、レストランも繁盛し、主婦の腕前も上がってくる。このことがイタリア料理店のダイナミズムを支えているのである。
イタリア本国のイタリア料理店ではずいぶん若い日本人が修業にいそしんでいる。日本国内でももちろんのことである。それらのシェフの卵たちが自信をつけてヒナにかえるのにはそんなに時間はかからない。速い人は5年もあれば一人前のシェフになり得る。そしてその若い人達が独立したとすると当然自分の店だから必死になって客を呼び込み、また満足を与えようと工夫する。このようにして、今日、速いテンポでイタリアレストランが増えてきているのである。若い人は先輩に追いつこうとし、先輩は若い者に追いつかれないように、双方が互いに競い合っていく限り、前途は洋々と拓かれるであろう。
イタリア料理が当初日本に入って来たときは、直接日本に入らずアメリカを経由して入ってきたので、このことが後々まで真のイタリア料理に対する大きな誤解を与えてきた。
すなわち、第二次世界大戦の際、連合軍としてイタリアに渡った大勢の兵士たちが、スパゲッティやピザに親しみ、それを本国のアメリカに帰ってから流行させたのである。それが大衆化されて日本に入ってきた。その頃でもアメリカではイタリア移民も多いことから、イタリア料理は盛んであったようだが、本場の味というよりもアメリカ大衆の味に変遷したものが定着し、日本へも大衆性の高いものを中心にして入って来たのだ。スゲッティミートソースやマカロニ、ピザなどアメリカ風に簡易なものばかりであった。しかもトマトケチャップやタバスコをかけて食べるなど、本場では考えられないスタイルになったのである。アメリカ風イタリアン、これこそ40代以上の日本人が抱くイタリア料理のイメージであったが、この10年で、日本人のイタリア料理に対する意識も大きく変わってきている。
「イタリアの食」という書き出しで始めながら、料理や素材について詳しく触れずに終わってしまった。小生はイタリアンレストラン向けの食材輸入会社を経営している関係で、東京都内に限らず全国各地の有名レストランのシェフにも接する機会が多く、いろいろ教わることが多く、この業界のことについては一般の人より詳しいだろう立場にいる。それゆえにイタリア料理についての私見を申し述べることに対して、気軽にはなれない。また小生の経営する会社が取り扱う商品についての説明なども、宣伝にもなり兼ねないので、出来るだけ触れないようにした。
イタリア料理に関する沢山の本が気鋭のシェフたちによって出版されているので、料理やレシピに関してはそれらを参考にしていただきたい。イタリアンのシェフたちには現状の発展に甘んずることなく、いつまでも美味しいものを作り続けて欲しいと願うものである。
<スペイン・ポルトガルの食事>
スペインもまたとてつもない文化と風土の違いが内在されていて、ひとつにくくることは極めて難しい。大別すれば地中海沿岸、ビスケー湾、大西洋の海岸に面した地方の魚介を中心とした料理と、アラゴンやカスティーリャ、ガリシア、そしてラ・マンチャ地方などの内陸地方の肉類を中心とした料理になるだろう。加えて、スペインは農業国なので豆類を含む野菜についてもさまざまな調理法があって美味しいものが多い。
まず、海岸に面した地域に共通することは、小魚を含めて魚種が豊富で、どこに行ってもグリルやフライ、酢漬けなどが非常に美味しい。小生はセルベッサ(ビール)をのみながら、カラマレス(いか)やガンバス・ア・ラ・プランチャ(エビの鉄板焼き)を海の見える小さなレストランのテラスで食べることを無上の喜びにしている。レストランでコース料理も良いが、むしろバルでタパス(小皿料理)をつまみながら、あるいはテラスで魚介類のフリット等を注文してワインやビールで気軽に済ませる方が楽しいかも知れない。ビールのサンミゲルは日本人の口に合う。
まずスペインの中で評価される料理はガリシア料理であろう。「ガリシア風」のことは現地ではガジェゴともいうがその料理は魚介類を中心とした料理である。スペイン人の間にもガリシア地方の人々は料理が上手いという定評があり、家政婦(料理人)を雇うなら断然ガリシア人と言われているほどである。スペインの各都市にガリシア風バル、レストランがあるので、もし今日はどのレストランで食べようかと迷った場合にはガリシア風レストランを選べば、間違いなく美味しいものにありつけるはずである。イカやタコ、帆立貝、カニ、エビ、ムール貝などをさまざまな調理法でとても美味しく食べさせてくれる。なんと言っても日本人にとって魚介の料理ほど口に合うものはない。しかも種類が豊富で、鮮度が良くそして価格が驚くほど安いのだ。
アンダルシアやバレンシアの魚料理も美味しい。小生はソパ・デ・マリスコスという魚介のスープが大好きで、新鮮な魚介の味が良く出たスープは毎日でも飽きることはない。ソパ・デ・マリスコスはカタロニアからカディスまでの地中海沿岸のどこでも食べられるものだから、日本食が恋しいときは、これをすするとたちまち元気が出てくること請け合いである。
アンダルシアの暑い夏には冷たいガスパチョが最高だ。いつかゴルフをして汗を流した後に冷たいガスパチョとサンミゲルのビールを注文したら、これが結構いけた。暑くて食欲がないときにこれを食べると、さて次は何を食べようかと元気が出てくるスープである。
バレンシア地方から広まったパエリャは日本人の大好物であるが、スペインを代表する料理というわけではなく、バレンシア地方を除いて、どこのレストランに行っても食べられるというわけではない。ただし、観光地では、旅行者用にパエリャをメニューに載せるレストランも多いので、特に日本人がよく行く有名観光地ではパエリャを食べることができる。レストランではパエリャはプリメル・プラト(第一の皿)として、スープやサラダ、パスタ類と同じように選ばれるが、その場合は例えば、アサリ入り、生ハム入り、豆などの野菜入りといったように、ほとんど単品だけ入ったパエリャである。パエリャバレンシアーナになると、野菜、肉、かたつむり、魚介などさまざまな材料が入って、メインの料理として注文される。イカ墨のパエリャもアイオリソースが添えられて独特の美味しさがある一品である。
肉料理となると、これは本場だ。アラゴンやカスティーリャ地方の内陸に特に肉料理が多く、中でも内臓肉の煮込み料理は特筆すべきものもある。胃袋の煮込みトリッパやカリョス(豆類と内臓肉の煮込み)は小生の大好物で冬の寒いときには体が温まる。腎臓(リニョーネス)の料理もスペインで食べると最高に美味しい。しかし、店によっては、日本人にはとても脂っこく塩味も濃いものがあったりして、店選びが大切かと思われる。スペインの各種のソーセージ、生ハムの美味しさは言わずもがなである。
スペイン料理はイタリアやプロヴァンス地方の料理と違い、ハーブ類や香辛料はほとんど使っていない。そのかわり、にんにく(アホ)とオリーブオイルをふんだんに使うのがスペイン料理に共通する調理法である。
カタロニア地方について触れるならばハツタケ茸をはずすわけにはいかない。この地方は松の疎林が何処に行っても見られるが、その根元に自生するハツタケはこの地方の人々に好まれ、バター焼きにして食される。欧州の人々が春になると待ち焦がれるホワイトアスパラガスと同じように、カタロニアでは秋になると首を長くしてハツタケの収穫を楽しみに待つ。ハツタケは我が日本でも全国的に採取される茸と思うのだが、あまり市場で見かけることがないのは残念である。あれほどに味がよくダシの出る茸は他にないと思うが、保存が難しく、しかも収穫時季が短いことや人工栽培に馴染まないこともあって、商品化しにくいのだろうか。小生の生まれ育った青森ではことの他このキノコを珍重している。塩バター焼きもそうだが味噌汁仕立てにするハツタケ汁は最高だと思う。小学生の頃からキノコ採りに出かけてはハツタケを見つけて歓声をあげたものである。これに比べればシメジもイグチも雑キノコというべきで喜びは少なかった。このキノコを輸入したいと思っているが、用途としては西洋料理や料亭料理より日本食とりわけ郷土料理や家庭料理向きであろう。
先にも述べたが、スペインではレストランであらたまって食べなくても、いろいろなスタイルのカジュアルな食べ物屋がある。バルのカウンターでタパスをつまむのも良い。[タパス=小皿料理のおつまみのこと。サン・セバスチャンなどのバスク地方では、おつまみに楊枝を刺してサーブすることからピンチョスと呼ばれる]また、メソンと呼ばれる居酒屋でワインとつまみを楽しみながら、ツナといわれる大学生たちのバンドの音楽(ギターやスペイン民族音楽)を聴くのも良い。ツナは大学の学生のクラブ活動で、学資を稼ぐためのアルバイトであり、メキシコのマリアッチの本家と言えるものである。
スペインの代表的な惣菜にトルティーリャがあり、これは分厚いオムレツの中にジャガイモや、ハム、パプリカ、マッシュルームなどを入れたものである。スペイン風オムレツというとジャガイモの入ったものをさし、これもやはりバルの定番メニューになっている。スペイン人はこれをパンにはさんで食べる。子供たちの遠足に出会ったことがあるが、たいていの子供がパンにトルティーリャかハムをはさんだものを持っていた。たぶん日本人にとってのおむすびのようなものなのだろう。
アングィラ(うなぎの稚魚)をニンニクとオリーブオイルで煮たものは美味である。ボケロン(かたくちいわし)の酢漬けまたはフリッタはスペインのバルの定番タパスでどの地方に行っても間違いなく食べられる。チャンケッテというイワシの稚魚のフライは、アンダルシア独特のもので、熱々のチャンケッテを手で口に放り込みながら食べるのも愉しい。また、イタリアのパスタにイカ墨をからめたものがあるが、スペインではイカの墨煮はボイルした米と一緒に出てくる。イカ墨の甘さが何ともいえずに美味しい一品である。ただし、墨煮を食べた後にはお歯黒になるので注意が必要であるが。
ゲテモノと言うべきでないと思うが、魚介類の中で見た目にグロテスクだが特筆すべきものがある。ペルセベスとヴィオレッタである。ペルセベスは指の先に爪がついたような形の貝で、鮮度の高いものにレモンをきゅっと搾って生のままで食べる。プロヴァンスからスペインにかけて日本のホヤを凝縮したような形のヴィオレッタというものがあるが、これは日本のホヤ以上に美味しい。小生は青森出身なのでホヤをよく食べるが、磯の香りが高くクセが無いヨーロッパのヴィオレッタには感激した。
~ 閑話休題 ~
世界で一番美味しい生ハムは・・・・・ハモンハブーコかクラッテロか
生ハムはやはりスペインのものが最高だろう。日本では最近になってイタリアから生ハムが輸入され始め良く知られるようになったが、スペインの生ハムについてはまだあまり知られていないようである。
スペインのハモンイベリコとかハモンベジョータといわれる生ハムは格別に美味しい。メロンをくるんで食べるのだが、一度食べればやみつきになる。話は変るがイタリアにはプロシュートと並んで、最高に美味しいクラテッロという生ハムがあるが、どちらも最高に優れた生ハムなので少し比較をしてみたい。イタリアのクラテッロはごく限られた地域内(パルマ近郊)パダナ平野の伏流水によって吹く冷たい風を利用して半地下の石室で自然乾燥と熟成をさせて作る。このクラッテロとハモンハブーコを比べてどちらが美味しいのかという議論になったことがある。甲乙つけるのは難しいということにしておきたいのだが、どうみてもハモンハブーコの方に軍配が上がりそうだ。しかしながら料理との相性やワインとの相性によってはクラテッロの方が美味しいと思うことがあり、持ち味の良さを考えればどちらも生ハムの王様と言えるだろう。
以前ミラノから150キロほど南の町でバイオリンのストラディバリを生産したことで世界的に有名なバイオリンの町クレモナの町に何度か出かけたことがある。この町と生ハムで有名なパルマの町そしてイタリアルネッサンスの頃に一世を風靡した女傑のエザベッラ・デステが君臨したマントバに近い小さい町ピアデナの二等辺三角形を結ぶ地域がクロテッロを生産する地域だ。しかもポ-川の伏流水の風が吹き上がる場所に限定される。以前に日本における販売代理店をしていた関係でパスタノザリ社のマルコ・ガンボー二社長に案内されて何度か会食の途中にその生産現場を訪れたことがある。クラテッロはアルプスの雪解け水が地下にしみこんで伏流水となり地上に再び流れ出すような地域で生産されている。すなわちその冷たい地下水の表層部を大きな川石で整地してその上に目の細い砂利を敷き詰め、地下の冷たい空気が地上の温度差に反応して冷気が吹き込むのをうまく利用した天然の冷蔵庫のような場所をつくり、そこに長期間つるして熟成させるのである。
スペインのハモンハブーコについては義甥の石谷樹人氏とスペインのマラガからポルトガルのリスボンにドライブの途中、二人の意見が一致してどうしてもハブーコ村まで行ってハモンハブーコを土産にしようということになった。セビーリャの町から車で疾走して2時間で吉野熊野を思わせる深い山中に入り込むと、小さな部落があり、そこがハブーコ村であった。村のほとんどが生ハム作りに関係していることが一目瞭然としていた。工場で、生産現場を視察したいと掛け合ったのだが突然の訪問だったためアポイントがなく受け付けて貰えなかったは残念だった。ハモンハブーコの工場訪問のツアーなどもあって、全国からバスを仕立てて生ハムを食べに訪れている様子だった。
上質のハモンハブーコは肉に触るだけでなんともいえぬ香りがしてしばらく皮膚にその香りを残す。それがまたたまらなく味覚を刺激してやまないのである。放し飼いで肥育した豚にドングリを食べさせるのだが、それがあの香りをつくるのだろう。ハブーコ村の周辺はすべてドングリ山である。そしてそのドングリの樹はすべて50年から100年以上の大木なのだが、地上2メートルくらいの高さで無残に切られていて、そこから小枝が無数に出ている。林相としては異様な感じを与えているが、樹木を矮化してドングリを採取し易くしているのだろう。スペインといっても海抜1000メートル前後のハブーコ村の冬は身を切るように寒くて強風が吹く土地柄と聞いている。ドングリと冷たい冬の風がハモンンハブーコにとって必須のものであるらしい。
ハモンハブーコの高いものは現地でもKg当たり2万円以上するもので、並みの生ハムではない。豚にドングリを食べさせて肥育するので同じスペイン産でも単なるハモンセラーノとは銘柄で区別してある。ドングリで肥育した豚の生ハムのことをハモンベジョータといい、その中でもハブーコ村で作られたもののみがハモンハブーコよばれ珍重されている。大いなる山間の僻村に過ぎないハブーコ村の製品がパリのシャンゼリゼ-近くに店を持っているとのことで驚いた。これに対してハモンイベリコという呼び名は黒豚から作る生ハムを総称しているらしい。
小生の古くからの友人で井利さんというマラガ近くのマルベージャに15年ほど在住している女性がいる。井利さんは前に述べた三重県の藤田謹司氏夫妻とも共通の友人なのであるが、彼女の紹介によりコスタ・デル・ソル周辺の美味しい店の食べ歩きもしている。この方はまれに見る才色兼備の女性である。素晴らしくきれいなスペイン語を流暢に操ることで定評のある女性で、今まで日本からの政府高官がアンダルシア地方、特にコスタ・デル・ソル方面を訪問したときは、現地の事情に精通していることから、何度となくガイド兼通訳として立ち会っている。その外交官たちは例外なく、日本への土産としてハブーコ村の、いわゆるハモンハブーコ(ベジョータ)を外交行嚢の中に入れて持ち帰るということを聞いた。最近ではこのハモンハブーコもスペイン国内だけでなく広く海外に向けて輸出されるようになっているが、現地の人たちは、そうなればドイツや日本など金持ち国に良い品がどんどん流れて、美味しいものが自分たちの手に入らないのではないかと心配しているとのことである。
井利さんのご主人は、グラナダ近くのハエンという古くからの町で病院を親子三代にわたって開業している名門の御曹司であるが、やはり彼もグルメである。マルベージャやアリカンテなどで、彼のすすめでこのハモンハブーコの最高級のものや、アングィーラス(うなぎの稚魚)などもいただいたが、やはり現地の人はおいしい穴場を良く知っていて十分に満足させられた。ついでながら言うと、現在日本に入っているイタリア産オリーブオイルの高級品とされている銘柄(香水の形をしたビン)は、彼の実家が経営する農場からイタリアへ樽詰めで送られたものを現地で瓶詰めにしているそうで、彼が日本へ新婚旅行にきたときに、この商品をいち早く見つけて喜んでいた。イタリア産オリーブオイルの中には、スペイン産のものをイタリアでボトリングした高級品も結構あるようだ。
話が飛ぶがこの項はスペインの食に関する部分なのでスペインの料理界についても触れないわけには行くまい。
2001年現在、料理の世界でもっとも話題になっているシェフはフランス料理のアラン・デュカスではなく勿論イタリア料理のかつての巨匠マルケージでもない。現在最も注目を浴びているのは今までの常識を打ち破ったフェラン・アドリアであるらしい。彼は、今まで無名に近かった辺ぴな場所にエル・ブリィ(エルブジ)という前衛的な盛り付けをするレストランを開店し、たかだかこの10年くらいの間に、世界のグルメたちを魅了する料理を作り続けているとのことである。
店を開いたその場所は景色こそ申し分ないとしても、非常に交通事情が悪く、カダケスあるいはロサという避暑地から砂利道のような田舎道を通って行く。小生自身カダケスまでは過去に3度ばかり車で行っており、そのときはヒローナからとフィゲ―ラスからのメインルートを取り、曲がりくねった砂利道の坂道を峠の2つか3つ山越えしたのである。そのようなことでそのカダケスから4~5キロ奥に入ったところにエル・ブリィがあると聞いていささか驚いたのである。その近くまで出かけていながらそんな店があるとも知らなかったのが悔やまれてならない。しかし小生が訪れたのは10~15年前の話なのでその当時としては今のように話題を集める店では無かったに違いない。
カダケスに3度も足を運んだのは、そこがかの大天才サルバドーリ・ダリの奥さんの生地だったことと地中海クラブ発祥の土地だったからであるが、フランス南端の国境ペルピニャンからスペイン領に入って程近いコスタ・ブラバに面した俗界を忘れさせてくれる別天地である。芸術家の集まる海辺リゾートとしても知られた土地である。
そのエル・ブリィの料理がサン・セバスチャンの名門レストラン、アルサックを始めとするスペイン各地の料理に大きな影響を与え始めている。料理の味付けや盛り付けはフランス料理のもつエレガンスとスペインのタパス料理を上手にアレンジしたもので、それに加え、カタラン(カタロニア人)の独壇場である奇抜な独創性をいかんなく発揮したもののように思われる。何と言ってもここカタロニアは、バルセロナの近くタラゴナにサクラダ・ファミリアで知られるガウディが、フィゲーラスにはサルバドール・ダリが生まれ、また、バルセロナを中心としてホアン・ミロやパブロ・ピカソが学び活躍した土地柄である。エル・ブリィのフェラン・アドリアもカタランとしての道を開拓しているのであろうか。
さて、次はポルトガル料理である。ポルトガルの料理はスペイン料理よりも食味がやさしい穏やかなもので肉料理などは日本人の口に良く合うものと思う。全般的にはフランス料理に似た味付けだ。これは調理にオリーブオイルとバターを混ぜて使用し、全般的にマイルドな味付けをしているからかもしれない。
海岸地方で食べるいわしとあじの塩焼きは新鮮な魚にただ塩をして焼いただけのものである。ナザレの町では昼時、夕食時になると、主婦たちがいっせいに路地に七輪を持ち出し、火を熾して魚を焼く光景が見られる。庶民的な味であり日本人の我々にとっても馴染み易く郷愁を誘う味である。レストランではたいていゆでたジャガイモと一緒に出てくる。その他の魚類も豊富である。川ますの料理も好まれている。
<バカラオ(干しダラ)・・・bacalao, bacalhau, baccala, morue>
スペインとポルトガルで忘れてはいけないのはバカラオ(バカリャオ)というノルウェーやアイスランドで獲れた大型のタラを塩漬けにして数週間天日で干した、いわば干しダラの料理である。調理する際には塩抜きが必要で、24時間以上水で戻して使う。トマトやジャガイモと一緒に煮込んだり、フライにしたり、コロッケやパイに入れたりするこの干しダラ料理は本当に美味しい。イタリアではバッカラと呼ばれている。今では200海里規制の問題があり、タラの漁獲は出来ないためそのほとんどをアイスランドやノルウェーなどから輸入しているようだ。
カトリック教徒の人たちは金曜日には肉を食べない習慣があり、その日は魚料理が食卓に上ることになる。中でも特にタラ料理は特別のご馳走とされている。イースターやクリスマスの食卓にもタラ料理が並ぶことが多い。タラは、塩をして天日で干すことによって、全く異なる味わい深いものに変質する。スペイン、ポルトガル、イタリアなどの国は特に日差しが強く湿気がないので、このバカラオの乾燥生産地としては適地なのである。もちろんスカンジナビアの本場では岩礁の上で白夜の中、寒風干しで生産されている。
このバカラオがヨーロッパ社会に貢献した役割は大きい。中世以前からノルマン人(スカンジナビア人と考えてよい)の進出(いわゆるヴァイキングも含むが)によってフランスのノルマンディー地方は彼らの基地となった。彼らがバスク地方のサン・セバスチャンなどを侵略征圧した頃には、このバカラオ(当時はストッカフィッソと呼ばれる乾燥しただけのものを作っていた)の通商路を求めて今のフランス国境を越えてドイツ南部まで進出したとのことで、ヨーロッパに与えた通商圏拡大の効果はとても大きなものがあったらしい。ヨーロッパ内陸に住む人たちは好んでこの保存食に工夫を加え、メニューを開発していったものと思われる。
<中国を始めとするアジアの食>
和食を別にすれば、日本人が生まれてから最も食べる機会が多いのが、ラーメン(支那そば)から始まって餃子や野菜炒めなど中国料理にその起源をもつ料理だろう。
中国料理ほど世界中に展開されているものはない。東南アジア全域はもちろん、アメリカ大陸にも大きい市場を持ち、ヨーロッパ全域にわたっても然りである。もっとわかりやすく言えば、サハラ砂漠の真中にあっても中華料理店があるのではと思われるほどだ。しかもほとんどの店は地元に完全に溶け込んでいて中国人というもののダイナミズムに驚かざるを得ない。エスキモーやサハラ砂漠のような地の果てとも言われる土地を含めてさまざまに旅をしてきたが、本当に信じられないくらいに中国料理店は普及している。サハラ砂漠の真中にも、もしそこにオアシスがあるなら、かならずや中華レストランがあるであろう。おなじことを何度も繰り返しているが、その位すごい浸透力である。
さらに、中国料理店と日本料理店で働く人たちを比べたときには大きな違いがあることに気づく。海外における日本レストランは大抵日本人観光客の多い場所や日本人ビジネスマンが立ち寄る場所に限られていて、長い間その地で店を持ったり働いたりしていても、日本人社会に交際を求めるだけで、その国の文化に溶け込むこともなく、言葉を覚えないケースが多い。
その点、中国料理の人たちは完全にその土地に根付いていて、同郷の仲間がその店の関係者以外誰もいないような土地であっても、営々と努力を重ねて、言葉でも生活習慣でも完全同化しているように思える。そういう環境にありながらも、中国人らしさというか中国人のアイデンティティーを失っていない。このことに関して言うなら日本人は中国人に完全に後れをとっていると言えよう。
中国人は地上にあっては食卓以外の4つ足、空にあっては、飛行機以外の空を飛ぶものは何でも食べると言われているのも、この民族の食に対する貪欲さと言うか美食に対する執念をあらわしているに他ならない。東南アジアではほとんどの国で中国料理が主流となっているし、タイやベトナムでは一見、その料理は違うようにあるが、おおむね中国料理の影響を受けている。
<インドの食事>
インドを最初に訪れたとき、この国の熱気と湿度によってもたらされる食材のにおい、特にご飯の蒸れる臭気を感じて、とても食べる気が起こらなかった。ニューデリーのアショカとかインペリアル、カルカッタのグレートイースタンなど、この国の最高級ホテルとて例外でなく、そのむれるような臭気からは逃れることはできなかった。
インドのカレーには何種類ものタイプがあって、日本のインスタントカレールーで作るような黄金色のどろりとしたカレーは見かけられず、さらりとした色の黒いスパイシーなカレーが本場のカレーなのである。舌の先が麻痺するくらいのインドカレーはやむなくこれを食べつづけるうちに、その辛さにとりつかれ激辛大好き人間になって、今の小生は中華でもタイ料理でも、メキシカンでも激辛でなければ物足りなくなっている。
我々日本人にとっての食卓の喜びとは、味の良さは当然ながら、食事が清潔であることはとてもたいせつな要素である。この点を考えると、インドではグラスを含めて食器全般の清潔度は全く想像を絶するものがあり、できるだけこれを避けたい気分になる。インドでの食事は、こういった意味であまりおすすめできるものではない。
グラスなども傷ついて透明度を失っている。コーラのビンにしてもその通りである。小生は別にヒッピーのような旅行の話をしているのではない、何度か訪れてこの国を代表するホテルなどに滞在した記憶を書いているのである。水分などは意識して果物から摂取するようにした。高温多湿であるがために不潔感が拍車をかけているのであろう、そのようなことで人手のかかったものに不潔感を覚えたのである。それでも目の前で焼かれたパン(ナン)などは安心して食べられる。
<日本の料理>
当然ながら我々日本人にとって日本食は最も日常的なものである。いろいろ理屈を並べたとて日本人にとっては日本食が一番美味であると言うことに異議を唱える人はいないだろう。
料理が洗練されていて味覚に優れたものは、少々高くつくかもしれないが、京料理だろう。高台院から花見小路にかけては、世界に冠たる最上質の食事が京料理を愛する人々によって脈々と生き長らえている。これが無くなったら日本の良さも半減して寂しくなることは必定である。
京料理の良さは味だけではない。フランス料理のように複雑なプロセスによるソースなどの味ではなく、自然と調和する素材の生かし方、そして目に映る芸術性の高い盛り付けによっても決まるのである。さらには、料理店の門をくぐるときから始まって見送ってもらうまでのサービスの、古くからの伝統的客あしらいなど、すべてが渾然一体となって、料理が味覚だけではないことを主張しているようにも思われる。
外食というものは、そこの店の入口を通ったときから五感で味わうべき料理がすでに始まっているといっても過言ではない。もちろん料理を食べに行くのである。味が悪ければお話にならないが、逆に言えば、接遇や設備に不備があったとしても美味しければよいと言えなくはない。しかしながら、料理の味という絶対条件と、良い雰囲気という必要条件の双方を満たしたときにその食事は最高のものとなる。
雰囲気も良く料理の味も申し分ないのに勘定が高いという不満が残るときがあり、これで全ての気分が損なわれるときだってある。この点に関しては、料理の味と受けたサービスそして支払った料金の釣り合いがとれているかどうかが大切になる。第一にどこで何を食べるかという前には、誰でも財布の中身を考え、それに見合った場所を選ぶことになる。選んだ店がこれらのすべての要素を満足させてくれたときは、うれしくなるのは当然である。
わが国最高の美食が京料理であるということに異論はあるまい。ただし、行きつけの店があるならまだしも、きまぐれのいちげん一見さんで出入りするにはかなりの覚悟を決めておかないといけない。そうでないと、支払いの時になってもめることがありそうで気が引けることは事実だ。どの店に入ろうかと迷うときには、誰かに予算を言って紹介して貰うようにすればあまり間違いがないだろう。名の知れた有名店は高いだろうと考えて、二流と思って入ったところが信じられないような請求をされることだってあり得る。無理に格好を付けないで予算を言って賄ってもらうことが良いように思われる。
料理法に関して言えば、新鮮な食材が得られる産地では、例えば北海道や九州の新鮮な魚など、鮮度が良いという、それだけでも申し分ないということになる。しかし果たして料理としてはどうなのか。鮮度の良い魚介を刺身にして食べる、天ぷらにする、焼き魚にするなどさまざまな形の食べ方がある。しかし新鮮で活きが良いから刺身が美味しいだけで、本当に料理と呼べるかどうか。いずれにしても鮮度の良い魚類ほど美味しいものはないが、料理方法としてみれば包丁捌きに熟練が要求されるものの、それだけでは本当の料理ではないだろう。
たとえば大分県の臼杵市の豊後水道で獲れる関アジ、関サバ、やはり大分県の日出町の城下カレイなど刺し身として地元で食べれば、日本中探してもこれ以上の美味なるものは無いと言えるほどだが、満腹状態まで食べればしばらくは刺し身を食べたくなくなるということになる。これは鮮度のみで食べることの限界を示している。
すなわち、京風料理のように、鮮度のみに頼らず、むしろ鮮度の落ちたものをどのように食卓に出すかという工夫によってもたらされた料理の中にこそ、真の料理の誇るべき本質があるように思える。
むしろ、料理というものは、鮮度の落ちたものや、はじめから鮮度の保持が難しいようなものを、それこそ様々な方法で、鮮度の良いものよりも美味しいものに仕立て上げることである。塩漬けにしたり、塩を戻したり、和え物にしたり、干し物にしたりと、素材から新たな旨みを引き出すのである、火の使い方は大切である。そのようにして手を加えられた料理法こそが料理の神髄と言えるもので、この点で京都料理が最高というのは、われわれ日本人の大半がこれを認めているように思う。
海から遠く料理に工夫が必要とされる土地であった京都の地から、鮒ずしや棒鱈料理とかの保存食料理や、鯛の蕪蒸しのような炊き合わせなど、多種多様なメニューが開発された。煮物や汁物にしても、見た目ばかりでなく、感激するような味覚が隠されており、日本人で良かったと思わせるに十分である。
小生の兄事する宇治オート社長の古後氏は、京料理の愛好家で、しばしば京会席料理を楽しんでおり、おかげさまで小生もお相伴にあずかることも再三で、いつも申し訳ないと思いつつ、楽しみにしている次第だ。
京料理というものはさすがに、御所のある京都にこそ発展したもので、この点ではフランス料理や北京の宮廷料理と同じで、究極の美食を求めて洗練され続けてきたことに間違いない。接遇の仕方、食器などに至るまで、似かよっているように感じられる。しかしフランス料理と違って毎日でも食べられるところは全くちがうのである。彼我の生理的違いはもちろんあるとしてもそこに京料理の真髄が隠されているのではないだろうか。
その他の地方で生まれた料理は、地物を中心に、その素材の個性を生かしながら、主として、そこに生まれて、働き、生活する人達の中で育まれてきた、いわゆる郷土料理である。そして鮭が大海に育ったあと、放流された河川のにおいを求めて回帰するのに似て、人間もまた、郷土料理というか、おふくろの味とも言うべき食生活から離れられないのである。小生の美食についての記述は、このように最終的には我が家庭料理を嚆矢とすることによって完結する。
~ 閑話休題 豊かな国日本 ~
日本は海や山の自然に恵まれ、四季があり、他の国の人たちにとっては考えられないほどの自然の美しさを持つ羨ましい国に違いない。この国に生まれ、外国を知らずに過ごせば、そのことを当然と思って感謝することなど思い浮かばないかもしれないが、これはとんでもないことだ。これ以上豊かな自然に恵まれた国などありはしない。しかも精神文化も繊細極まりない上等のものである。他国の人は経済大国であることよりも、日本の自然の豊かさと精神文化の繊細さに憧れを持つのではないかと推量する。
日本の豊かな四季によってもはぐくまれてきた日本の奥ゆかしい精神文化、こまやかな心遣いといった日本の伝統も、日本人が日本人らしさを持っていた戦前までに生まれた人の努力や生き様に負うことが大きい。小生の年代より後の、いわゆる昭和20年以降の団塊の世代の子供たち、すなわち団塊ジュニアの生態を見る限りにおいては、悲しくも日本固有の良き習慣などが退嬰化しているように思われる。アメリカのファストフードがもたらした食生活やライフスタイルの軽便化によって、若者の気品や奥行きが失われたように感ぜられて憂慮を禁じえない。
ハンバーガー、フライドチキン、カップラーメンといったたぐいのものばかりを毎日食べつづけていたらどうなるだろうか?その結果、まな板のない新婚家庭があったり、米を洗剤で洗ったり、イワシをサバと間違えたり、そんなことは全く恥とも思わない若者が増えたのである。そのような子供たちを育てた責任が我々親の世代である。申し訳ないことだ。このように書けば老人の繰り言といわれるかもしれないが、反発を嫌ってあまり優しく育てすぎた結果何かがおかしくなっていると思えば書かずにはいられない。本音ばかりでは世の中はギスギスしたものになって良くはないが、見過ごせないほどに限界を超えていると思えば、超えてあえて言うのである。
~ 閑話休題 吉兆御主人 湯木貞一氏の印象 ~
吉兆のご主人湯木貞一氏にお会いしたことがある。客としてではなく商品の紹介に関してであった。湯木氏がお亡くなりなる2~3年前のことで、ホテル西洋銀座の階下にある吉兆でお会いした。このときは現在、東京における吉兆の総料理長加藤氏に引き合わせていただいたのであるが、さすがに名実ともに日本を代表する京料理の総師としての風格がそこはかとなく感じられた。言うなれば戦後から平成にかけての北大路魯山人といっても、言い過ぎにはならないだろう、そのようなお方である。
さすがに小生も背筋をまっすぐにしてお話を頂いたのである。やせすぎず、痩身の氏の眼光は射るようなことはなく、話しぶりもとても穏やかであったが、どこか気品と控えめな威厳というかそんな雰囲気があって、印象深い方であった。
その時小生は、地中海のサルデーニャからカラスミを輸入して間もない頃で、ある人の紹介によって加藤総料理長に引き合わせを受け、その加藤料理長から、吉兆の主人が東京に来るので時間を合わせ来てくれと指定されて伺ったのであるが、氏は地中海産のカラスミの香りなどをかいだあと、やおら包丁を入れて味見をしたのだが、やはり3000年の歴史のある本物は違う、と味についてお誉めをいただいたのである。
カラスミが日本に入ってきたのはポルトガルの宣教師によっておよそ400年前から(信長の時代)であるが、地中海地方ではおよそ3000年前から作られていた歴史があり、向こうが本場なのである。小生は自分自身の舌を信じて国産品より味、香りともに優れていると自信を持って最初に輸入を始めた業者である。これによって、日本への本格的なカラスミの輸入の道が開かれたので、湯木氏にも加藤氏にも感謝している。