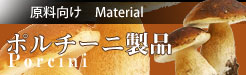5. イスラムとビザンチンの地中海を巡って
<永遠の憂愁、遊牧の民ベドウィン族>
世界中にはベドウィン族以外にも遊牧の民があるだろうと思われるが、ベドウィン族ほど気位の高い人種はいないのではないだろうか。シリア砂漠から南下してアラビア半島そして北アフリカ一帯に及ぶ地域に、ベドウィン族は広く分布している。
地中海の北岸諸国に多く見られるロマ(ジプシー)は国籍も国境の意識もなく、あちこちと流浪しているが、対するベドウィンもまた、国境を持っていない。ベドウィン族の生活する砂漠地域においては、国境を越えて遊牧する彼らに対し、国境を云々することなく制約していないという話を聞いた。古来よりわずかばかりの草を求めて、アラビア半島や北アフリカ一帯を移動し続けてきたその生活のあり方は、王朝などの都がある一部の地域を除けば、この地域全体に共通する祖先からの生活様式であったに違いない。それ故に、誰も国境を無視して生活する彼らをとがめたりしないのだ。
半砂漠というか土漠というか、まばらに草が生えた地域を遊牧する彼らは、定住して農耕する人々に対して、軽蔑の念を持っている。気ままに何の制約もなく、この乾いた大地を、羊を引き連れて、天の星を友にしながら生活する、そういう生き方こそ彼らの性分に合っている。誇り高い勇者は、限られた狭い場所に押し込められるような生活は耐え難いのだろう。それでも交易のため、遊牧の成果を定期的に近くのメディナ(バザール)に持って行っては、塩や茶などと交換しているらしい。
車でシリアの砂漠やモロッコの国内をドライブして幹線をはずれると、これらベドウィン族のテントが点在している。
未だ20才代後半の頃、これらベドウィン族のテントをモロッコ人のガイドと共に訪ね、一夜の宿を借りたことがある。現代の我々が生活の利便に使用しているものは何ひとつとしてない簡素な生活であった。会話はアラビア語を話す通訳がいたので成立したが、話題は限られていた。どこを通って、どのような生活をしているのかについて話を聞いた。彼らの口からは定住する人達への蔑視の言葉を聞かされた。彼らは極めて寡黙であり、毅然としていて恰も哲学者や修行僧を思わせる威厳と気品があるという印象を受けた。視線を遠くに据えて、世俗的なこととか文明の利器などに関しても、あまり興味を示すでもなく、みすぼらしいほどの家財に囲まれながら生活している。
唯一文明の利器といえば、アルミのボウルや鍋などで、これで羊を主にした肉や乳製品などの少ない食材を調理し、生活している。
テントに入ると、まずミントティーで歓待してくれた。家畜の糞を乾燥させた燃料にその辺で集めたと思われる小枝などをくべて湯を沸かすのである。 夜には羊肉を炙って、ケバブのようにしたものを、小麦粉を焼いて塩をまぶしたパンとともに出してくれた。種族の習慣なのかと思うが、人気のない土漠のど真ん中で出会った縁を大事にしてくれる人達であった。日が暮れるにつれて、最初に訪問したときと違い、いつの間にか、娘や息子と思われる人達が増えて、子供を加えれば十人近い世帯だったことが知れた。
夜、小用を足すために外に出て天空を眺めたら、漆黒の天空に星が大きく瞬いて、感動また感動であった。乾燥地、特に砂漠地帯では、星の光が強烈なことは説明の必要もないが、この感動は体験しなければわからないだろう。
天文学が古来アラビアで発達した理由も当然納得された。これほどの神秘と感動があれば、大作家による壮大な物語や名曲の数々とて対抗できず、ましてや、日々変化する物質文明の移ろいなどに関係なく、人の温もりと天球の神秘を感ずるのみでも生きていける理由がよくわかった。
今の日本では物が有り余り、人の心や物を大事にする気持ちを失いがちになっている。わがまま一杯に育ちすぎて生きる目標を見失った少年たちが増え、殺人など凶悪事件が激増している。翻って、ベドウィン族などの生活を見ると、厳粛に人生とは何か、について考えさせられる。
ベドウィンのテントには、この他にもう一度10年近く前に訪れた。シリアのダマスカスからシリア砂漠を250キロメートルほどドライブすれば、2000年ほど以前にシルクロードの要衝として繁栄を極めたパルミュラという巨大な都市の遺跡がある。ここに行く途中、遠くにぽつんと見えるベドウィンのテントを見つけ、道路から外れて土漠にホコリを立てながら訪問した。浩司君という若者とシリアを縦断したときのことだ。
その時はクリスマスの頃日本を出たので、餅やあんこ、それにカップラーメンなどアラブの片田舎では食する物が不自由だろうと考え、車のトランクにたっぷり食糧を詰めて行った。それを持ち込んで訪問したのだが、アラビア語は皆目見当がつかず、モロッコの時と勝手が違い、意志疎通が全くできないのは当然であった。それでも写真を撮ったりして友情を温めることになり、その後、持ち込んだ餅を焼いてあんこをつけて食べたり、カップラーメンにお湯を注いで食べてもらったら、彼らもずいぶん喜んだようであった。
モロッコとシリアは、地中海の両端に位置するが(約4000キロメートル位離れている)、ベドウィンのテント生活様式は30年近く前にモロッコを訪れたときと、全く変わることのないものであった。
小生は生来、好奇心が旺盛なのか、それまでの間にニューヨークのハーレムやブロンクス、そしてナポリの暗黒街とも言えるスパッカナポリなどを、深夜に一人歩きしたこともあり、インドのカルカッタでは路上で生活する人達の中に経験を求めて身を横たえたことがあって、少しばかりのことでは驚きはしない。 しかしながら本当のことを言えば、ベドウィンのテントの内で全く言葉が通じないことあって、万が一襲われでもしたらという思いがよぎって、薄気味悪いと思ったことも真実である。
数時間過ごした後に別れの時がきて、礼を言って、日本からの絵はがきなどの土産を渡したのであるが、今までの心配事は杞憂に過ぎなかったことを知らされた。言葉が通じなくても歓待してくれる心はわかるし、別れの際にはその人影が見えなくなるほどになっても、手を振って別れを惜しんでくれたのである。寡黙で毅然とした人達の暖かさ、貧しさを超越して悠久なる自然と共生する、彼らの優しさを感じたひとときであった。
<イスラムの服装など風俗について>
ひとくちにイスラムといってもイランやインドネシア、マレーシアまで幅広く、簡単に言い表すことはできないが、ここでは中東や北アフリカなどで見る印象について述べる。
トルコなど近代化されたイスラム世界の男性の服装は、背広を着て靴を履いている(戦前のレバノンもその通り)。カイロやカサブランカなどの都会では、機能性を重視する生活圏では同様である。しかしながら、都市におけるビジネスマンをのぞけば、男子の場合、頭からすっぽり被る袋状のジェラバと呼ばれるフード付の服装をしているのが普通である。ジェラバを着て、町中をぶらぶらしたりしている風景は、アラビア半島や北アフリカの人々には、よく似合う。
この服装の良さは、下に何を着ているのか判らないようにボロ隠しになるという利点の他に、防寒、防暑、防砂の為にはなくてはならないものなのだ。砂漠など乾燥地域の生活は日中と日が沈んでからは極端に温度差があるので、このジェラバを着ることで、日中は太陽熱を遮り、夜は防寒の役目をするという具合だ。真夏の炎天下といえどもほとんど湿気がないため、防暑の働きを成すわけである。履物は親指付のサンダルである。
その他の用途として、時間通りに来ない運行バスを待つ間、土漠の中にある停留所などでは、フードをすっぽり被って、いつ来るとも知れないバスを何時間も待つのである。もちろん、地べたにそのまま身を横たえてのことで、非常に便利な物である。
地面はほとんど水分など無い乾燥した大地なので、多少ホコリで汚れても、手で2、3回ホコリを払えば問題は全くないのである。以前、砂漠の真ん中で小用を足していたら、誰もいないように思われた大地から忽然と人が湧き出るようにあちこちに現れて驚いたことがある。彼らが徒歩で用向きを足しに出かけるときには、目的地までの道のりの中で、疲れをとるために土漠に身を横たえて仮眠を取ったりもしているに違いない。
小生もマラケシュのバザールでジェラバを一着買い求め、モロッコ滞在中、何日か着て歩いたことがあり、快適さに手放しがたい思いをしたことがある。このジェラバの下には普通ズボンをはいていて、上半身はセーターやジャケットを着ており、脱げば我々と変わらない服装をしている。
女性の場合も、身体をすっぽり包み隠すように男性同様のコートを身につけているが、これはジェラバとは呼ばない。カフタンといって、生地や色合いにも女性らしく柔らかなイメージがある。フードはついていても普段あまり利用しないが、代わりに、日本の「おこそ頭巾」さながらに頭部を布ですっぽり隠しているのである(独身女性はしない)。アフガニスタンのタリバンが強要して着けさせたブルカである。
コーランの教えでは女性の肌は、夫や家族以外の男性には見せてはいけないと、教えられているので、いろいろな工夫をして身を隠している。頭巾のみでは口元や頬の部分などが露出するので、口元を着衣と同じ材質や色をした大きなマスクで隠し、更におでこから口元にかけてきめの細かいレース状の布で覆っている。誠に異様というか不気味な感じさえするのだが、慣れてくると何とも言えず、アラブに来ているという感じがしてぞくぞくするのだ。
顔面を隠すレースをつけない場合、露出する顔の部分にレース模様の入れ墨を施し、素肌を見えないようにしている。入れ墨と書いたが、日本の入れ墨のように針で刺すのではなく、ヘンナと呼ばれる植物の染料で顔に書くのである。もちろん、手首や足首も露出してはいけないので、この部分にも同様にヘンナで細かな模様を描いている。(直近の2003年の旅行では、そのような風俗もだんだん減少している様子で、女性の服装は欧米化してきている印象を受けた。)
最初にモロッコを訪れたとき、車付きガイド兼通訳のブラッヒムアカザンという青年を雇って、アルジェリアの国境を越えたり、アトラスを越えてサハラの玄関を訪ねたのだが、彼はとても紳士的で教養と礼節ともに言うこと無しで、ずいぶんとあちこち一緒に見て歩いた。その際、何故モロッコの女性は入れ墨をするのかと訪ねたら、それは信仰心の篤い証拠なのだ、という答えが返ってきた。コーランの通りに信仰を守れば、素肌の露出を避けるためにそうなるのだとのことである。それ以来、ちょっと異様に思っていたこのヘンナの染料で描いた入れ墨の女性を見ると、敬意も湧いてきて美しくさえ感じられるようになったものである。
この時のガイド兼通訳のブラッヒムアカザン君も今では60歳近くなるのだろうか。本当に信頼できて、語学に堪能なそしてあらゆるアラブの歴史等について詳しい好青年であった。彼はその後、ショーンコネリー主演の「風とライオン」にもガイド役としてスクリーンに出演しているが、今でもガイドをしているのだろうか、読者の中にマラケシュのジェイマル・フナの広場で彼からガイドを受けた方もいると思うので心当たりがあれば消息を知りたいものだ。
衣装のことで書き忘れてならないのは、主として婦人の場合は、色によってそれぞれの部族が区別されている。同じベルベル族でもモーリタニア系とかチュニジア系、そしてサウジアラビア系とイエメン系など、一目で判るようになっているのである。青いカフタンで統一していればブルーメンと呼ばれ、これはサハラの方からの部族で交易のために来ていると判るのである。
判りやすい例えで言うと、中東和平のことで世界中を飛び回っているパレスチナのアラファト議長がいつも頭に被っている(カーフィルと記憶しているが)スカーフ状の物でも、そのチェックの色や形はアラファト議長の出自を明確にするのである。すなわち、このモザイクのような民族のアイデンティティーを明確にする手段となるのである。サウジアラビアなどは白っぽい布地を身体にまとい、頭巾はヘアバンド状の物で止めているが、このヘアバンド状の物にも工夫があって、クライシュ族であるとか、またはその地位がどの程度になっているのかということが識別されるようになっているらしい。
女性はカフタンという袋状の上着の下に、色とりどりの欧米風の衣服を身につけているということである。このことは、筆者がアメリカ留学時代にイランパーレビ王族の、ファティマという女性が同じクラスにいて、彼女から聞いたことである。いずれにしても女性同士の集まりでは、結構華やかに衣装を楽しんでいるらしい。しかし、表に出て不特定多数の人と接するときは、単色のカフタンを身にまとっていて、地味に見える。珍しいと思ってカメラを向けたりすると大声で拒絶されることは必定である。
そのような地域を旅行するときは、女性は素肌を露出するような、ショートパンツやノースリーブは遠慮するべきであって、旅行を予定する場合は長袖シャツなどを持参すべきである。
<アラブ・イスラムで感じたことなど>
欧米人とアラブ人(イスラム)との違いのひとつには、時間に関する認識が全く違うということがあげられる。砂漠の中で暮らしていて、砂嵐にあったりして、予定の時間に到着できないとき、緊急連絡すべきことがあっても、通信手段が確保できないなどで、待ち合わせ等に正確を期しがたい。そのような、生まれついての生活環境の中で、時間には無頓着な性格が形成されるのは当然なのだろう。
男達は失業率の高いせいもあるが、チャイハナ(茶店)に寄って日がな一日ミントティーをすすったり、カ-ドを楽しんだりして過ごしている。特に長い水ギセルの煙草を吸うたまり場では、長い衣装を引きずって悠々とひとときを過ごしている。このような光景は東のトルコやシリアであっても、西のマグレブの国であっても少しも変わらない。
発展途上国と言われる国の子供達は、小さいときから家計を助けるため、また、病気の親の薬代を稼ぐため、危険な交通量の多い路上に出て新聞や煙草を売ったり、そして、信号が変わるまでの短い間に、停止する車の窓を拭いたりして少しばかりの金を求めてくる。そのような状態は決してほめられたものではないが、これらの経験の中から必死に生きるための知恵や工夫が為されて逞しい生き方を体得しているのである。
ひるがえって、日本の子供の育て方を考えてみるに、目標を与えることをせず、泣いたり、怒ったりするのが怖いため、小遣いを与えたりして甘やかして育てている。このような育て方をされた人間が、どのようにして将来、あのように苦労して育った人々と渡り合っていけるのかと、はなはだ心配になる。このような風潮から生まれる国の将来というものは、政治家のひ弱さなどにもつながり、国際政治の中で敬意を払われることなく翻弄されてゆくであろう。今のうちに国家とか、人生とかを充分に認識させて、その上に立って真のエリートを育成することが急務であると思われる。
パリのホテルクリヨンやリッツなどのレストランでの会食する機会があった折に、何度か日本人の政治家や官僚と外国の要人との会食風景を眼にしたことがあるが、一部の人を除いて日本人の政治家や官僚は、手もみをしながらぺこぺこと頭を下げている。そのような現場は、見ていて気分の良いものではない。政治哲学や国家観が基本にそなわっていれば、商人ならいざ知らず、手もみをしながらペコペコするような態度はとらないだろう。一国を代表する立場の人が実に情けない。なめられるに決まっている。
話題が飛んでしまったが、アラブ世界では、人々の逞しさからいろいろと考えさせられることが多い。
<世界文明の十字路イスタンブール>
イスタンブールほど面白く興味深い都市は世界中に存在しようか。栄華を誇ったローマ帝国を作り上げたイタリアでさえ対抗できないのではと思えるほどに、この国に重層に塗り込められた歴史によって、尽きない興味を与えてくれるのである。それはこの国が一言で言い表せない多様な民族と文化の混交により成り立っていることに起因する。これに比べれば、エジプト文明でもローマ文明でも、スケールを別にすれば単調な歴史にしか思えないほどである。
イスタンブールは、元々はビザンティウムと呼ばれていたが、東ローマ帝国の時代に、コンスタンティヌス帝の支配によってコンスタンチノープルに名称が変わり、さらにはメフメット二世のオスマントルコに支配されるに及んで、イスタンブールに改名させられたのである。
このイスタンブールの町を逍遙すれば、様々な顔立ちの人達に出会う。トルコ人の他、ギリシャ人、ユダヤ人、クルド人、アラブ人、モンゴル人、カフカス人、ペルシャ人など、ありとあらゆる民族の顔立ちの人がそこに住んでいる。それよりむしろ、1人の人間の中に、それらの血が全部混じっているのではないかと思わせる人達も多くいて、まさしくここは、民族の博覧会場のような多様な人達が暮らす大都会なのである。各地方に行けば、土着の民族が、民族毎に住んでおり、比較的混交しないで生活しているのであろうが、このイスタンブールは、文明、文化の十字路と言うべき土地柄である。民族の博覧会場という言葉が世界でもっとも相応しい都市なのである。
イスタンブールの町は、ボスポラス海峡を隔てて、ヨーロッパ大陸とアジア大陸の2大陸に分かれている。ヨーロッパ側は市の中心街を形成しており、アジア側のウシュキュダル地区は住宅街を形成している。朝の出勤時にはアジア側の居住地からボスポラス海峡をフェリーで、あるいはボスポラス大橋を車で、ヨーロッパ側に出勤する人たちでごった返し、夕方は、その逆である。このような壮大な出勤風景は世界中さがしてもここだけであろう。ちなみにヨーロッパからの鉄道の終着駅はシルケジ駅であり、アジア側終着(始発)駅はハイダルパシャ駅である。そこからフェリーに乗れば10分そこそこで向かい側の別な大陸に着くのであるから面白い。
現代のヨーロッパ文化に多大な影響を与えたのはギリシャ文化であり、次にそれを継承した形のローマ文化が影響を与えている。イスタンブールがかつてはアテネの植民都市であり、トルコとギリシャは隣接しているため、相互に影響をし合ったと言えよう。当然のことながらギリシャ文化を通じてトルコの西欧への影響もあったわけで、スラブ社会へも黒海を横断して深く入り込んだに違いない。
トルコへはアジア側からはペルシャ、すなわち今のイランによる侵略もあり、アレキサンダー大王の東征によって、ギリシャ文化、そしてイランやインド文化も、さらにはモンゴルすなわちタタールやスキタイの文化が移入したに違いなく、こうしてみればトルコとトルコを代表する歴史的大都会イスタンブールは、黒人世界やポリネシアなどを除けば、ありとあらゆる民族が入り込んでいることが納得できるであろう。違う場所に新しい文化が根づき、また、前の土地の上に更に新しい文化が重層的に張り付いて、次第に今日の形成を見るに至ったのである。トルコの文化は歴史的にはビザンチン文化と呼ばれており、帝国の華やかなりし頃は、世界に最も広く影響を与えていたのである。
イスタンブールのみならず、この国全土の歴史的遺産は驚くばかりである。イズミールへの途中のトロイ遺跡周辺には使徒パウロが生まれているし、聖女マリアの墓地もそこにある。エーゲ海沿いにはヘレニズム文化の花が開いたベルガマもある。アンタルヤはセルジュークトルコ朝の港町として栄えた土地である。海岸線は地中海地方有数の景観を誇り、現在はリゾート地としてにぎわっている。アンタルヤの近くには素晴らしく魅力的なセルジュークトルコの古都コンヤという町がある。ここは神秘的な宗教的な踊りで知られている。かなり前のことだが、バスでアンカラからコンヤに立ち寄って、アンタルヤに至り、イスタンブールに飛行機で戻ったことがあるが、その素晴らしくエキゾチックな雰囲気は、今でも鮮明に覚えている。
イスタンブールについて話し始めると、話題は際限なく広がってゆく。
旧市街の中心部イスタンブール大学に近い場所にグランドバザールがある。金銀細工や革製品をはじめ、なんでも売っている。バザールの建物は驚くほど立派で、天井付きの壮麗なビザンチン風のものである。エキゾチックこの上ない雰囲気の中で、ついつい財布の紐が緩んでしまい、後で必要ないものを買わされたと悔やむことになることは請け合いだ。ここから金角湾の方向に5分ほど坂道を下れば、日用品、生鮮品なども置いてある庶民的なバザールのエジプシャンバザールに出る。香辛料のにおいが鼻について刺激的である。
エジプシャンバザールのすぐそばは、ロシア側から黒海を渡って南下してくる観光船などが出入りする港である。旧ロシア体制が崩壊したすぐ後に訪れたときは、この辺りの路上には、旧ソ連の軍服やキャビア、旧ソ連の高官が持ち込んだと思われる品物の数々が並べられ、あちこちで激しい客引きの声が行き交っていた。100g程度のキャビアが1~2米ドル前後という信じがたい値段で売られていてびっくりした。もっとも塩分が強すぎて、お世辞にも上等のものとはいえなかったが、紛れもない本物であった。これらの商品は、旧ソ連が崩壊する際に、政府高官を巻き込んだ各経済部門が換金を図ろうと、自由主義の窓口でもあるイスタンブールに持ち出した物なのであろう。当時(1990年末ごろ)は、ルーマニア、ブルガリアなどの東欧諸国の人たちも、無数に路上に市を開いていて、安ホテルに泊まった際には、それらの行商人で混雑していたことを記憶している。自分の国から品物を持ち込んでそれを換金し、物々交換などしてそれをまた本国に持ち帰って換金するといったことを繰り返す商行為が、旧ソ連をはじめとして目先のきいた連中によって始められたに違いない。現在の経済マフィアといわれる人たちの原点もこのようなところにあるのかもしれない。
旧市街には、ブルーモスクの愛称で親しまれるスルタン・アフメッド・ジャミイや、東ローマ帝国時代に建造されたギリシャ正教会でその後イスラムのモスクとして使われているアヤ・ソフィアがある。イスタンブールの朝は、夜明けとともにこれらのモスクのミナレットからスピーカーで流されるコーランの音で目覚めることとなる。それはそれはとても印象的で、エキゾチシズムに満ちた夜明けとなる。イスラム諸国にとっては普遍的な日常である、独特のあとをひくようなコーランの読経(アッザーンという)も、普段聞きなれない日本人にとっては、遠い国に旅してきたという感慨を持たせてくれるものになる。
メデゥーサの首を水中に逆さにして礎石としているのは、イエレバタン・サライとして有名な地下宮殿である。100メートル前後の長方形の地下を300本あまりのコリント様式の柱で支える地下宮殿は、トプカプ宮殿の飲料水を蓄える水がめとして建設されたものであるが、素晴らしく立派であり、単なる貯水池などと呼ぶことがためらわれる壮麗なものである。以前ジェームスボンドの主演する007の映画でここを舞台にした印象的なシーンがあったように思う。
数限りない見せ場の中で、イスタンブールを代表する見所といえば、なんと言ってもトプカプ宮殿であろう。中国陶器や日本の古伊万里などの収集品も充実していて、これらのコレクションではドレスデンの美術館にも匹敵するといわれている。巨大な世界最大級のエメラルドや謁見の間の金の玉座などは、あまりにも豪華すぎて声も出ないくらいである。日常、宝石や貴金属が好きで多少無理をしてでもこれらを買い求める人も、ここに行けば自分の趣味もケチなものに思えて、いやになってしまうのではないかと察せられる。トプカプ宮殿にはまた、美女たちのハーレムがあり、「宦官」たちもからんで繰り広げられたサルタンとの生活を隔てる間仕切りの構造も面白い。
1000人前後の人が働いていたという台所も見ることになるのだが、ただただ驚くばかりである。トプカプは一見すると、ベルサイユやベルベデーレ宮殿などと違い、外観はそんなに立派に見えず、むしろ質素に見えるのだが、内容的には世界に冠たるトルコ帝国の偉大さを伝えるに十分な場所である。
宮殿からは、マルマラ海を通行する船を全て見渡すことができて、しかも金角湾に照り映える夕陽を眺められる。これまた素晴らしい風情である。イスラム、ギリシャ、ローマの文化が混ざり合った独特の雰囲気は、ただただ感銘深い。かつてイギリスの名宰相ディズレリー卿が議会での演説の際に、ビザンチンの服装をしてトルコに関しとうとうと論じ議会を酔わせたことがあると、鶴見悠輔氏の「グラッドストーンとディズレリー卿」で読んだことがあるが、むべなるかなと感じた次第である。
トプカプ、アヤ・ソフィア、ブルーモスクは近接していて、歩いてすぐ近くである。坂道を下ればヨーロッパ大陸の鉄道の終点シルケジ駅に至るのだが、そこから目と鼻の先にフェリーボート(渡し舟といったほうが適切)が出ていて、アジア側と頻繁に往来している。ここからは歌で有名なウシュキュダルやボスポラス海峡を通って黒海が近い。旧ソ連時代に最も重要であった不凍港であるオデッサなどにも行けるのである。
ガラタ橋というイスタンブールの人たちに日常的になじみ深い橋があり、イスタンブールの新旧の市街地をつないでいる。橋は二層になっていて基部の部分ではマルマラ海で取れるサバやイワシの塩焼きなどを出す料理屋が軒を連ねており、庶民的な雰囲気の中でアラック(水を加えると白濁する酒)などを飲みながら地元の人に溶け込んでほろ酔い気分になるのは、大きな楽しみのひとつである。こんなときは、味の良し悪し、清潔だとか不潔だとかにこだわってはいけない。あくまでも地元の庶民の生活を知りたいという気持ちで出かけなければならない。朝早くコーランを唱える音で目覚めたら、ガラタ橋かそこから1500メートルほどの南側にあるマルマラ海にある魚市場に出かけて見れば、とれたての魚が並べられており、見ているだけで楽しい。
旧市街の中で必見(必体験)は、いわゆるトルコ風呂のハマームである。外観はさることながら、中に入った途端、その石造りの、小さな体育館ほどもあるような建物の中に、立派な髭をたくわえた壮年の男たちが客を手ぐすね引いて待っている。ドームの中心にはどこからともなく蒸気が流入しており、そのむくつけき男の案内で、ちょうど一人が横たわれるほどの石の台の上に身を横たえると、タワシのようなもので体を洗ってくれる。その後にコンパートメントを思わせる小部屋の中でマッサージをしてもらうのだが、彼らの力強いマッサージは、体がばらばらにされるのではないかと心配になるくらいである。しかし、その後は実に気分爽快この上ない。
このトルコ式の風呂のことはハマームというのだが、これは何もイスタンブールに限らず、シリアのダマスカスやモロッコのフェズやタンジールなどのイスラム世界に共通したものであり、日本のマッサージつきサウナなどよりはるかに贅沢な気分にさせられる。10年程前、日本に居住するトルコ人の抗議によって、かつてのトルコ風呂と呼ばれた歓楽施設は、ファッションマッサージなどという横文字名称に変えられた。その妖しげなものをトルコ風呂などと呼ばれたら、怒るのはあたりまえだろう。ハマームは元来、身や心を清める精進潔斎、いわゆる斎戒沐浴の意味があるのである。
庶民の生活になじんだガラタ橋を渡れば、イスタンブールの新市街であるタキシム広場に出る。ここにはかつてヴェニスやジェノヴァなどの商館が金角湾沿いに建ち並び、いわば租界のような場所であったと聞いている。坂の上にはヒルトンやシェラトンなどの近代ホテルや諸官庁の高層建築が建ち並んでおり、旧市街のような雰囲気とはおよそかけ離れている。それでもヒルトンホテルなどは、外観はアメリカンスタイルながら、内装はビザンチン風に彩られており、居心地が良い。
トルコ人に共通して言えるのは、ほとんどの人が旧ソ連に嫌悪感を持っていることである。これは、露土(ロシア-トルコ)戦争に痛めつけられたことに端を発しているように思われる。反面、対日感情は非常に良い。これは日露戦争で日本がバルチック艦隊をせん滅し、トルコの恨みを晴らしてくれた、という感慨を持つ親日家が多いからである。
トルコは第一次世界大戦後、敗戦国として分割され国土の大半を失ったのであるが、完全に解体される前に、救国の英雄ムスタファ・ケマルが立ち上がって、ぎりぎりのところで独立を成し遂げた(彼は後にケマル・アタチュルク(トルコの父)と名のることになった)。その後、彼は首都をアンカラに移したが、イスタンブールでも政務を執っていた。彼が最後に執務した建物では、時計が彼の死亡時刻にすべて合わせられ止まっている。今でもケマル・アタチュルクは限りなくイスタンブール市民、いなトルコ国民に愛され続けている。
<アジア側のトルコ>
カッパドキアへは、アンカラからバスで行くと便が良い。このアナトリア地方は鉄を最初に作ったヒッタイトから始まる歴史があり、かつ陸路シルクロードによって古くから東洋と密接な関係があったのである。バスに乗って、アジア西端のシルクロードを通ってキャラバンサライ(隊商宿)の遺跡で歴史を追想するのも悪くない。
トルコの東南端の湿地帯を大きく抱えたアダナという聞きなれない空港に降り立ち、一泊したことがある。ここは、アナトリアや他のトルコの地方とは打って変わって近代的な工業都市である。広い洪積平野は紫色を帯びた土壌で覆われていて、乾季には砂漠を思わせる不毛の地のようであるが、トルコでも有数の都市であり、人口も100万近い。シリアとの国境にも近い。
トルコは国土が広く、東部にはノアの箱舟で有名な海抜5000m級のアララット山があり、地中海辺りまでタウロスの山肌がシリアやイラクなどを分けている。このためポツンと海岸線にあるアダナの町は、その地形から訪れる前は辺境の地に違いないと思わせたのだがとんでもない。タウロス山系の地下の伏流水などに恵まれて、見た目以上に暮らし易く裕福な土地柄であると思われた。アダナではローマ時代からの植民都市の遺跡を見て回った。
この町を訪れた理由は、地中海に面したシリア国境沿いにアンタクヤ(アンチオキヤ)という町が近くにあり、この港湾古都が中国に始まるシルクロードのひとつの終点として過去に栄華を極めたと聞いて関心を持ったからである。背後にせまる山脈は、切り立った山並みとなっており、トルコ東部やシリアの北部国境の象徴的な地形を成している。白っぽくむき出した巨岩巨石が疎林の緑に囲まれて印象深い。この辺りから、アララット山に向かってイランやアルメニアに至るシリアとの東部国境付近は、今でもクルド人などの山岳民族による山賊行為が頻繁にあるそうで、旅行者としては安易に近づくべきところではないようである。
トルコはイスタンブールやイズミール、アンカラのような大都会を除けば交通量が非常に少なく、スピードを出したくなるが、道路にでこぼこがあったり、路肩がもろいので車を運転する場合は要注意である。アンカラを中心とするアナトリア地方は高原がなだらかに広がっているので特にその傾向が強い。国全体を通してみると、山岳地帯が多いのでカーブが多く、ついついスピードを出しすぎて、出会い頭に車を避けきれないという場面もありそうだ。アナトリア地方やカッパドキア地方では冬期には積雪があり路面が凍結するので、この時期のドライブは避けるべきであろう。
<シリアそしてパルミラの遺跡を訪ねて>
シリアには1993年に、若いドライバーを同行させて、ダマスカスから北はトルコ国境まで、そしてさらにレバノン国境へとレンタカーを借りて旅をしたことがある。初めて訪れるシリアだったので、リビアと並んでテロリストをかくまう国家との印象が強く、深夜にダマスカス空港に到着した時は少し緊張したことを覚えている。空港に到着するなりマシンガンで武装した兵士が空港を守備し、暴走するトラックなどが直進してくるのを防ぐように配慮された分厚くて大きな鉄釘のバリケードがジグザグに配置されているのが目に入った。否応なしに、戦時体制がしかれていることが感じられたのである
シリアを訪れたときは、少し中東の歴史について不勉強だったと思い知らされたのだが、その後の経験によって、このシリアほど古くからの歴史と誇り高い民族もないのではないかと思うようになったのである。
その昔のシリアは、ヨルダン、イスラエル、レバノンなどを包含して大シリアとよばれた偉大な国家だった。世界に覇権を目指したことはないにしても、中東の人間にとってダマスカスはカイロと並んで尊敬と羨望の町であり、これは今でも変わらないと思う。中東においての学門の中心地であるダマスカスの人々は、貧しいながらも誇りと気品に満ちて暮らしている。われわれ日本人が持つ印象では、シリアはテロリストの国であり、今は亡きアサド大統領の独裁国家であるというものである。それも当然理解できるのだが、なにしろ、この国はその昔に大シリアと呼ばれた時代には、エルサレムにキリストが生まれ、世界最古の町として知られるイリコやビブロスもあり、地中海世界に覇を唱えたフェニキアの歴史もある。そのようなことから、人々の誇り高さと気品ある表情についても納得がいくのである。十字軍に対して果敢に戦ったサラディンの土地でもあり、医学などの学問の中心地でもあった。この町ダマスカスは一度訪れたら最後、魅力に取り付かれても不思議はないほどである。それはダマスカスのもつ独特の歴史の深い雰囲気と表情が我々を虜にするからに相違ない。
ヨハネの墓もサラディンの墓もあるダマスカスから、紅海の(今はリゾート地で有名な)ヨルダンのアカバ湾までヒジャーズ鉄道が通っていて、かつてはメッカ巡礼に重要な働きをしたのである。この鉄道はかつてアラビア半島に至るルートを結んでいたが、今では駅舎があるものの鉄道は休業になっていて、利用されている形跡はなかった。
シリアの東西南北を意識して走り回ったが、国中いたるところ、道路のあちこちに巨大な立て看板が見られた。独裁者「アサド大統領の肖像」であった。今は息子の代になって、他国との融和も進んで少しは様子が違うと思うのだがどうだろうか。再訪してみたいものである。
テロや独裁国家などという恐ろしい一面を忘れるならば、この国の人たちの気質ほど、心休まるものはないのではないかという印象がある。心根が優しく、慈悲に満ちて純粋さを思わせるその目元は、全ての警戒心を一度にしてぬぐい去らせるのである。一般市民の表情、とりわけ子供にそのような印象がある。イエスキリストそしてヨハネが生まれた国であり、かの英雄サラディンの国であることを痛感させられる。シリアの国境を守る厳しい軍事上の出来事も、この一般市民の安寧を守るためのものなのだろう。厳戒態勢の中のシリアの国内に入って痛感させられた大きな収穫のひとつであった。国内はきわめて治安が良く、やさしさと人なつっこい人々がいて、小生の好きな国のひとつである。
また、シリアほどに美人の多い国もないと思われた。セム系やハム系であろう、肌の透き通るような、そして肉感的美人の多いこの国では、街を歩くたびに、はっと息を呑むようなことが多かった。もっとも、観光客として、この国一番のウマイヤッドホテルやチャームホテルに滞在したことで、この国の上流社会の女性たちを見ることが多かったため、そうした感じを抱いたことと思う。たしかに貧しさのうちに美貌が失われ、苦しい人生を感じさせるような人もいたのだが。それでも、小生にとって、美人の多い国はどこかと問われれば、シリアだと答えるに違いない。
パルミラという偉大な遺跡がこの国にあることをご存知だろうか。ダマスカスから車で走って3時間くらいのところ、シリア砂漠のど真中にこの遺跡がある。かつて中国から地中海に至るシルクロードの隊商は、宿駅として、水や物資を補充する地点として、ここを必ず通ったのだと聞いた。ローマ帝国の前進基地としての位置付けもあったといわれるが、そのうちに、シルクロードの隊商から通行税や関税を徴収するに及んで、国の隆盛がもたらされ、最後の女王ゼノビアの時代、3世紀になって、その強大な力を背景にローマ皇帝と張り合ったことから、ローマ皇帝の怒りに触れて破壊され、砂に埋もれたまま近世までかえりみられなかったのである。その繁栄は600年にもわたる長い間続いたのであり、それに相応しいスケールの大きさに圧倒される思いのする遺跡である。世界を代表する遺跡である3Pのひとつとして(3Pはピラミッド、パルミラ、そしてヨルダンのペトラ)、人類の遺産であると思われる。
<中東のパリといわれたベイルート>
ベイルートはレバノン紛争で知られており、パレスチナゲリラなどの危険が想定されることから殺伐とした印象があるが、このような認識は1975年以降のことである。以前のベイルートを知るものには、また歴史的に見て、ここは中近東を代表するとても素晴らしく洗練された都市なのである。
古代フェニキアの王都であったこの町は、風景、人情、物産、気候のどれをとっても中近東で輝ける文化的な都市で、中東のパリといわれたほどである。エジプト、サウジ、イエメンから、またシリア、そしてイラクなどから、その文化的な雰囲気を求めて、勉学のため、ビジネスの拠点として、ベイルートに多くの人がやってきた。レバノン内戦の始まる1975年以前は日本の商社の支店も多く、またイラン、イラク、サウジアラビアなどをはじめとする中東の石油施設で働く日本の商社マン、エンジニアたちが、息抜きの場を求めてベイルートにやってきていた。アメリカン大学もあって、アメリカの中東政策の拠点としても栄えていたのである。
街中にはペルシャ絨毯の店や、ホテル・フェニキア、ホテル・リヴィエラ(レストランミチコのある)などの五つ星クラスのホテルも林立して、車で40~50分も走れば、ショーの舞台に象などが出てくるほどの規模のカジノがあって、フレンチカンカンなども愉しめたのである。東側は、アンチレバノン山脈が走り、中東にあって、万年雪に覆われている。この山脈は秀麗を誇っており、シリアとの国境にもなっている。この間、車で2~3時間も走れば、シリアの主都ダマスカスに到着する。
古来、地中海世界を駆け巡ったフェニキア商人については今に至るまでその名声がとどろいており、その意味においてこの国の人々の国際性は、日本などと比較すれば雲泥の差がある。
そのシリアとレバノンを隔てるアンチレバノン山脈とレバノン山脈の中腹にベーカー高原があって、ここに日本赤軍などのテロリストグループの拠点があったことは、多くの日本人に知られている。しかし、かつて、華やかで洗練された都がレバノンのベイルートにあったとの認識をもつ日本人は、一部のアラブ通を除けば皆無に等しいであろう。
世界最古の街は、イスラエルのジェリコ(イリコ)であるが、世界最古の港湾町は、地中海に面したベイルート近くのビブロスである。バールベックの遺跡もシリアにほど近い中部にある。
小生は若かりし頃、好んでベイルートの町に滞在したことがある。ホテル・リヴィエラの日本食レストランミチコに滞在して、マダムミチコの知遇を得たことは前にも述べたが、この地に惹かれたのは、単に穏やかで一年中春を思わせる気候の快適さや諸設備の洗練された雰囲気にあるのではなく、この国の国際性に強い印象を受けたからである。町のレストランに入れば、欧米、中東、ありとあらゆる人たちが客として集まっており、そこに働くボーイたちの動きには目を見張るものがあった。さすがに日本語はほんの片言であるが、ドイツ人と見ればドイツ語、フランス人と見ればフランス語、スペイン、アラブ、そして英語圏の人々に対して、それぞれの言葉で、それもどこから来たなどと聞かず、彼らの直感によって、それぞれの言葉でてきぱきと捌くのであった。ひとりで4~5ヶ国語を操るのはあたりまえであり、あまり語学に達者でない小生も、その流暢な、よどみのない言語能力には、ホトホト感心させられた。数日間滞在することで、それが一部のウエイターだけでなく、商行為に携わる人すべてに共通して、言語に長けていることがあたりまえとされているのがわかり、さすが、フェニキア商人の町と感じ入ったのである。
この国はありとあらゆる民族や宗教が共存するモザイク国家である。このことが近年のレバノン紛争の起因となったのであろう。ある特定の国が、自分の宗教や戒律を押し付けてくることによって、この完全に見えたモザイク国家は、もろくも崩れ去ったのであろう。とにもかくにも、もったいない町が壊滅したのである。テレビ放送などで、無残にも砲撃された建物を見ることは、古きよき時代のベイルートを知る者にとって、寂しさを感じるものがある。さぞかし、マダムミチコも戦乱の中でつらい思いを経験したに違いない。
歴史的な長い目で見れば、この戦乱状態も収まり、再びベイルートは蘇るに違いない。なぜなら、これほどの快適な気候と明媚な風景は中東のどこにもないのであり、その地勢学的位置から見ても、放っておかれることはないだろうと信じるからである。
~ 閑話休題 中東紛争から学ぶべきこと ~
人間は悲しみと喜びを感ずる動物である。戦乱の結果もたらされる肉親を失う悲しみ、恋人を戦場に送る悲しみ、家財を失う悲しみなどが一方であり、もう一方では戦場から帰還する恋人との再会の喜び、そして戦争に勝利するという喜びもあろう。だがいずれにしても痛ましくもあさましい、戦争というこの愚かなる人間の行為は、いつ終わるのであろうか。
しかしながら、繰り返される個人間の「いさかい」をはじめとして、戦争などの行為を反面教師として、人間の思いやりとやさしさ、相手に対する立場を越えた理解などは育まれてきたのかもしれない。喧嘩をして初めて本当の友情に至るということがあるが、頭で考えたことではなく、血を流す、親族や恋人を失うなどの、泣いても泣ききれない深い悲しみを経て、人間として最も大事にしなければならない愛情のなんたるかを知るのかもしれない。
だとしても、神様もむごい試練を課すものだ。特にイエルサレムの聖地を巡るキリスト、ユダヤ、イスラムの諸宗教による相克の歴史はいつ終わるとも知れない。このように神はこの地エルサレムに、すなわちパレスチナに生を受けた人々をユダヤ人の言うように人類の選民となし、彼らに殉教の苦しみを与え続けることによって、これ以外の人類に反面教師としての役割を負わせたのであろうか。世界中の人民に平和のなんたるかを知らしめるための、神の謀り事だったのかと思わせることがあって怨めしく思われる。神は人知を越えたところにあり、時には冷徹非情に人類に鉄槌を下すことがあるのであろうか。ジハード(イスラムの聖戦)などの試練を与え、その代償として信教者に天国の約束を与えてこれを救い、バランスをとっているのであろうか、問うてみたい気がする。
人間と人間の関係は、互いに礼儀を尽くさなければならないことは当然であり、礼儀こそがすべての基本であると信ずるが、真に友情を育み理解し合うためには、肝胆を開いて互いに本音を主張することが第一である。それを乗り越えて理解し合わなければならない。時としてムキ出しのエゴが衝突するもことそのためにはあろう。主張をぶつけあうことで、相反する利害の問題が確認され、その結果口論になったり、喧嘩沙汰になることがあるわけである。
国家間においては、先に述べたとおり、戦争にもなるだろう。しかし相互理解のためには、このようなプロセスも時として覚悟せねばならない。そのような経験の中から無意味な血を流すような愚を避けるために、互いが譲り合ったりするのである。この結果、大人と言われるようになり、成熟した風格も備わってくるものであろう。
それに反して最近の我が日本の男性諸氏にみられる風潮はどうであろうか。生きるために自分をむき出しにして戦う気概がうすれたことはいいとして、ただただ人との軋轢を恐れるがゆえに難しい問題の種を後回しにして、相手の主張に合わせて、その場を取り繕うとする表層の優しさのみに惰しているのではと思えることの方が多い。もちろん、むき出しの闘争心はご免こうむるが。今すこし骨太い生き方を見習っては如何かと思えるのである。問題を起こしたくない、相手に良い印象を与えたい、このようなことは誰にとっても望ましいことに違いないが、根本をないがしろにしたまま、このような態度に終始していれば、必ずや何らかの形で、その反動がくるに違いない。
昨今のニュースに取り上げられる、残酷な少年犯罪なども、容疑者を捉えてみれば、温和でやさしい子供だったり、誰にでも好かれる成績の良い子供だったりする。小生にはなるほどと思われるのだ。親の言いなりになり、学校の先生の良い子になって、勉強のみに明け暮れてばかりいては、いつかその子供が自我に目覚めたとき、コントロールを失い、常軌を逸する妄想にとらわれて行動するのは、ある意味では当然の帰結と考えられなくもないのである。
教育の問題は難しいに決まっているが、親が人生の何たるかに見極めがつかず、ただただ世間体を装うがために、お行儀の良さを押しつけてばかりいては、問題は解決されない。局面において徹底的に息子や娘と相対峙するなかから、真剣に生きようとする志が芽生えるものと思っている。
基礎的訓練や試練を与えることは大事である。少年に至るまでの幼児期や乳児期を通じて、親が子に対して人間として在るべき姿の基本を徹底的に教え込まない限り、何の目的意識もなく、物事に感動したり感謝したりすることもなく、宇宙の無重力状態に漂うがごとく無気力で心を失った人間が育つのはわかりきったことだ。子供の自由に任せるということは、少年期までの間に、徹底的に躾を教え、思慮分別のついた頃になって社会に順応させるために、ライオンが千尋の谷に我が子を突き落とすがごとく、ひとり立ちさせるため我が身の寂しさをこらえながら手元から離すことである。子供はそのような苦痛や、物のない不自由などの中から、忍耐を覚えたり工夫することを覚えたりして、ひとり立ちする力と心を養ってゆくのである。
<アレッポそしてトルコ国境の厳戒態勢>
ギリシャからトルコを経てシリアに至るまでの間は、一部を除いて途切れ途切れのドライブ旅行をしたが、イスラエルには行っていない。
古代の遺跡パルミラに行ったついでに、シリアの北部にあるアレッポの町に着いたのは夜遅くであった。アレッポは4000年もの歴史のある古都であり、ビザンチンの都への往還、あるいはエルサレム巡礼の際には重要な拠点となった都である。シリアで二番目に大きい都会であるが、今では、交通の要衝であった昔日の面影は感じられず、落ちぶれた感じの漂う土地である。ここの見所はバザールで、アーケードの天井にドーム状に黒い屋根がかけられており、その天井に無数に開いた小さな穴から太陽光線が入り込むのが印象的である。朽ちて穴があいたのか人為的に星空のように見える天井を作ったのかは判らないが、ここには庶民の暮らしの全てがある。
アレッポの城塞は市を見下ろす高台にある。2000年以上の歴史を持つ風雪を経た古城である。地理的にも重要な地点にあったため、長い年月の間、要塞として数々の戦乱をくぐり抜けてきたこの城はアレッポ必見の場所である。
シリアで特に感じるのは、十字軍の遠征の為に点々と距離を置いて築城された数多くの要塞があることである。一朝事態が風雲を告げたら、「のろし烽火」によって連絡をとり合えるような距離に築かれていて、それぞれが高台から高台へと切れ目なく続いているような感じであった。煙の形を変えたり、間隔にリズムを与えたりして、伝えるべき内容までもマニュアル化されていたに違いなく、詳細に伝わったのではないだろうか。
当時はローマからの伝令事項は多かったはずで、シリアに限らず途中随所にこのようなのろし烽火台があったことと推察される。古城のうち最大のものは、ホムスという町と地中海に面するタルトウスの港町との中間にある山の高台に威風堂々とそびえる「クラック・ド・シュバリエ」と呼ばれる名城である。今でも(1996年当時)その周辺は何故か知らないけれど、シリアの軍隊が警固していた。堅固なこと、重厚なこと、風景とうまく溶け合った威容は素晴らしく、規模において、中東からヨーロッパに存在する要塞として最大のもののような気がする。シリアでは必見の地である。
旅の話が前後しているがアレッポから車で40~50分も走ればトルコとの国境検問所がある。シリア兵が武装して警固していることは無論である。大型貨物トラックが50~100台と並んで税関検査を待っていた。一旦シリアを出て、アンタキア(トルコ領)まで出掛けてまた戻るつもりであったが面倒そうなので諦めて、重連の水車で名高いハマの町から地中海東端の港町ラタキア、そしてタルトウスを目指した。
タルトウスは小さな町であるが、フェニキアやローマの時代から後背地に繁茂するレバノン杉を使って軍船や商船などを作っていたアルワード島とは目と鼻の先にある。アルワード島には通船を利用して20分前後で行けるので、当然行くことにした。
アレキサンダーなどの時代に、多くの船がこの地で造船されたと聞いて歴史を追想した。船の竜骨等に使われるレバノン杉が豊富にあったことから、アレキサンダー大王やローマ帝国軍の軍船、そしてギリシャの軍船が造られたのである。その当時としては地中海世界最大(世界最大)の造船所があったと地元のチャイハネ(茶店)で聞いた。レバノン杉は、グラナダのアルハンブラ宮殿の天井の梁にも使われている。
小生は、杉のような軽くて柔らかい材質のものが、なぜ梁に使われたり船に使われたりするのかと、いぶかしく思っていたのであるが、たまたまシリアをドライブ中に、レバノン杉を大量にストックしていた製材所を通りかかり、何気なしにその原木を持ち上げてみて驚いた。重量感は日本の杉とは全く違い、ずっしりと重く、むしろマホガニーかチーク材よりもきめが細かく重いのである。成長には、ヒノキよりも更に時間が必要とされることが理解された。これなら船の竜骨に使えると思った次第である。
周囲は1時間も歩けばこと足りるこの町には、島の中心の高台をぐるりと廻る歩道があり(車は一台もない)およそ300世帯前後が住んでいるように思われた。古くからの石畳の道を歩いて見たら、まるでゴミ箱のように紙くずなどを捨ててあってうす汚くて驚いた。中には自分の門内のみをきれいに掃除してある家もあったが、とにも角にも驚いた。これとは前後するがアレッポ城へ行く道すがらでも同じような光景を見た。アレッポで最も大きいと思われる墓地を通りかかったときに、やはりゴミに埋もれたような墓地だったので、この国の貧困とくらしを知る上での参考になったと思っている。
中東はどこに行っても乾燥しているので比較的疫病が発生しないのだろうか、したがって風が吹けばそのうちゴミなど吹きとんでしまうということなのであろうか、考えさせられることであった。
この旅行の際、ダマスカスの空港で、目の不自由な子供たちを引率した日本人の団体に出会った。2時間ほど空港で飛行機待ちをしていたのであるが、よくよく見れば曽野綾子氏と三浦朱門氏が引率していて、何人かのシスター達が忙しく子供達の面倒をみていた。その時の旅はどのような経路で帰国したのか記憶があいまいになっているのだが、その後イスタンブールの空港を経由し日本に帰る機中で再びこの団体に出会い、しかも曽野・三浦両氏とは席が前後であったので声をかける機会があった。当時文化庁長官を離れて自由の身であったとはいえ、著名な作家である三浦氏と曽野氏がエコノミーシートに身をしずめて旅をしているのには感銘を受けた。ヨルダンのペトラに立ち寄ったと聞いたがエルサレムに巡礼した帰りとのことであった。
小生の近い親戚に、教育者として聖心女子学院に何十年か奉職し、20年近く教頭として美智子皇后や曽野綾子氏そして緒方貞子氏などの著名な方々を中学、高校と6年間にわたって担任した「ノサケン先生」こと野坂健三先生がいるが、その先生から色々と聞かされていたので、ついつい親近感もあって話しかけたのであった。毎年のようにハンディキャップのある子供たちを生地巡礼の旅に引率しているとのことであった。
~ 閑話休題 トルコの道路事情 ~
トルコ、シリア、レバノンは主要都市間では道路は立派に整備されているが、一歩町村道に入ると凸凹もかなりあるので高速運転は控えることが肝要である。歴史の古い地域なので道はあらゆる方面と接続している。このため道に迷っても遠回りをしてまた同じ目的地に向かうことが出来る。時間に余裕がある場合は、地図に関係なく走りながら意外性を求めるのもいいが、シリア国境やレバノン周辺などは厳戒態勢を取っているので慎重な行動をとることが必要と思われる。要所要所に頑丈な鉄のブロックがジグザグに設置されているので、どのみち速く走ることが出来ないので心配は無用である。
古くからの歴史を持つ国々は、むかし、馬車道だったと思われるような細道にその国の生活ぶりがうかがわれて面白い。新しい幹線道路沿いには近年のモータリゼーション後に作られた建物しかないので、距離と時間を稼ぎたいときだけに限定し、小さな村道などを巡れば、愉しいこと、意外なことに出会える。ただし、トルコの東国境近辺の山岳地帯は今でも山賊が出没するらしいので近づかないことが肝要である。
<エジプト雑感>
エジプトのカイロは二度訪れた。スエズの入口を見るためと、海岸にあるアレキサンドリアの町を訪問するためである。スエズを見るために、アレキサンドリアから運転手付の車をチャーターしポートサイドまで旅をした。
アレキサンドリアの街はナイルデルタによって作られた広大な平野となっており、緑豊かで他のエジプトとは全く違っている。かつてはエジプトの首都だったこともあり、それなりの気品を感じさせる街である。名前が表わすように、アレキサンダー大王によって造られた町であることは無論である。プトレマイオス王朝の最後を飾った女王として君臨したクレオパトラの活躍した都でもある。当時世界最大と言われた図書館などもあり、文化の中心的役割を果たした土地として有名である。また最近発見されて話題になったアレキサンドリアの大灯台などもあって往時の殷賑(いんしん)ぶりが忍ばれる。海浜には瀟洒なホテルが立ち並び、現在は中東のリヴィエラと言われるほどにエジプトらしからず洗練されている。
カイロはヨーロッパだけでなく、世界各国から観光客がひっきりなしに訪れる地である。日本人にはエジプトと言えばギザのピラミッドやルクソールのツタンカーメンの遺跡などが想像されて、あまりアレキサンドリアについて聞くことがないが、必見の場所であることは言うまでもない。
ピラミッドや王家の谷などエジプトの世界的に有名な内陸にある観光地についてはあえて触れない。ただエジプトについて一言触れるとすれば、ナイルデルタの街アレキサンドリアを除けば、カイロ-ルクソール-アスワンに至るエジプトはナイル川沿いに両岸の2~3キロメートルだけが緑で、それが機上から眺めればナイルを縁取るようにして南北を縦断しており、まさしくエジプトは「ナイルの賜物である」という言葉を実感させられる。ナイル川から2~3キロメートル離れれば、ほとんど全国土が炎熱によって焼けただれた赤い砂漠の国であることを知らされる。
ナイル川での川下りや、フィカールといったと思うが筏に帆をはらませてナイルを当ても無く、風に吹かれるのも風情がある。考古学に興味が無くても、ここの国立博物館は行かねばならない。想像したものよりはるかに大規模な「ツタンカーメン」の厨子など金箔の葬具には驚くだろう。ギザにあるピラミッドやスフィンクスだけでない、必見の場所が無数にある。
<チュニスの旅>
地中海全域(ティレニア海、アドリア海、エーゲ海等も含む広義の呼び方として)にわたって展開された戦乱と興亡の歴史は、東のギリシャ、ペルシャなどに始まり、フェニキアを含む今のシリアからカルタゴ、スペイン、ローマ帝国、ノルマンなど枚挙にいとまがない。更には、今のイラクのバクダッドにあったアッバース王朝の勢力争いに破れたムアーウイアの「後ウマイア朝」に関して言うならば、東地中海の端からカルタゴ、モロッコを経てスペインまで本国をのがれて西の果てまでたどりついて王朝を開いたのである。直線にして約4000キロメートルの旅を動力のない時代に、帆船いっぱいに逃亡の荷物を積み込んで西の果てマグレブまで逃れたに違いない。
もっともローマ帝国もスコットランド辺りまで版図を拡大している。イングランドとスコットランドの国境線に、今でもハドリアヌスの建設した石を積んだ壁が残っている。これより先にもはや国はないとして、ローマ帝国は、人の住む限界はここまでと自ら認めて、帝国の境界線に石塀を造ったのである。エジンバラに向かう国道幹線に、「ここよりスコットランド」と大書された標識があって、必ず目に入る。
この地域に見られる侵略したりされたりの興亡の歴史を学習すれば、複雑に絡み合っていて、単なる歴史好き位ではとても覚えきれない。小アジアを含むすべてのヨーロッパ、アラブやスラブなどが複雑に関わっていて、ややこしいし、宗教面でも、イスラムとキリスト文明との相克によって、全ての歴史が彩られていることに気づく。複雑すぎて頭が痛くなるほどである。
チュニスから車で3時間ほどの内陸に北アフリカ最古のイスラムによる古都カイルアンがある。そのカイルアンとカルタゴの遺跡を見たいと思い、マルセイユから飛行機で飛んだことがある。十字軍の遠征もそうであるが、イスラムの布教にかける情熱については、灼熱の大地を越え万里の波涛を越えて、西の果てにまで布教しつくしたそのエネルギーのすごさに驚嘆させられる。
後期ウマイヤ王朝は数千キロメートルの流浪の果てに、チュニジア(昔のカルタゴ)の内陸に営々と執念を積み上げて、ここのカイルアンを拠点にしてアルジェリアそしてモロッコのフェズ、メクネスなどに足場を固めながら、結果としてイベリア半島の全域に渡って版図を拡大したのである
話は変わって、今日の我々が、十分な可能な時間をもらったとして、東京から京都まで徒歩または馬に乗って行ってこいといわれたとしても、そんなエネルギーなど持ち合わせている人はいない。鎌倉や江戸時代の人達は、これらの距離をひんぱんに往来していたのであり、それを考えただけで、人間のエネルギーのすごさを感じる。しかし、この地中海世界を巡る覇権の争奪戦に見られる、長駆往来のスケールは、ケタ違いなのである。生き延びなければならない本能と、他を勢力下に置きたいとする野望と、それに加えて宗教心による伝導の執念なのか。このようなことを考えると、血を流したりして命の保証のない遠征をあえてする人間というものの、原始的力強さに驚かされる。
最近はインターネットだ、Iモードだ、ITだといって、情報通信による社会革命と呼ばれる文明が全盛であるが、それは利便の問題であって、人間の生活の基本に絶対になくてはならないというものでもない。電話回線を使って荷物を運べるものではないし、キーを打っても、三度三度の空腹は満たされない。一次産品の生産がなければ人間生活は営めない。コンピューターのもつ意味と暮らしに与えてくれた利便の良さは、まさしくたいへんに大きく意義のある革命と呼べるものであり、これからはこの文明の利器を使いこなしていかないことには、時代に取り残されてしまうであろう。しかしこれらは人間の幸不幸とかあり方とは別な観点で考えるべき事柄なのである。
歴史の興亡の中でのそれぞれの民族が命を懸けた行動は、たとえそれが余儀なく強制されたとしても、苦しみが深ければ喜びは更に大きく、そのような喜怒哀楽に満ち満ちた世界に思いを馳せるのも悪くはない。
さて、イラクのバグダッドは一度訪ねたいと思っているが、未だ機会がなく(危険であり)訪れてはいない。ここはチグリス・ユーフラテス文明発祥の地である。二千数百年にわたって繁栄を続け、紀元前500年にペルシャに亡ぼされたと書物に書いてある。その後8世紀にアッバース朝イスラム国家がバグダッドに都を定めたらしい。
問題はその先であるが、バグダッドに建てたアッバース朝とシリアのダマスカスに都を定めてモンゴルに亡ぼされたウマイヤ王朝のカリフの末裔との間に、スンニー派とシーア派の意見対立があったのだ。何かの書物で読んだが、敗れ去ったウマイヤ王朝の生き残りの人達が追われ追われて、辛苦の果てに、このチュニジアのカイルアンに拠点を造り、ベルベルの人達を教化しながら、ついにはイベリア半島全域を勢力下に置いて、今のスペインのコルドバやグラナダにウマイヤの望郷が伝わってくるようなイスラム文化の都を造ったのである。
後期ウマイヤ王朝によるイスラム文化の普及、伝導は、地中海世界ほぼ全体に達するほどで、このことを抜きにしては、語り尽くすことは不可能である。これらの影響力からすれば、ナポレオンがどうだとか言っても、比較のできぬほどの影響を後世に残している。
チュニジアは観光立国である。カルタゴの歴史を別にすれば、地中海に面する海岸線は、なだらかな平原が広がりを見せており、オレンジ、デーツ、アーモンド、いちじく、そしてオリーブの畑が延々と南北にのびる、比較的豊かな土地柄である。長い海岸線には、近代的な設備を持ったホテルを始めとして、フランス、ドイツなどからの観光客用のリゾートが無数にある。北アフリカの中では格別に治安も良く、こぎれいな町並みは一瞬フランスの田舎町を感じさせるが、庶民的なリゾート地であることも好まれて、物価なども安く、四季を問わず、バカンス客が多い。気候や海の青さについては、地中海世界一番と言えるかも知れない。
日本からグァムやサイパンに出かけるような感覚で、フランスから観光客が来ているようである。このチュニスからシチリアの西部にあるトラパニという町にはフェリーに乗れば8時間で行けるので、ここからイタリアのトラパニに渡ってもいいかもしれない。
<アルジェリア>
この辺りを表現する言葉には、地の果て、あるいは太陽の沈む国を意味するマグレブがある。日本では「ここは地の果てアルジェリア、どうせカスバの夜に咲く....」という歌で知られている。
モロッコと似たような地形を持つアルジェリアには、モロッコのフェズから2泊の予定で現地ガイドを連れて出掛けたことがあった。アルジェの町へ行く途中で、オンボロ車がオーバーヒートして不調になり引き返したことがある。その間、車の整備を兼ねて、オランに一泊したが、何か潤いのない、ぎすぎすしたような感じがあって、あまり好印象は持たなかった。
この国は、一時、フランスの一部とさせられた歴史が近年にあり、フランス風の優しい表情があって柔らかなのではと思っていたのだが、町で受けた印象は決して良くはなかった。アルジェリアの民族解放戦争で心まで傷められたのであろうか。とにかく失業者が非常に多いという印象を受けた。
オランの町は、古い歴史を持つ人口約30万人の町である。石油化学の工場があり、その他に軽工業も発達していて、新旧の対照的な雰囲気、カオスを感じさせるものがあって、落ち着かないのかもしれない。それに拍車をかけるように港町特有のざわめきも加わるので、殺伐とした雰囲気が漂うのもやむを得ないだろう。小生はトルコやモロッコの国が大好きで、これらの国は数日間、車であちこちと泊まり歩き、かなり見聞しているのであるが、アルジェリア人の印象はまるで違う。アルジェリア人の性格気質には多少いらいらした思いがある。
滞在中、うす汚いホテルしかとれなかったが、夕食をとったフランス料理屋のギャルソンから、ここはスリやかっぱらいが特別多いから気をつけるようにとも聞かされた。車が不調になったり、宿が汚かったり、そして、今度は町でも一番良さそうなフランス料理屋に行ったら、今度はかっぱらいに気をつけろと言われ、そんなこんなで良い印象を持てなくなったのであろう。
現在はチュニジアも含めて、このマグレブ3国には、一応足を入れているので、少しは比較できるため簡単な印象を述べる。チュニジアは北アフリカでも一番こぎれいで、さっぱりしていて、フランス風の町並みやホテル設備もまあまあのような感じであるが、アルジェリアは、少しぎすぎすして、住民の目つきもきつくて、安らげない感じだ。フランスの統治にあった国はどこも町や人の表情に優しさと柔らかさがにじみ出て、しゃれているはずだと予想していたのだが、町も汚く貧しさが感じられた。
ただしモロッコは違う、アルジェリアとは気候や大地の形質は似ているのだが、旅行者にとって限りなく魅力ある土地である。チュニジアはリゾート開発が国の重要な政策のひとつに位置づけされているので居心地が良いのはもっともであるが、モロッコの場合は、アルジェリアと違って、比較的他国の侵略が緩やかなものであったからではないだろうか。王政が維持されており、またイスラムの教育も徹底されているが、アルジェリアではアルジェリア戦争が近年にあり、社会主義的政策が採られていたことで、その違いが出ているような気がする。
<マグレブ(地の果て)モロッコの印象>
モロッコへは外人部隊やカサブランカの映画に影響されて憧れていたこともあって、地中海沿岸の国々の中ではもっとも早くから行き始め、旅行先としては大好きな国である。
初めてモロッコを訪れたのは20代前半の頃で、ニューヨークからリスボンに立ち寄って深夜に到着した。そのときに窓外から眺めた星空の輝きは今でもはっきり覚えている。カサブランカの空港はバラック風の小さな空港で、漆黒の闇の中にいるような気がしたものだった。早速タクシーに乗ってホテル・カサブランカに乗り付けたが、タクシー料金のことで一悶着があった。後でわかったのだが、運転手が請求した金額が現地通貨のディラハムであったのに対し、アメリカに長期間滞在して日本への帰途にあった身で、それをドルと間違えて聞いたのであった。ふざけるんじゃないと思う気持ちで言い合いになったのだが、むこうは、英語がほとんどできず、フランス語で話すので、らちがあかず、すったもんだの揚げ句に、ホテルのフロントまで行って仲裁してもらった。原因が単純なことだったので、お互いになんだそんなことだったか、というわけで、握手してチップをはずんで別れたのであった。そのとき以来、スペインやポルトガルなどに行ったとき、時間を作って時折モロッコに出かけることになるのである。
カサブランカで初めて日の出とともに始まるコーランの読経すなわちアッザーンを聞いたときは、何とも言えない感銘を受けて、エトランゼになれたような気がした。当時のホテル・カサブランカは今のカサブランカ・ハイヤットリージェンシーとは違い、現在、ホテル正面脇に再現された名画「カサブランカ」を再現する「バー・カサブランカ」はなかったし、リージェンシー系列ではなかったように思うが、当時としてもカサブランカ一の最高級ホテルであることは同じであった。
初めてカサブランカを訪れた翌朝のことである。ホテル・カサブランカの裏手の方には、バラックの店が建ち並び、ほとんどの女性がベールで顔を隠し、長いコート風の上着に身体を隠し、顔や手など衣類からはみ出した部分は、いろいろな図柄を思わせる刺繍にも似た入れ墨(後から知ったが、ヘンナという染料で描くようだ)をほどこして、ぞろぞろと歩いている雰囲気には少し驚いた。
男性は、もちろんジェラバと呼ばれるドンゴロスのようなフードつきの上着をまとっている。ほとんど日本人観光客などいないその当時、その中に身を置いたときの気分は、不気味で少し緊張したことを、しっかりおぼえている。英語は通じないし、心細いものがあって、気の弱い人物なら泣き出すことになるのではないかと思ったものである。今では、いろいろな旅行記やガイドブックが充実していて、そんなに驚くことはなくなっているが、旅慣れた身であったとしても、イスラムの異質な空間に初めて身を置いた時の印象はそのようなものであった。
前述の女性の化粧についてであるが、ヘンナで化粧したというか、入れ墨風なものを施した女性達は、貞節で信仰心の篤い人達だということを後日知った。これは2度目に訪問したとき、内陸深く知りたいと、マラケシで雇い入れた車持ち込みガイド兼運転手から、1週間にわたる旅行中に聞いた様々な話の中のひとつである。婦人は家族や、夫以外に自分の肌を見せてはいけないそうで、したがって、袖からはみ出す手首や足首の部分、チャドル(ヴェール)からはみ出す顔面の部分に、できるだけ入念に、刺繍状の絵模様を施すことが、信仰心の証として尊敬されているとのことである。
場合によっては顔面を隠すために、更に頭から真っ黒いレースのベールをかけて、どちらが前後かわからないように装った人達も結構見受けられた。2001年の秋に発生したアフガニスタンがらみの事件でパキスタンやアフガンが頻繁に映像として放送され、今では珍しくはなくなったが。御婦人方が頭からすっぽり身にまとうものを現地ではブルカと呼ぶらしい。同じイスラムの世界でもマグレブと呼ばれるモロッコ、アルジェリア、チェニジアやシリアやヨルダンなどの中東そしてイランやアフガニスタンなどを一つの区切りにして呼称の違いが見られるようだ。たとえばバザール、スーク、メディナは同じ意味の言葉である。
初のモロッコの旅では、そのような光景があまりに珍しく、うっかりカメラを向けてしまって大声で怒鳴られたものである。トルコなど近代化されたイスラムの世界は別だが、他の保守的な国のイスラム諸国では、無造作に写真を撮ったりしてはいけない。このことは、たとえ観光客であっても、ノースリーブなど肌を露出する服装は慎むべきだということにも通じるのである。それでもこの10年ほどの間にはそれなりの意識変化が見えて、徐々に欧米的文化が受け入れやすくなってきているようだ。TVやインターネットとかの普及によるものもあるのかもしれない。
カサブランカやマラケシュなどのモロッコの南の部分は一部のオアシスをのぞいて、ほとんど赤茶色の土壌に石ころが無数に混じり、およそ農耕は不可能と思われるが、早春には砂漠ではない土漠にタンポポやポピーや無数の野の花が咲き乱れ、遠くから眺めればとても美しい景色である。
一方で、首都の置かれているラバトやメクネス、フェズからタンジールに至る北側の地域の大半は、色濃い緑に覆われていて、この国が農業国であることを知るのである。雨はほとんど降らないのだが、アトラス山脈などの雪解け水が伏流水となって流れ出しているに違いない。
<パリ・ダカ・ラリーとカサブランカまで併走>
パリ・ダカールのラリー出場者に混じって、ステージ以外の一般公道を移動する際に、カサブランカまで約500キロメートルにおよぶドライブをした時のことである。スペインのアルヘシーラスからフェリーで対岸のモロッコのタンジールに向かう船中で、ラリーは今夜、タンジールに泊まり、翌朝、港の前からカサブランカに行くとの情報を得たので、タンジールに宿を取って翌朝に備えた。ところが、後続の便で来たカミオン(トラック)、セダン、オートバイのラリー群が、港に着くやいなや、けたたましい排気音をたてながら大集団でタンジールの町を抜けていったのである。慌てて、アフリカステージのスタートはタンジールではないのかと再確認すると、スタートはラバト(首都王宮のある)で明朝8時であるとの返事を得て、翌早朝の3時半に起きるとラバトまでの300キロメートルの道のりをスタートに合わせて激走したというわけだ。
この話題に触れるのには理由がある。タンジールからマラケシュの間はなだらかな起伏のある単調な山坂を幾度も超えていくのだが、早朝の300キロメートルに及ぶドライブは、ものすごく深い霧というか朝靄の中を走ることになった。早朝には年中このようなことがあって、天の雨に頼らなくてもこの霧によって作物が守られているとの話を後で知ったのである。時速100Km前後で20~50メートル先しか見えない片側一車線の道を、絶えず事故の危険を感じながら、センターラインの白いラインだけをたよりに3時間走り通したのも、パリダカのスタートに合わせるために必死だったのである。とにかく、この時のモロッコの朝霧には悩まされた。ドライバーは以前レーシングドライバーを志したこともあるフリーターの青年だった。首都のラバトからマラケシ(マラケッシュ)に至る間には北アフリカには珍しく高速自動車道が通っていた。
話は変わるが、このときは自分の1回のドライブ旅行としての走行距離は最高で、シリア、トルコを経てヨルダン国境で車を返却し、改めてリヴィエラをはじめとする地中海沿岸都市をスペインのアルヘシーラスまで行き、さらにカサブランカからフェズに抜けて、スペイン南北を縦断し、ボルドーからクレルモン、リヨン、雪のシャモニーを抜けてミュンヘンまで、7ヶ国を約7000キロメートル駆け巡ったのである。まさに本書のタイトルのごとく「地中海を駆ける」旅であった。
今は60歳になり、このような強行軍の旅をする気にはなれないが、10年前まではこれ位は平気であった。仕事の関係もあって、イタリア、プロヴァンス、スペインの海岸線2000キロメートル前後の間は何度もドライブしている。主要幹線に出たり入ったり、田舎道を走ったりして、この間の事情にはかなり明るいつもりでいる。旧ユーゴの南やアルバニアそしてリビアやアルジェリアの海岸線は連続しての走破はしてないものの、特徴的な場所をピックアップしながら、部分的に旅をしている。トルコに関しても、ある程度の距離を走っている。
そして、このモロッコに関しても、タンジールから南端に近いアガディール(イワシの水揚げでは有名な港であり、ビーチのリゾートも南仏のように素晴らしく整備され、モロッコ随一の海洋リゾートである)を通り、アトラスを越えてワルザザートまでと、カサブランカ、フェズ、タンジールを何度か走っているので、かなりのモロッコ通を自負している。
モロッコの王宮や行政府のあるラバトの周辺は豊かな大地で、モロッコ全土を支えるに足る生産量を誇っていると書いたが、農産物の種類は他の地中海世界とほぼ同じである。ただ、この地域の圃場は非常に良く整備されていて、各農場の周辺にはオリーブ林やコルク樫の木やユーカリの大木が林を形成したり、街路樹となったりして、ドライブしていても心安らぐのである。深夜から早朝のあの霧や朝靄の賜物なのであろう。またメクネスにはローマ時代の植民都市ホリビュルスがあり、地中海の東の果て、シリアに起源を持つ後ウマイヤ王朝の氏族によるイドリス朝の古都ムーレイイドリスなどの町があって、それらを思う時、「つわものども」の夢の跡を思わずにいられない。
南の港湾都市アガディール周辺は、日本で消費されているオイルサーディンの7割近くを供給している水産加工業の発達した町である。アガディールブルーとも言える表現しきれないほどの、大西洋の海の碧さは生涯忘れ得ぬものである。
地中海とは単にイタリアまでの海ではない。ティレニア海、アドリア海、エーゲ海をも含んで広義に地中海と称するのであって、その総面積はロシアをのぞくヨーロッパがすっぽり入るくらいの大きい海なのである。
この海域は、位置的にイタリアを挟んで、東に西に、南に北に、およそギリシャ、フェニキアから始まる4000年強の興亡の歴史があり、尽きることのないロマンを満たしてくれる。ポエニ戦争のハンニバル、ペルシャ戦争のダリウス王、シーザーとアントニウスとクレオパトラ、アレキサンダーの遠征があり、近世にはエジプト遠征における兵士を前にして「4000年の歴史が諸君を見ている」と激励したナポレオンがいる。
ワルザザートというサハラ砂漠の玄関のひとつとも言える小さな町がある。マラケシュからアトラスの山越えをして、サハラの入口に入るのだが、荒涼とした乾燥しきった赤土の町は我々砂漠を知らないものにとっては、極めて印象深いものである。ここから南へ、そしてカスバ(要塞の町)街道の先エルフードから南へと、サハラ砂漠は果てしなく続くのである。
30代前半の頃、マラケシュで言葉が通じないので、数カ国語に堪能で親切なブラッヒム・アガザンという当時20代中頃の敬虔なイスラム教徒の青年ガイドを雇って旅をしたことがある。今でもアラブの国を車で旅をすることになるとガイドが必要であるが、その理由は簡単である。まずは、奥地に入るほどに英語が通じなくなるからである。以前は日本人観光客などいなくて、日本人という民族を知らない人が多く、必ずシノワが来た(シノワ=中国人)と声をかけられたものである。その他に大きい理由としては、道路標識が全く不備で、あった場合でもアラビア語しか表記されていないからである。
宿や食事については、最悪の場合は、身体に新聞紙を巻いて、パンをかじっていれば何とかなるのだが、この広大な土漠や砂漠に迷い込んだらと思うと、ガイドに頼らざるを得ない。幹線からはずれれば、地図などは当てにはできないのである。
パンをかじるというと思い出すことがある。以前マラケッシュからフェズに向かうドライブの途中で、ドライブインらしき場所をみつけて入ってみたのだが、メニューもなく粗末な食卓に腰掛けて注文をして待つ間キッチンの状態を見て驚いたことがある。ドロドロして汚れた、わずかばかりの水で皿や鍋などを洗い、まだ汚れが落ちていないギトギトした皿をそのまま使用しているのである。そのためいっぺんに食欲をなくし、食べることなくそこを立ち去ったのだが、その後行けども行けども人家まばらなドライブルートでは食べ物にあり付けず、途中でベドウィンのテントに駆け込んでパンを分けてもらったというわけだ。その時焼いてくれたラクダの脂身のサンドイッチは今思い出しても格別のものであった。
北アフリカはインドや東南アジアなどと比べて湿度が高くないので、皿や鍋釜をきれいに洗わなくてもそれほど不潔に思うことはないのだが、以後この地域の地方を旅をするときはインスタントやレトルト食品を携帯することが多くなった。もっともこれにはもう一つの理由があって、どうも小生にはアラブ料理に多用されるクミンやターメリックの香辛料があまりにもきつくて口に合わないのだ。
フランスの植民地支配を受けたモロッコなどの観光地には、パリの一流店にも劣らない味覚を持ったレストランもあり、むしろフランス料理を食べるためだけの理由でもモロッコに出かけたいと思わせるものがある。しかし、それはカサブランカやアガディール、マラケッシュやフェズといった国際的に知られた場所に限られており、小さな町や村での状態はまったく違う。先述の調理場の洗いものについて考えれば、日本のように水をジャブジャブ使える国こそが珍しいのであり、このことは北アフリカ諸国やトルコ、ギリシャ、スペインにしてもてある程度共通しているように思える。
以前、ベニメラルという小さな町に宿を取って、その夜星空を見るために町を歩いていたら、いたいけな子供が手を振って呼んでいるのに出会ったことがある。その子が小生の手を引いていくので、ついていくと、30前後と思われるベルベル人の婦人がおり、1ドル恵んでくれと言うのであった。何のことはない。1ドルで売春を申し込まれたのである。自分の娘が母親に頼まれて客引きをしていたのであった。ようするにとても貧しい原始的な暮らしぶりがこの地方では珍しくは無かったのである。ホテル・カサブランカは当時一泊30米ドル位であったのでこれを参考までに書いておく。
この話には後日談があって、帰路カサブランカに出て、1~2泊した折りに町を散歩していたら、日本人を見かけた。珍しいことだと思い声をかけたら、海外協力隊の隊員でカサブランカにオートバイの修理を教えるために2年ほど滞在している人であった。当時カサブランカに日本人の観光客が訪れることは珍しく、お互いに話が弾んで、午後に、すすめられるままに、彼の宿舎を訪ねたのだが、3DKほどの広さの所に5~6人の海外協力隊の方々が畳を敷いて共同生活をしていた。情報収集のこともあり、ビールを飲みながら、いろいろな話をした。先に述べたようなことも話題のひとつになった。ペルーやパキスタンを回ってカサブランカに滞在中のその青年は、「1ドルの言い値は安くない。自分はワルザザートの近郊のカスバで日本円50円を支払って一夜を過ごした」と言ったのである。その時の青年の顔を今でもかすかに覚えている。
砂漠や土漠を旅していて、誰もいないと思われるだだっぴろい大地で、どこからともなく人が湧き出てくること……には驚かされた。砂漠や土漠のなかで、車から降りて小用を足すときが何度かあったが、その途端、どこをみても一望千里の土砂漠の中から、忽然と人がわきあがってくるのである「湧き出てくる」という形容がぴったりなのだ。後で知るのだが、彼らは隣のベドウィンやベルベル人同志のテントに移るとき、そしてその他の目的で徒歩の旅をするとき、土漠の最短距離のルート上や、バス停などでいつ到着するか時間の定まらないバスを待ちながら、土色の麻袋のようなジェラバという着衣をすっぽりかぶって、フードで頭を隠し、あちこちに寝ころんでいるのである。
ベルベル人は、Berbergia(バルバジア) と呼ばれ、「barbarian=野蛮人」の語源にもなっているようだが、その他にベルベルとは物音がしない、静寂という意味があると何かの本で読んだことがある。彼らのとぎすまされた聴力や視力は、車の音や異邦人の動きを一瞬にして識別できるのであろう。しかも大地から湧き上がるように忽然として現れるのである。これは砂漠を旅しながら眺めた、夜空の降るような星とともに忘れることのない印象を与えてくれた。虚飾が無く夜空の星を眺めながら、少ない物資を上手に生活に活かして暮らしているベドウィンの遊牧の民は、どこかもっと深遠な人生哲学に基づいて毅然として人生に立ち向かっているかのような印象を受けた。
旅をするたびに奇異に思うことや、生活習慣の違いによる珍しい習慣に出くわすことがあるが、それらは、それぞれの風土の中で、無駄のない合理性に裏打ちされた結果なのである。まず、それをおかしいとかではなくて、どうしてそうなのかという風に考えていけば、納得がいくのである。旅をすることは、民族の壁を越えて共生することが大事だという多くの教訓を得ることにつながると言えよう。
<古都フェズとマラケシュ(ムラビト王朝)について>
マラケシュには、車でたどり着いても、バスでCTMと呼ばれるバスターミナルに着いても、この町はメディナ(旧市街)と呼ばれる中世からの周囲の城壁で囲まれた(周囲約20キロメートル)アラビアンナイトの時代をそのまま彷彿させられるような正面入口に到着する。そこジェイマル・フナ(ジャンマールフナ=直訳すれば死者の広場と呼ぶらしい)には異種多様なアラブの世界らしきものが中世そのままに残っており、風情に満ち満ちたカオスがそこには存在する。メディナの中は、完全にマラケシュ市民の生活の場であり、ここにはおよそ30万人が暮らしている。無数の工房や、商店がひしめいており、この広場は、フェズにも見かけることもない、世にも珍しい独特な雰囲気である。中世から祭りや集会などもあったりして多目的に使われたらしいが、イスラムの戒律を破った犯罪者の首をはねたりした処刑場があったことから、死者の広場と呼ばれているらしい。もちろん市場も兼ねていて、各地から集まったあらゆる産物の交易場所であったことは言うまでもない。
ここで最初に目につくのは、スーダン帽などを被った黒人のアクロバットである。その他にも羊の皮袋につまった水を売る水売り商人がいる。蛇使いがインドよろしく笛を吹いている。占い師が何事か判らぬが、水晶玉やカードなどで占いをしたりしている。各種のアクセサリーが山と積まれてもいる。それがジェイマル・フナの風景である。サハラなどから交易をしながら、ここの交易市場、メディナのうちにあるスーク(バザール)で物資を調達していくのでもあろう。遠くサハラを越えて、モーリタニア周辺からも人がやって来る。
ベドゥイン達も遊牧しながら、羊毛や皮製品や、乳製品なども持ち込んで交易をしていることだろう。とにもかくにも騒然とした混沌の中に恐ろしく活気があって、まるで生きる力を与えられるような気になるのだ。一切の虚飾や遠慮のない真剣な、それぞれの生き様の原点を見る気持ちにもさせられる。
メディナすなわちスークの中は、まるでアラビアンナイトの時代のように人間臭さに満ちている。暮らしをつなぐ通路の天井は、葦のようなもので葺いてあって、そこから光が射し込むときにできる、光と陰のコントラストは印象的である。買い物をするにあたって、価格の交渉も又、限りなく楽しい。これは乾燥した大地に暮らしているイスラムの民に共通しているのだが、物価はあって無きに等しい。すべての取引は相対で値決めがされる。したがって、とりあえず提示される価格の半値などは当たり前で、交渉しだいで3分の1になったり、5分の1になったりする。不合理といえばこれ以上不合理なことはないのだが、延々と値段交渉の駆け引きをすることになる。場合によっては、百円値切るのに1時間とかの時間を費やすのである。旅行者にとってみれば航空運賃や滞在費用、そして休暇をとっているとはいえ、それぞれの時間給を計算したら、百円や千円ぐらいどうでも良い筈なのだが、真剣になって百円でも安くしようとする、その駆け引きが、また楽しいのである。ばかげていると言うならその通りだが、そのような掛け合いの中にこそ、旅の喜びや楽しみがある。無人に近いスーパーマーケットなどでの買い物の便利さはこの上ないが、物を売り買いするという行為そのものの点で、これほどつまらないものはないだろう。たとえ、時間的なコストが高くつくとしても人間らしくて面白いのである。商いとは何なのかを知ることができ、合理性のみの中で価値規範を求めてきた我々西洋社会との違いを考えさせられることは多い。
何故にイスラムの生活は、このような商習慣になっているのかと考えたことがある。大きく分けて考えると、マホメットの教えの中で、持てるものは持たざる者に喜捨をすべしとの教えがある。このことによって、売り手は相手の顔や表情を見ながら、おまえは金持ちだから少しぐらい小生に恵んでくれ、というのであり、貧しい人には、そんなに必要なら原価を割ってでも分けてやる、といういわゆるザカート(喜捨)の精神が少なからず存在するのであろう。
彼らの起源が砂漠の民である以上、物価の決め手になるものは商品の製造コストだけではなく、必要性によって値決めをせざるをえなかったということにも起因するだろう。たとえば、ここに百億円の資産を持つ金持ちがいるとしよう。彼は砂漠の中を旅して、道に迷い、その結果一杯の水がなければ間違いなく死ぬであろう局面になったとき、そこに羊飼いの貧しい少年が充分に水を持ち合わせていたら、どのような商談になるのであろうか。水はオアシスから汲んできたものであり、原価はタダだったはずである。しかし、その少年が商才に長けていたとすれば、どうであろう。その水を分けてもらえば結果的に命は助かるわけで、大金持ちは限りなく百億に近い金を出したとしても、それを買うに違いない。極言すればそういうことになるのだ。
全ての取引の値踏みはこのような状態の中から慣習として培われ、現在に至っているのではないだろうか。アラブ商人のしたたかさは、このようにして養われたものであろう。OPECの取り決めなどが原因で、石油不足という事態になった場合は、オレはアラブの世界に顔が利くから、または親しい友人がいるからといって、自分が出かけて行けば石油を安く分けてもらえると安易に考えるなら、向こう側は、おまえは友達だから他よりも高い値段で買ってくれ、と言うに違いない。そのくらい、我々日本人とはあらゆる面において違いが散見されるのである。
この地域の人々は困窮しているような生活をしている人であっても、決して卑しさを感じさせない毅然とした表情をしている。バクシーシ、即ち、施しをくれと言っても堂々として悪びれる風はない。無い者が有る者から施しを受けることは当然であって、それが神の意志、すなわちインシャッラーであると、生来理解しているからであろう。言い過ぎであることは承知しているが、喜捨をする機会を与えていることに感謝でもしろと思っているのかも知れない。
話は変わって、マラケシュのメディナからほど近いところには、ムラビト王朝の遺跡が立派に残っていて素晴らしく印象的であるが、何よりも記憶に鮮明に残るのは、王族のため砂漠に造られた人工池である。300メートル四方もあるかとおもわれるプールがあり、その昔は飲料水としての利用はもちろん、船遊びなども楽しんでいたらしい。雨のほとんど降らないこのような場所だからこそ、アトラスの山から導水してこのような池を造っていたのであろう。発電や農耕のためではない舟遊びのプールとしては最大クラスのものであろう、なんと贅沢なことか。もちろん、モザイクで装飾された王宮や、その他の建造物は当然のように素晴らしく美しい。歩くのもよし、観光馬車に乗って優雅に愉しむのも良しである。
マラケシュの新市街は、近代建築がにょきにょき立っているイスタンブールのタキシム地区などとは違って、上手にイスラムの古都の雰囲気にとけ込むようにデザインされた優雅な市街地である。ここには欧米の一流ホテルが緑の中にイスラム様式美で装飾され点在しており、フランスの保護領だったこともあって、フランス料理はパリに引けを取らないほどの内容である。GATTの国際会議もここで開かれたことがあるが当然であろう。
<フェズのメディナ(スーク・バザール)>
メディナだけを見るなら、アラブ世界、すなわち世界のメディナ(バザール)の中で、フェズが突出している。
その規模において、その迷路の複雑さにおいて、そして優雅さと活気において、感嘆する内容と気品を備えたものである。メディナの中には数十万人の人達がマラケシュと同じように生活している。無数の坂道と路地がメディナの中を交差し、外周はいざ知らず中に入れば車の一台も通っていない。タクシーはロバのタクシーである。全ての物資の輸送とてまた然りである。中世に完全にタイムスリップしたような感じは、歩けば歩くほど強くなる。
ここのメディナのなかに迷い込んだら、ガイドなしには一生かかっても出てこられないと言うが、あながち誇張ではないだろう。ここのメディナ(イランではバザールといい他のイスラムではスークという)について物語を書こうとすれば、それだけで何冊かの本でもできるに違いない。
需要と供給は良くしたもので、メディナの入口周辺ではガイドが国家の認定バッジをつけて、無数に待ちかまえているので選ぶのにひと苦労するほどである。あるときは、メディナに向かう途中、市街地の何キロも手前の方からオートバイに乗って、小生の車を追いかけてきて、赤信号の都度にガイドを売り込んできた者があった。しつこくて振り切るのに苦労した。後から考えてみれば、彼は家族を扶養するために実に一生懸命仕事をしていたに違いないのである。ウルサイと思い、追い払うのに多少乱暴な言葉を用いた自分を今は恥じている。
マラケシュのメディナの方が少し優雅で幻想的ではあるが、フェズの方がダイレクトに生活感が伝わってくる。ここはまたイスラム世界における学問や芸術をもリードする知的な町である。イスラムのモザイクタイルによる装飾芸術をより高めたフェズは、モザイクタイルの町としても世界的に有名である。グラナダのアルハンブラ宮殿であろうと、セビーリャのアルカサールであろうと、フェズの職人無しにはその装飾が完成しなかったのであろうと思われる。また、ここはダビデの星のマークを家に取り付けているユダヤ人の多いことでも知られている。
日本の時代に照らし合わせてみると、日本の大和朝廷の頃からイスラムのアラブは、フェズやチュニジアのカイルアン、そしてコルドバを通じて、その頃未開であったヨーロッパに医学、化学、天文学等の自然科学分野で大きな影響を与えたのである。それは、今の西欧とイスラムの世界がまさに逆転したかのような関係であったのだ。
現代文明において安易な合理性や利便性を追求することで人間性を失いつつある我々は、この伝統的生き方を続けているイスラムの文化には学ぶことが多いような気がしている。
~ 閑話休題 現代と中世と ~
小生の海外経験は、20代前半のアメリカ留学(オレゴン州立大学ポートランド校)に端を発しており、英語での授業を受けながら、勉強にあまり集中できないときなどに、旅行をして見聞を広めようとしたことにある。当時アメリカにあった(今でもあるのかも知れない)米商務省の後援する21 days no limited travel ticketという21日間アメリカ中の飛行機を無制限に使えるという、鉄道旅行で利用するユーレイルパスのようなものがあった。当時1ドル360円の時に、日本円で4万円強だったと思うが、これを利用して機中泊をしたり、機内食に合わせて食費を浮かせたり、北から南、東から西へと飛行機を何度も乗り換えて旅行を始めたのである。
以来、空港でレンタカーを使うことに慣れてきて、よほどのことがない限り、空港に着くなりレンタカーを借りて旅をするということが小生の旅のスタイルなってきている。
そのようなわけで、アメリカも良く旅行して知っているが、地中海というこの領域は、そのアメリカと比べて、はるかに大きいのである。単に土地面積のことを言っているのではなく、歴史上の異質な文化を横断することにおいて、また人類の文化の起源であるエジプト、ギリシャ、メソポタミアなどを広く含有していることにおいて、アメリカとはとうてい比較にならない奥深さと味わいを持っていて、そのような意味で大きく広いのである。
アメリカを旅した後、フランスやイギリス、ドイツといったいわゆる先進国の状況を知りたくて、暇さえあれば会社の経営を誰かに任せて旅をしていた。ヨーロッパへ行き始めた当初は、スペインとかイタリアに足を伸ばすことはあまりなかったが、何度もヨーロッパに足を運ぶうちに、スペイン、イタリアを旅するようになり、その生活の楽しさや気軽さ、そして、知れば知るほどますます歴史の奥深さに興味が湧くようになった。
人生の楽しみ方を知っており、豊かな食生活を享受しているラテンの諸国の方が、視察や研修とかでない、いわゆる自由な旅の行き先としては、圧倒的に魅力があるように思われる。太陽の恵みはもちろんのこと、旅の楽しみには、美しい風光を愛で、豊かな食事と美味しいワインを愉しむことも含まれる。しかし、これだけでは決して充分ではない。歴史についての奥深い味わいを楽しめるその場に身を置くこと、これこそが旅の醍醐味と言えよう。崩れかけた細い路地などは絵画のモチーフになりやすいが、機能だけを重視した現代の超高層ビルなどの絵は絵画として鑑賞に堪えられるであろうか。安いが見栄えが良いだけの建築資材を使って、表層のみをこぎれいにした建物などに、安らぎをおぼえるであろうか。そうはいっても、東京などのようなテンポの速い変化するような都市にあっては、利便さが第一になりやすいこともやむを得ない。無機質な生活を送らざるを得ない場合もある。それに逆らうことは難しい場合が多い。そのように都市生活が近代化されるほどに、人々はなんらかの安らぎを求めて旅に出ることになるのだろう。本書で書き綴る地中海沿岸州の歴史と現状等は、これらのことを充分に満たしてくれると確信する。