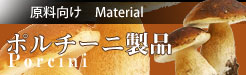8. 地中海における興亡の歴史について
地中海における戦争の歴史ほど世界史上に強く影響を及ぼしたものはないであろう。古くはペルシャの遠征によるペルシャ戦争、いわゆるサラミス・ミレトスの海戦があり、スパルタとアテネの間のペロポネソス戦争、名将ハンニバルによるローマとのポエニ戦争もまた数次にわたる大戦であった。ポエニ戦争は、現在のチュニジアのカルタゴから象の大群を引き連れ、スペイン、プロヴァンスを経て、アルプス越えまでした大掛かりな戦争であった。その後、ハンニバルのカルタゴを破ったローマが興隆し、その版図は、北はイングランドの北部、スコットランドに至るまで拡大された。
当然のこととして、そこに至るルート上にあるカルタゴやモロッコに植民地を築き、対岸のプロヴァンスやスペインを拠点にしながら、各地の重要地点を制圧していった。通信や交通手段が人馬によるしかない時代であることを考えれば、人間の飽くなき拡大精神には驚嘆させられる。さらにはローマとササン朝ペルシャとの数限りない東地中海における抗争の歴史が続き、時代が下がって、ローマからイスタンブール(当時のコンスタンチノープル)に政権の中心が移るまでは各地で小競り合いが絶えることがなかった。
その頃ダマスカスに都を置いたウマイヤ朝も今のシリアからイベリア半島まで侵略している。アブドラ・ラーマン二世の時に、後ウマイヤ朝が本国を追われ北アフリカを西端まで逃れ、さらにはスペインのほぼ全土を占領した歴史も、世界史上に大きな影響を与えた。
十字軍がイタリアのプーリア州にあるバーリやブリンディシから、フランスからの修道騎士を乗せてエルサレムへの聖地巡礼に旅立ったのもその頃であったはずだが、十字軍の遠征自体、聖地巡礼に名をかりたキリスト教のイスラムに対する侵略戦争と見てとれなくもない。各地でキリスト教徒による略奪も頻繁に行われ、そこに、それを迎え撃つイスラム側の英雄サラディンが登場するのである。
戦争ほど残酷で無意味なものも無いように思えるが、戦時に活躍した英雄たちの生き様の中には限りない感動があって、血が沸き立つほどのロマンを感ずるのは何故だろうか。
ヴァイキング等、ノルマン人が今のフランス、ノルマンディー地方に拠点を作り、はるばる地中海にまで侵略し、その結果として、シチリアにノルマン文化の栄華を築いたのも10世紀前後である。その後も延々と興亡の歴史は続くことになる。
メフメット2世によるコンスタンチノープルの落城、そしてイスタンブールの歴史が更に重なる。これから先の地中海ではイスタンブールに拠点を置くビザンチン帝国の圧倒的な制圧の歴史と、ビザンチンと競合共生しながら自国の繁栄を図る海洋都市国家の綱引きが始まる。ヴェニスやジェノヴァ、ピサなどビザンチンを通じて東方の物資を確保するための、いわゆる地中海の覇権争奪戦であり、ポルトガルやイスパニア、オランダによる大航海時代がそれに前後して新世界のルートを創り出すまでの間は、トルコの独壇場だった。
レパントの海域において、トルコがスペインの無敵艦隊に一掃され、その後ナポレオンのフランスがイギリスのネルソン提督によってトラファルガーの海戦で全滅させられるまでの近世の歴史は、まさに帝国の興亡史と呼ぶにふさわしいもので、血わき肉踊るロマンに満ち満ちている。
ナポレオンのエジプト遠征はトラファルガー海戦の少し前であったが、まさしく彼はピラミッドの前で「兵士諸君、4000年の歴史が諸君の英姿を見つめている」と演説した。指揮官たるナポレオン、そして兵士たちは、長い歴史に思いをめぐらせながら、陶然とその歴史の中に浸りきったに違いないと想像している。
時折小生は、地中海の真中に位置するサルデーニャ島の古都アルゲーロにあるホテルVillas las Tronas(渚にあり潮騒の音が聞こえ、かつてサボア王国の別荘としても使われていた)を訪れる。ここでは、窓を開け放ち、打ち寄せる潮騒の音を枕に聴きながら、ひとり静かにフェニキアの歴史やハンニバル、シーザー、アントニウスやクレオパトラなど歴史のロマンを追想することを愉しみにしている。もちろん降るような星空の神秘さを感じながら。
<中東紛争と宗教の関わり>
地中海をはさんで北海岸と南海岸に分けることは、とりもなおさずキリスト教世界のヨーロッパとイスラム教の世界に分けることとなる。今まで地中海と表現する場合、広義の意味でイタリア北岸と旧ユーゴスラビアにはさまれたアドリア海、ギリシャからトルコまでのエーゲ海を含んで地中海としてきた。
この意味においては、イスラム世界は、地中海の東岸と南岸に及んでいると言えよう。
キリスト教はちょうど2000年を経過した。イスラム教の開祖マホメットは、6世紀後半に生まれているので、つまり、マホメットの生誕までの間にはキリスト教は東地中海一帯に布教を広めて、313年にはすでにミラノの勅令によってローマ帝国に公認されるまでになっていたのである。
一方、マホメットが7世紀初期にメッカを奪還し、アラビア半島を統一することによって、本格的にイスラムの宣教活動を行い、今のイラクやイラン、そしてトルコやエジプト、モロッコなどへ徐々に広がりをみせたのである。
当然のことであるが、キリスト教世界とイスラム教世界がしのぎ合うようになるのは8世紀以降のことである。その間にイスラム勢力、この場合「後ウマイヤ朝」であるが、マグレブ(今のチュニジア、アルジェリア、モロッコ)を征服している。
一方、西の方のスペインでは、コルドバにおけるキリスト教会がそれに先立つ8世紀末に取り壊され、そこにメスキータ寺院が建立された。
11世紀、12世紀になれば、今度はキリスト教の反攻とも言える十字軍の遠征が盛んになり、北からエルサレムまでの道がキリスト教徒によって確保されている。
この間各地でイスラム教徒とキリスト教徒との小競り合いが無数にあったであろうことは想像にかたくなく、この抗争の中に互いに影響し合ったものはないのかと思うが、そのようなものは見受けられないようだ。たまたまシリアのダマスカスにあるイスラム世界の輝ける騎士サラディンの墓が隣にあるウマイヤモスクの一隅にあるヨハネの墓とほぼ同一の場所にあることとエルサレムを聖地としていることくらいであろうか。
キリスト教は昔のシリアの一地域(今のイスラエル)である準砂漠のような土地に誕生し、その地中海の北側一円に広まっていったのであるが、これはひとつにはローマ帝国の庇護があったからであろう。その後、複雑な事情により、ギリシャ正教、ロシア正教、そしてカトリックなどに分かれ、北上する形で伝播したのである。エジプトのコプト教やエチオピアなどに原始キリスト教のような形で残っているとしても勢力としてはわずかである。
これに対し、イスラムの世界はアラビア半島一帯、イラン、イラクなど東方面と北アフリカのマグレブまでの間、ほとんど砂漠を含んだ乾燥地帯に広まっていった。これには必然性があるにちがいない。
加えてユダヤ教もこの中に混成されており、キリスト教とイスラム教との3つの宗教が互いにしのぎあいながら、共存している。
もっともユダヤ教のみは、他の2宗教に対して超然としているように思われる。これは宣教による帰依によるのではなく、ユダヤ人であるとする彼らの選民思想からきているので、そう思われるかもしれない。
3つの宗教ともにエルサレムを聖地として、お互いに排除するというわけではなく、ただしそれぞれの宗旨については、絶対に妥協しないかたくなさは、現今のパレスチナ問題を見れば明らかである。メッカを聖地とするイスラム教のマホメットは、エルサレムで昇天しているので、ここはメッカに次ぐ聖地でもあるのだ。
この地中海東海岸に当たるシリア、レバノン、イスラエルはヨルダンも含めて近年までシリアの国だった。20世紀初頭になってユダヤ人国家を目指すいわゆるシオニズム運動が広がりをみせて、サイクス・ピコ協定や、バルフォア宣言などによって、シリアからの分割統治がされ、イスラエルはイギリスの委任統治領となるのである。ヨルダンやサウジアラビアの国境線の分断は、地図上で直線的になされたわけだから、そこには割り切れない諸々の事情が絡み合っていたことと思われる。その後、ナセル大統領の時代になって、この地域は、イスラエルを取り囲むイスラム勢力の結集などによって、第一次中東戦争が発生し、以後終わりの見えない戦争に巻き込まれることになる。ここでは歴史の古いそれぞれの宗教が複雑に絡み合って綱引きをしている。レバノンにおける戦争はまさにその代理戦争の見本のようなものであり、精緻に組み立てられたモザイクがこっぱみじんに破壊された結果であって容易には修復ができないのである。
元より紛争の多い地域だったわけだが、当時の大英帝国主導による斡旋案による分割統治に始まった領土問題は、今アメリカを仲裁に立てて必死にその調停をしているわけだが、アメリカをもってしてもそもそも抜本的に解決されるとは考えられない。
仮にアメリカのパワーで調停を成し得たとしても、その内実にかかわる諸問題は実に複雑なものがあり、しかも世界の大半を支配する宗教の根元に触れる地域のことであれば、なおさらのことである。
この地域において完全解決が実現するとは思えない。仮に誰かの調停によって和解ができたとしても、10年20年とする小さな時間的経過のうちに、またいつか再燃するだろうマグマの巨大さを感ずるからである。これが単に経済的利害による紛争であったら簡単に決着するであろうが、やはり宗教が絡んだ問題は我々日本人が考えるのとは違って、それぞれの民族や国家の存立に関する問題であり、部外者には理解しきれないような気がする。
これら紛争当時国に対しての日本政府の政策の決定は、難しい諸問題をさて置いて、当面の自国の経済問題にとって何が必要なのかという、目先の問題によって惑わされたりしているように感じられる。考えてみればキリスト教には理解があっても、イスラムやユダヤ教などに接する機会のない日本人にとって、この問題の調停などできるはずもなく、割り切って目先の経済問題のみに絞って政策を立案することは、あるいは正しいのかもしれない。むろん、その場合には、そのような上澄みだけをかすめるような日本の政策に対して、反発を受けることは間違いないと覚悟しなければならない。
我々日本人にとって、中東問題は、ある意味では遠い国の話のように思えるが、欧米やアラブ諸国にとっては、それぞれの国の根元に関する問題であると同時にアイデンティティーの確認の問題である。欧米などの新聞の一面がパレスチナ問題に触れることが頻繁なのに対して、日本では経済問題を除けばいつも隅にしか取り上げられない理由がここにある。
問題の根源は、キリスト教やユダヤ教、そしてイスラムの聖地が、狭いエルサレムという土地にあって、日常的に接触があることから、何かの折にすぐ発火しやすい状況下にあることにある。これは極めて不幸と言わなければならない。
ユダヤ教徒にしてみれば、3000年も前から映画の十戒によって知られる「出エジプト記」以来の住みなれた故地であり、その後アレキサンダーやローマ帝国によって国を失って以来、世界中に離散したユダヤの土地を、2000年後のおよそ60年頃前にイギリスの信託統治領イスラエルとして建国独立を許されたわけだから、死守しようとするのは当然のことである。
キリストが生まれたのがエルサレム郊外のベツレヘムであることから、キリスト教徒にとってこれ以上の聖地はないであろう。宗教のことについては詳しくは知らないながら次のように感じる。ユダヤ教とキリスト教に共通するのは、モーゼの十戒を基本にしているという点であり、旧約聖書を読めば根源が同一に帰するように思われて、この2つの宗教の格差は何とかなるのではないかと思われる。しかし、ここにイスラム教が入るとかなりややこしくなるのである。
イスラムにとってエルサレムは天使ガブリエルの案内によってマホメットが昇天したとする聖なる地であって、ユダヤ教徒がローマ帝国によって国を失って以来、イスラム教を構成するシリア人、ヨルダン人、シュメール人、ヒッタイト人、ペルシャ人、そして有史以来のベルベル人などありとあらゆる民族が、今の国境線に関係なく約2000年にわたってこのあたりの地域に生活してきたのである。いうなればイスラムにとっても故地死守というか、故地奪還というか、まことに気の遠くなるような話なのだ。
モーゼとイエス・キリストとマホメットが三者会談しないかぎり片付かないのではと思われる。
地中海を取り巻く諸国間には以上のような宗教による布教活動がからんでおり、全域に及んで征服したり征圧されたりと歴史の中に幾層にも重なり合っているのである。この地域を理解するにはこのような基本的歴史のことを知らなければならないだろう。単に歴史的建造物を眺めたり、美術館巡りのみでは、真の理解は無理である。
歴史や宗教のことに関して記述することは、この本の主題ではないし、筆者自身、その史実について歴史家のように詳しくはないわけで、このへんで宗教や戦争について書くことをやめようと思うが、最後にイスラム教の地中海を越えて西欧に与えた関係について思うまま簡単に述べたいと思う。
メッカはイスラムの開祖マホメットの生誕の地とされており、イスラム教徒にとって最大の聖地なのだが、この地は酷熱の砂漠のど真ん中に位置するオアシス都市であって、交通の便が悪い。そのため、後に布教の中心になったのはウマイヤ王朝(シリアのダマスカスが都)やアッバース朝(イラクのバグダッドが都)などである。やがて東はイラン、イラク、西はエジプト、リビア、アフガニスタン、トルキスタン、南はイエメンなど、およそ砂漠を伴う乾燥地を主として伝播していった。これは地中海の北側にはすでにキリスト教がしっかりと根を張っていて、布教活動が難しかったためではないかと容易に推測できるが、やはり砂漠で生まれた教義が砂漠の民に受け入れやすかったこともあるのであろう。
スペインの項で書いたことであるが、コロンブスのアメリカ大陸発見後、コルテスやピサロなどが米大陸に上陸して定住した都市などは、母国の風景や気候に似た土地であったことと、相似るものがある。
<国々の風土のちがいについて>
和辻哲郎の書によるまでもなく、風土というものが、民族というかそこに住む人にとって、いかに大きい影響力を持つのかについては充分に理解されるものがある。
古来、日本の国は瑞穂の国といわれているが、その前に先ず、やおよろずの「神々がおわします国」といわれている。あらゆる神々がこの国にいて、出雲の国における神々の会議によって、この国が始まったとされるわけだが、その理由はそれなりにあるのであろう。至るところに海があり、山がある。少し動けば温泉があり、寒い土地、暖かい土地、そして川の流れとみずみずしい緑は四季の変化と南北の違いを反映して、この国に変化を与えている。
山岳や湖水もあり、平野部には豊かな水田が河口まで広がっている。四季の変化もある。このことを、日本人は当たり前と思い過ぎていないだろうか。このことの不思議さについては誰も触れないで日常を過ごしている。不思議なことであると形容するならば、それはおかしいと反論されそうであるが、世界中を駆けめぐってみると、このように恵まれた国は極めて少ないのである。正しく言えば、日本は考えられないほどに、自然の美しさと豊かさに満ちていている。この奇跡的に幸運な事実について、他の国と比較してみるといい。
イスラム・アラブの国はどうだろうか。端的に言えば、砂漠の中で生まれ、どこまで行っても同じような景観の中で育ち、そして死んでいくのである。イヌイットのような極地に住む人々は、年中凍りついた大地の中で、食料も限られた暮らしをしている。違いは、半年の夜の生活と、半年の昼のみ続く世界といったものしかない。コーカサスなどの山岳に暮らすクルド人たちは、一生涯海を見ることのない山岳地帯で暮らしている。緑豊かな熱帯雨林の人々には豊かな自然があっても、四季の変化がなく、年中、蒸し暑さと暑熱の下で暮らしている。インドも然りである。中国はどうであろうか。森林を無計画に伐採し、補充の植林をすることもなく、枯れ山の状態で殺伐としている。モンゴルは草原の豊かはあっても凍土との繰り返しであろう。シベリアについては記述する必要もない。
アメリカは違う。イエローストーンやヨセミテの大自然があり、ニューイングランドの紅葉は美しく、マイアミの海は素晴らしい。とは言ってみても、国の尺度の問題がある。住む人々の生活圏を考えた場合、小麦やトウモロコシだけの世界、牧草地だけの世界、ネバダやニューメキシコの半乾燥地の世界など、飛行機を使わない場合の日常の生活では他と全く隔絶されている。人によっては単に小麦畑しか知らないというように、単純にして気の遠くなるような、過酷な大地であると形容してもよいくらいだ。
無論全体として考えれば偉大な大地であることは誰の目にも明らかではあるが、飛行機で飛べばすぐそこというのはごく最近のことである。動力や通信のない時代からの先祖以来の生活状況を見れば、そのなかで、性格や気質が育まれて来たことには違いない。
繰り返すことになるが、日本という国はいろいろな面で真に素晴らしい自然に恵まれた国で、どんな所に住んでいようが、海や山、湖や川、温泉など、あらゆる景観が配置されている。四季の移り変わりは繊細な感情をはぐくんできた。このことは、あうんの呼吸でお互いが理解し合える土壌を形成したことに結びついている。まあまあ、なあなあで細部に及んで明文化しないでも理解し合える独特の性格形成につながった。
日本では、やおろずの神々が君臨したとしてもついには共棲できるようになったのである。それぞれの家に神棚があり、仏壇があり、クリスマスにはキャロルを歌って喜び合えることになるのだ。これほど寛容で住み易い国はないと言っても言い過ぎにはならない。
だが大概の国の人々にとっては、これほど不思議なことはないだろう。砂漠の国の人にとっては、緑滴る国は思い描くことはできても実感が伴わない。熱帯の人にとっては雪国の人の生活には思いが至らない。したがって、各々その人の出自によってその地を支配する宗教観なり世界観で自分の主張を押し出してくるのである。このことは自己主張すべき個性の発揮と一体になっており、中途半端な妥協には同意しない性格となって現れてくる。
キリスト教世界では、教義を基本にすべてが成り立っているので、その点で、日本人との違いが見られる。もちろんイスラムもその通りである。このように、イスラムやキリスト教など、確立された教義が生活の全てを律している国々については、それが良いとか悪いとかの論評の問題をとっくに超えている。ユダヤ教などはさらに戒律や選民思想が強烈で剛直な生き方を変えたりはしない。
日本人が外国人に対する場合、日本の心、すなわち神道的なもの、あるいは仏教的なものの考え方に基づいて(もちろんこの中にキリスト教であろうとイスラム教的なものであろうと何でも良いのだが)、自分の考えはこうなのだ、このような考え方で自分を表現しているのだと、道筋をはっきりさせて自分の生き方に自信を持たなければいけない。そうでなければ、自分に対する評価はなされないことになる。彼らにとって無宗教的な、すなわちアイデンティティーのはっきりしない生き方は理解し難いことなのだ。
教義の下で全てを律した生活をしている国の人々にとっては、融通(ゆうずう)無碍(むげ)にもみえる日本人が怨めしくも思えることがあるかも知れない。(明確な思想的、宗教的背景のない日本人はやはり理解し難く優柔不断だとして、何を信用してよいか判らないという評価につながりかねない)。このことは国際政治の局面では重大な問題をはらんでいるように思える。一般市井の暮らしの中だけなら良いのだが、それ以上の立場にあり重要な職責にある人達は、このことをよくわきまえておかねばならないだろう。
<暗殺集団の今昔、オサマ・ビン・ラーディンとアサシンについて>
2001年9月に発生したニューヨークの世界貿易センタービルの爆破事件は世界中の耳目を集めた近世まれに見るテロによる大事件である。事件の全容が解明されるにつれて、それがオサマ・ビン・ラーディン率いるアル・カイーダというイスラム過激派によるものと断定された。結果としてビン・ラーディンをかくまったアフガンにまで戦火の災いが及ぶことになった。この事件以後、イスラムの世界についてのニュースが日常的に、紹介されることになり、ムジャヒデイン、ラマダン、などイスラムに関する用語が我々の日常生活の中にも入ってくるようになった。
報道の中で、カブール、ヘラート、マジャリシャリフ、カンダハルなどのアフガンの地名が頻繁に出てくる。古来この地はアジアとヨーロッパを結ぶ最も重要な位置にあり、アレキサンダーのペルシャ攻め、またモンゴルやチムールが地中海方面に遠征する場合も必ず通る要所であった。アーリア人がインドに侵入した時も、ジプシーがヨーロッパに押し出された時も同じだ。避けては通れない位置にあるのがこれらの都市である。今では航空機や船による物資の輸送が中心になり、ほとんど顧みられなくなった地域だが、近世以前は世界の交通の要衝だったのである。
アフガニスタンと現在呼ばれる国は、そのような理由から、ありとあらゆる民族が定着して形成された国である。さらに峻険な山岳地であることが拍車をかけ、部族毎に無数の集落自治が行われるようになっている。アル・カイーダなる組織に中央アジアとか、アラブから多国籍の兵士が加わっているのも、このような理由からである。極言すれば、アフガニスタンは、誰の、どの民族の国なのか判然とせず、その意味において考えてみると、不幸な国と言えるかもしれない。
さて、中世の頃にこの周辺にはびこり、近隣諸国を震撼せしめた「アサシン」という組織をご存知だろうか。現在のイラン北部に位置する、山深いアラムートという場所で実際にあった話である。イスラム教シーア派の分派でイスマイリ派と呼ばれる集団が、「山の老人」といわれる首魁(しゅかい)にひきいられ、エルブールズ山脈奥深くの「アラムート」に城壁をかまえ、自己の主張に合わないものを片端から暗殺し、ある時期に近隣諸国に大きな影響力を持ったという有名な史実である。
その常套的な手口は、生活に苦しむ若者、身寄りの無い孤児等を集めて、養い、自己の都合に合わせて教育し、殺人の手先にしたことである。
必要な時はハシッシ等の麻薬を利用して眠らせ、特別に準備された場所に、美酒、珍肴、そして美女をはべらせて、彼らが求めるままに快楽を与え、そこが天国であると言い聞かせ洗脳したのである。
その後また麻薬で眠らせ、通常の質素な生活をおくらせ、必要に応じて「また天国に行きたくないか」とけしかけて、天国に行くためには、誰某を殺してこいと、命じて実行させたのである。命令を受けた若者は、その快楽が忘れられず、喜んで実行に向かった。この歴史的事実は何かを示唆しているようである。
現代における麻薬の第一に「お金」があげられ、人によっては「ベンツ」など高級車もそれに当るだろう。テロリストのオサマ・ビン・ラーディンは巨億の富を持ち、アル・カイーダと呼ばれるテロリストの幹部に惜しげもなく、札束や、ベンツなどの高級車を与えたとニュースなどによって知ったのだが、それを聞いてこの「山の老人」率いるアサシンを思い出した。
イスラム世界では、不便きわまりないような中世的生活でさえも甘受する人々が多く存在し、現代の豊かな文明の恵みをうけている欧米風の社会生活との間には大きな価値観の違いがある。
しかしながら、このたびのアル・カイーダやタリバンの、アメリカ、すなわち西側世界に対する敵対は何を示唆しているのであろうか、彼らの犯した行為はあまりにも卑怯かつ残忍で、いかなる釈明も絶対に許すことの出来ないものである。アメリカや同盟国の懲罰行動は当然である、断固支持する。
しかしながら、そこまで彼らを追いつめた原因が何であったのかについて、考えなければならないことも多々あるのではないだろうか。